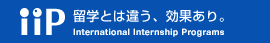フィンランド
・折り紙
『鶴』と『箱』を用意し、パワーポイントスライドで手順書を作って臨みましたが、難しすぎるようで、毎回苦戦、時間内に終わらないこともありました。学年に合わせて少しずつレパートリーを増やしています。各クラスに設置しているスタンド型のカメラで手元をスクリーンに映しライブ感覚で見せながらやると効果的でした。
・ソーラン節
1,2年生に教えました。限られた授業時間で「踊れた達成感」を味わってもらいたかったので、繰り返しの振りだけ教え、あとは好きに踊ってもらっています。覚えやすいのか生徒の達成感はあるようで、見ている先生のウケも良いです。回を重ねてレクチャー資料を改良していく中で、大人のまじめなレクチャービデオよりも、運動会のソーラン節を見る方が子供はより集中し、振り覚えも良いことがわかりました。
せっかく受け入れてもらったからには、全員満足の...は難しくても、なるべくたくさんの生徒に楽しんでもらえるような文化紹介がしたい。
教職も特殊技能もない自分が、生徒たちに何を与えられるか、どんな経験を提供できるか、考える日々です。
お世話になったクラス担任の先生たちに、感謝の気持ちで変形手裏剣をプレゼントしたら、とても喜んでくれました。
日本の文化を学校やホームステイ先で紹介するたび、「すごいね」と驚かれますが、興味を持ってくれた人から追加で質問された際に即座に答えられないことがよくあり、自分は日本のことについてまだまだ知らないことが多いなと痛感しています。
健康上のハプニングがあり病院を受診する際、言葉の壁が高く苦戦しましたが、ホストファミリーや小学校の先生たちが助けてくれました。本当に感謝です。
活動の合間に、adult high schoolでフィンランド語を受講して勉強もしています。
1か所目の滞在は残り1か月ほどですが、この後も別の小学校や教育機関を訪問、近隣保育所で日本の文化紹介等もさせてもらう予定です。
私自身の教科が社会科であるため、日本語クラスに参加する以外は、歴史や政治、宗教の授業によく参加させてもらっていました。その他にも、英語や心理学の授業に参加させてもらう機会が多かったです。そのなかで、各教科の授業で取り上げるテーマに関連した内容で、日本の文化や社会について紹介する時間をもらいました。
歴史、宗教の授業では、『日本の宗教と文化』というテーマで日本の文化や社会における宗教の影響、考え方について紹介しました。宗教というテーマは表現や伝え方が難しかったですが、この授業をきっかけに先生方と宗教やそれぞれの国の文化について話をすることもでき、改めて日本について考える機会にもなりました。
1月に入り、次は「日本の教育制度」というテーマで話をする時間をもらいました。生徒には日本の文化について興味があること、知りたいことのアンケートをとりましたが、やはり日本の高校生の学校生活に関心があるようでした。また、今月は今学期のテスト週間に課題の一つとして書道にも取り組みました。まず、自分自身の「今年の漢字」を調べて決めてもらい、その漢字を書きあげるという内容でした。自分で選んだ好きな漢字を納得いくまで黙々と書き続ける生徒が多く、数を重ねるごとに上達していく様子を見せてもらい、純粋に嬉しかったです。
来月から第4学期が始まりますが、引き続き日本語クラスが開講されるため、次の文化紹介について考えていきたいと思います。
授業① 寿司パーティー
高校3年生の英語の授業で国際理解と称して、寿司パーティーを開きました。巻き寿司と握り寿司、インスタントの味噌汁、緑茶という簡単メニューでした。授業時間54分におさめるために、英語の先生と相談して、酢飯と錦糸卵は事前に用意して、後は具材を海苔で巻くだけ、握って鮭やいくらを載せるだけ、という段取りにしました。生魚を食べれないという生徒や卵アレルギーの生徒もいましたが、巻いたり握ったりする作業は楽しそうに取り組んでいました。片付けの時間まで入れると若干時間切れの面もありましたが、ワサビや折り紙で作った箸袋などは生徒にも先生にも好評でした。ただ、残った食材や巻きずしの切れ端などを容赦なく捨ててしまうのを見て、米の一粒まで大切にする意識やもったいない精神などについても事前に触れておけばよかったと反省しました。
授業② 日本の高校との交流授業
日本の高校と異文化交流授業を行いました。時差の関係で、フィンランドの午前中の英語の授業と日本の授業の時間帯が合わず、日本の高校には放課後に有志を募ってもらい交流が実現しました。接続の準備や打ち合わせの時間を考慮して、交流時間は正味40分としました。双方の出席者が10名程度だったこともあり、自己紹介とそれぞれの学校紹介の後、質疑応答という構成で時間内に収まりました。お互いに、緊張していたのとシャイなのとで、最初はぎこちない場面もありましたが、後半は日本側の生徒が活発に質問をしていたのが印象的でした。英語力の差はあったと思いますが、コミュニケーションをしようとする姿勢が大事だということが生徒自身にも理解できたのではないかと思います。終了後は、双方のホームページやSNSに授業の様子を掲載したり、リンクを貼ったりして、発信することもできました。
授業③ 折り紙教室
小中学校へ折り紙の出前授業に行きました。折り紙の経験がある生徒もいましたが、手先を細かく使うことや、折り紙特有の紙の折り方は、慣れない分難易度が高いようで、年齢を問わず苦戦しつつも楽しそうに取り組んでいました。完成したものを眺めて楽しむだけでなく、使ってほしいと思い、折り紙でブックマーカーを作成しました。アニメのキャラクターや動物をモチーフにしたもので、顔や名前を書き込むとオリジナルのブックマーカーが出来上がります。そのまま、宿題の個所に挟んでもらい、「これで全員宿題を忘れないね」などと声をかけると、生徒もまんざらでもない表情を浮かべていました。ポケモンのブックマークが大人気で、黄色の折り紙を大量に使いました。12月には、クリスマスシーズンのためサンタクロースやクリスマスツリーの折り紙を取り上げました。こちらも、メッセージカードや飾りつけに使える実用的なものを意識しました。この時は、赤の折り紙を多く使いましたが、途中でなくなってしまい、赤い包装紙を正方形に切って代替しました。サンタのメッセージカードに「love」を日本語で書きたい、と尋ね
た生徒がいて、「愛」と黒板に書いたところ、クラスの生徒全員が黒板に「愛」と上手に書いたのを見た時は、不思議な気持ちと感動とで胸が熱くなりました。
授業④
中学2年生、3年生に日本語の授業をしました。日本のゲームやアニメは中学生に浸透しており、アニメの声優の声を生成する無料ソフトを使って、ひらがなやカタカナについて説明しました。象形文字、指示文字、会意文字の漢字の意味をクイズ形式で出したところ、イメージを膨らませて漢字の成り立ちや意味を理解してくれました。基本的に、マンガの吹き出しにはすべて振り仮名が振ってあるので、ひらがな対照表でセリフの読み方を拾って、google翻訳の日本語の枠にローマ字入力すると、英訳やフィンランド語訳が出てきます。生徒の前でアプリやソフトを使ってみせると、ハードルが下がり興味をもってくれたように思います。
自分の名前をひらがなやカタカナで書く、というシートを作りましたが、フィンランドの名前は日本語で表記しにくい発音や、ja(ヤ)、vo(ヴォ)など対照表に書かれていないものも多く、理屈を説明するのが非常に難しかったです。
フィンランドの高校は基本的に単位制で、部活動にしっかり取り組みたい生徒など、4年間かけて卒業する生徒も一定数いますが、日本の高校とほぼ同じ学齢です。生徒たちは、素朴でシャイな印象ですが、打ち解けると流ちょうな英語と笑顔で話してくれ、日本の高校生と変わらないな、と感じます。一方で、自律性、自立性を尊重する国であるためか、服装やメイク、髪形などは驚くほど大人びています。多くの生徒がピアスや髪染めで自己表現を楽しんでおり、日本の制服文化や服装検査の話をすると驚きと関心をもって聞いていました。自動車で通学する生徒も多く、校外学習に生徒の車に分乗して行った時は不思議な気持ちになりました。また、フィンランドでは高校生でも低アルコールの飲酒が認められています。(「二日酔いで登校することはある?」との質問には、愚問とばかりに即「NO!」と返ってきました。)週末にバーで生徒に会って、「このお酒は飲むべき!」と薦められたのは衝撃的な体験でした。
ヨーロッパではタトゥーをしている人も多く、私自身の認識も大きく変わりました。フィンランドではタトゥーが許されるのは18歳以上からなので、高校でタトゥーを彫っている生徒はいませんが、祖母との思い出や好きな花など、卒業後に向けてすでにモチーフを決めている生徒もいます。「一生消せないからこそ、慎重に大切に決める」と話していたのが印象的です。
授業中は、トイレはもとより、教室内の移動、飲み物や携帯電話も基本的には自由です。当初は、急に立ち歩いたり電話が鳴って教室から出ていく生徒たちに「えぇ~!」と驚き、その度に先生を凝視してしまいましたが、授業中の規律は守られ、発言も活発です。自由なのに崩れないという状況を目の当たりにして、日本の高校の規律の厳しさについて考えさせられました。(ただ、ニュースなどでは、生徒が授業中に携帯電話やパソコンでゲームをしているという話も聞くので、学校や授業担当者によるものも大きいのかもしれません。)
多くの授業でペーパーレス化が進み、紙の教科書も希望すれば使えますが、ほとんど見かけません。筆記用具を持参しない生徒も多く、私がワークシートを使う授業をした際には、貸し出し用の鉛筆を取りに来る生徒の列ができました。日本でもかなり普及してきましたが、定期テストも支給されたPCで行っていたのは驚きました。(故障が多いので扱いを丁寧にしてください、という学校からのアナウンスが時々入ります。試験監督をしたときに、生徒のパソコンの電源が入らず往生しました。)また、私が受けている英語の授業では思った以上に宿題が多く出されます。授業担当者はPC上で課題の取り組み状況を見ることができ、進捗状況が成績に反映されます。生徒たちは放課後や空き時間を利用しているようで、取り組みの質、理解度共によいのも驚きました。フィンランドの大学入試にあたる高校卒業資格試験は、完全デジタル化され、1科目6時間という長丁場なので、生徒たちは進学を見据えて主体的に学習に取り組んでいるように見えます。基本的に先生、生徒双方に「学習はさせられるものではない」という共通理解があるからではないか
と感じます。
・6年生の選択授業の1つで、理科を担当
・放課後のサッカークラブの指導
・5、6年生の英語の授業のT2
・特別支援教室のサポート
・水泳授業の引率
< 学校での公共施設の利用 >
学校にプールの施設がないため、体育でプールを実施する際は、市内の公共施設を利 用している。9月~12月上旬までの期間で各クラス4回、施設利用の時間割が割り当てられている。水泳の授業はその施設のトレーナーが行っている。
現在は、学校から自転車で10分ほどの所にホームステイをしています。ホームステイ先のご夫婦の子どもたちはすでに自立していて、ご夫婦と私の3人の生活ですが、本当の家族のように接してくれ、フィンランドの家庭や文化について深く触れる機会に多く恵まれています。社会教育が進んでいる国なだけあって市民講座も充実しており、週に3回フィンランド語講座、編み物講座に通って、余暇活動の重要性を実感しています。
研修校では、英語科の先生が国際交流の担当として私の受け入れ責任者となっており、小中学校との交流や生活全般の渉外をお世話してくださっています。私自身は、生徒と先生の中間のような立場で、日本の文化や社会について毎週2回のペースでプレゼンテーションを行ったり、生徒と英語の授業を受けたり、英語科以外の授業を見学に行ったりしています。基本的には毎日英語の授業に出席し、生徒と同じように当てられたり、ペアワークをしたりしていますが、日本での専門が高校公民科だったこともあり、自分の英語力の低さに日々苦労しています。
まずは先生方の働き方、職場環境についてです。職員室は、机や書類が並び授業準備等を行う部屋と、ソファが並びコーヒーを飲みながらリラックスできるスペースに分かれています。リラックス空間は、多くの先生方が談笑しながらコミュニケーションを取る大切な場であるということを日々感じることができます。先生方は研修生である私を温かく迎え入れてくださり、いつも気にかけてくださいます。担当教科に関係なく、すべての先生が当たり前に英語を話されることに驚きました。先生方は、基本的に担当授業までに出勤し、授業、やるべきことを終えると帰宅するため16時にはほぼ職員室が空っぽになります。帰宅後や週末など、自分の好きなことのために使う時間が日々の生活において大切だとおっしゃっていました。まさにワーク・ライフ・バランスを実現しているなと感じます。
続いて、授業についてです。授業は5学期に分かれており、生徒は各学期で自分の受けたい教科を選択し登録します。そのため、生徒も自分の授業時間に合わせて登校し、終われば帰宅するため日本でいう大学生のような印象を受けました。教科を問わず様々な授業を見学させてもらっていますが、どの授業にも共通していることは、生徒の主体的な活動が中心であるということです。1クラス75分授業ですが、生徒たちはその時間のトピックに基づき、多くの時間をグループワーク、調べ学習、課題などに費やします。生徒達が自分で考え、活動する時間を大事にしているということがわかります。また、自分の考えや意見を表現することについても1年生の初期段階から学んでいます。表現、発表方法についても、ゲーム作成やプレゼンテーション、パワーポイントの作成など様々です。生徒が自主活動に取り組む際には、教室外の好きな場所で行ってもよいという自由な雰囲気も見てとれます。先生方は、知識を教えるのではなく、生徒達の主体的な活動をサポートし、導いていくという姿勢を大事にしているのだということを、どの授業からも感じ
取ることができます。
今後も、日本との共通点や相違点について感じ考えながら研修を続けさせてもらいたいと思います。
スロベニアから来た先生は20年以上教員として働き今月退職したとのことでした。9月からはエラスムスの学生としてまた勉強し始めるとおっしゃっていました。今回会ったスロベニアの先生以外にも、数十年働いてまた学生として学び直すという人に何人か会ったことがあるので、海外では日本よりいろいろな選択肢があって自由に自分のベストを選びやすい環境にあると感じました。
ギリシャとスロベニアの先生と教師の働き方についての話題になりました。ここ数年でどの国でも教師の働き方は大きく変化してきたようですが、やはりフィンランドが一番働きやすそうという話になりました。その先生の話によると、スロベニアではたまにサービスで働くことがある、という話であったり、ギリシャではなにを決めるにも会議が必要で、支援の子に対する決定も難しい時があるという話からでした。確かに、数ヶ月先生方を見てきて給料、休暇、教師の負担、保護者からの信頼という面でもフィンランドではワークライフバランスがとりやすいなーという印象がありました。話を聞きながら日本と比べ、日本の先生は本当に負担が多すぎると実感しました。ただ、そのフィンランドでも今のようになるのに10年以上時間がかかりゆっくり変化してきたと言っていたので、働く環境を変えるには時間と労力がいると感じました。
ある先生が説明してくれたところによると、頭も体も起きてないから、ゆったりとした授業をしているよと教えてくれました。たしかに二ヶ月の休み後なので児童も体が学校モードに切り替わるのに時間がかかりそうとみていて思いました。
今週は基本的に自分のクラスでの授業がメインでした。クラスのルールを確認したり、タイムスケジュールを共有したり、と事務的なことをしたり、夏休みの思い出を発表したり、と新学期の最初は日本と似ているような活動をしている先生が多かったです。
新しい学年になったということで、自分のプロフィールを書かせている先生がいました。その先生はただプロフィールを書くだけではなくて、サイコロを使って出た目によって一人一人違うプロフィールを作るということをしていました。少しの活動でも子供達がワクワクするような仕組みを取り入れていて、この方法は日本でもできるなといいアイデアを吸収できました。今週は初めということで9:00から13:00のタイムスケジュールでしたが来週から本格的に通常の授業が始まります。少しずつ体を夏休みモードから学校に切り替えて行きたいです。
そんな長い夏休みを終えて久々に学校へ行きました。新しい先生を交えてミーティング。一人一人自己紹介をするのは日本ではなかったことなので、先生方一人一人の言葉を聞けていいなぁと思いました。ミーティングは勤務体系や、職務に関する基本的なことが中心で、年度途中で参加した私は知らないこともあり、でも基本的なことは日本とそんなに変わらないかな?と思ったり。
ミーティング後は玄関に集まり、下足箱をどう使うか全員で話し合いをしました。全員で話し合う中で年や、年数関係なく自分の意見を言っている先生方の姿に、一人一人の意見を持ち、伝えることを大切にしている様子がわかりいい関係だなと思いました。
その後は、1人の先生が所有しているフローティングサウナに先生方と一緒に。船のようなものにサウナがついており、クルージングを少し楽しんだあと、サウナに入りそのまま湖で泳ぎました。サウナで歓迎会をするのもフィンランド流だなとフィンランドカルチャーを体験しました!
フィンランドの子供は思っていた以上にシャイで、それでもとても優しい子が多いです。フィンランド人はとても優しくいつも気遣ってくださいます。その性格から学ぶことも多く、自分を見つめ直すきっかけになっています。
日本の学校の改善点、良いとところも自分なりに感じれました。教育そのものの違いますが、先生たちの働く姿勢が全然違っていて、いい具合に凝り固まった考えが解されたように思います。4月から仕事に復帰し、今の私は、仕事への向き合いかたが変わりつつあります。
また、様々な場所を訪れると、そこに新たな出会いがあります。そこで「教師」「学生」「父親・母親」「祖父・祖母」「現地人」「外国人」など様々な立場の人たちと話をすることで、それぞれの視点から考える「教育」について意見を聞くことが非常に楽しいです。自分とは異なる経験をしてきた人たちの話しを聞くことは大変興味深く、貴重な体験をすることができています。
時間がいくらあっても足りないと感じる日々ですが、帰国の日は着々と近づいてきています。一つひとつの出会いを大切にし、また、支えてくれている人たちへの感謝の気持ちを忘れずに、最後まで充実した生活を続けていきたいと思います。
ホストファミリーもホストスクールの先生たちも本当にあたたかく迎え入れてくれ、私はいつも笑顔で過ごすことができました。恵まれたことに、「辛い」「悲しい」と思うことは一度もありませんでした。唯一「悲しい」ことと言えば、帰国後ここに戻ってくる日が確定していないことくらいです。でも、いつの日か必ず、もう一度フィンランドを訪れたいと強く思っています。
一年間続けた「日記 兼 レポート」はかなりの容量になりました。日々の出来事を日記形式で写真ととも書き溜めたので、帰国後はこれを一つの本にまとめたいと思っています。成果を形に残すことができるということは達成感にも繋がるので、毎日コツコツと続けてきて良かったなと思っています。(これは、今後留学を予定している人たちに自信をもっておすすめします)
帰国に際し、たくさんの人たちから「ありがとう」という言葉をかけてもらいました。今の私の心は、一言では到底表すことのできない、充実した温かい気持ちで満ちています。
今後の私の目標は、この経験を活かして次のステップに進んでいくことです。まだまだ自分の可能性を信じているので、今後も学び続け、飛躍を目指していきたいと思います。それと同時に、自分を同じように学ぼうとしている人たちへのアドバイスや、子どもたちの可能性を広げるサポートに力を入れていきたいと思います。自分に何ができるのか、考え始めるとワクワクした気持ちになります。
最後になりますが、このような充実した経験ができたのはたくさんの人たちのサポートがあったからです。支えてくれた全ての人々に心から感謝し、同時に今後も成長し続けることを約束することで、少しずつ恩返しをしていけたらと思います。ありがとうございました。
ALL IS OK. You choose.しなければならない、ではなく、自分で決めなさい。
この言葉は、はじめは素晴らしいと思っていましたが、だんだんと苦しくなってきました。
自分が選択しないと誘ってはもらえません。日本の文化として遠慮するという行為がうまく通じずにただの行きたくない、ととらえられ、気持ちがすれ違ったり、食べたいときに自分で食べるという習慣も勝手に冷蔵庫を開けることに抵抗がある日本人にとっては気を使いうれしいことに体重が減っていきました。外国で暮らすということは素晴らしい発見もたくさんありますが日本の素晴らしさもたくさん感じることができました。
とは言うものの、近くにある室内プールにはたまに泳ぎにいきますが。(^_^;)
ホームステイでなく、別な学校(スエーデン語の高校生のよう)の寮に入れてもらっており、独り暮らしになれた私には気楽でいいのですが、朝食の短い時間に高校生と食堂で挨拶を交わす程度の付き合いしかできません。従って、学校の休みの時期は人との交流がなくなってしまいがちです。
①薬に頼りすぎない:こちらは物価が高いこと、また薬局が日本のドラッグストアのようにあちこちにあるわけではなく体調が悪い時に気軽に行ける距離にないことから、スーパーで買えるものの中で体調不良にいいものを購入しました。みかん、はちみつ、レモンティー。しょうがとはちみつの飴。米と卵とだしで雑炊。ビニール袋を三重にしてアイスノンを作りました。
②マスクを外でつけない:こちらの人はマスクをつけて出歩く人を見ると、重病人or毒テロリストor手術を抜けてきた医者と思うそうです。ヨーロッパ人はアジア人のマスクの原因は大気汚染のためと思っており、風邪予防とは思っていないのでかなり注目されるとのこと。同じ学校の先生が日本に住んでいたこともあって教えてくださっていたので私は注目を浴びずに済みました。
③病院は最後の手段:こちらは、体調が悪くなったら3日くらいは休養して様子を見るようです。病院に行こうにも、予約の電話をしてその日に行けることはなく、待たなければならないため、こちらの人たちは「病院に行けばいい」ではなく「病院に行かないでもいいようにしよう」を考えの根底に持っています。自立した暮らし、というものとも関連性を感じました。
今回、体調不良から異文化を学習しました。
ただ、特別英語の勉強を熱心にしているわけではないので、自身でその理由を考えてみました。「他の日本人とは違う」という言葉もあったので、何が違うのかも考えてみました。
私の結論は、「答えを出すスピード(判断力・決断力)が一つのポイント」ということです。
これは私が教師として子どもたちにぜひ身につけて欲しいと願っている力の一つですが、判断力・決断力の不足は、成長の機会を逃してしまうのではないかと考えました。
時々出会う日本人旅行者などの様子を見ていると、相手からの投げかけに(問い)に対して「どちらでも良い」「ひとりでは決められない」「分からない」という答えでモゴモゴしている人が多いような気がします。
これは私の性格ですが、基本的に相手からの投げかけに対してスパッと答えを出すので、その結果会話がスムーズに進行し、自然と会話量も増えていったのではないか。そしてこれが上達のポイントだったのではないか、と考えました。
(ふと、「Noと言えない日本人という言葉があったな...」ということも思い出しました。)
「空気を読む」「周りの様子に気を配ることができる」という習慣があるのは日本人の誇らしい部分でもあると思いますが、時にその度が過ぎるのは、自分の成長のチャンスを逃してしまうのではないかと思います。
さて、私は会話力の上達を褒められましたが、「英語で文を読むこと、書くこと」の上達はまだまだだと感じています。今後はそちらにも意識を向けつつ、それでもやはり今の「英語を使って実際にコミュニケーションをとることができる」という貴重な環境・時間を楽しんでいきたいと思います。
さて、今回はこれから海外に留学する方へ一つアドバイスができればと思います。
それは、「まずは何事も積極的にチャレンジしてみること」です。当たり前のことかもしれませんが、私はこの「基本」のおかがでたくさんのチャンスを得ることができました。
日本文化(日本語)の授業依頼はもちろん、通常の授業のサポート、放課後や週末に映画やコンサート、パーティーへの招待など、本当に多くの誘いを受けることができています。それも特定の限られた人だけではなく、研修先の先生方やホストファミリー、友人、さらには「友人の友人」からも声をかけてもらっています。
これは、私が「とても温かい心遣いのできる、素敵な人たちに囲まれて生活することができている」という恵まれた環境にいることも理由の一つですが、先日ふと「私はたくさんのイベントに参加することができて幸せだ」という話をしたところ、「それは、あなたが『どんなことでも、なんでもやってみよう!!』という姿勢だからよ。私たちも誘いやすいもの」という返事が返ってきました。
これが、私がこれから留学をされる方に伝えたいエピソードです。
積極的な方、控えめな方、それぞれ性格は異なると思いますが、誘う側として考えたら「あの人なら楽しく参加してくれるかも」と思える人に声をかけることが多いと思います。
嫌なこと、辛いことを無理して続けることはありませんが、「まずは一度チャレンジしてみる」ということは、大切なことだと思います。(その挑戦の中で新しい出会いを得る機会も多くありました。)
当たり前のことですが、改めてお伝えできたらと思います。
これからも一つひとつの出会いに感謝の気持ちを忘れずに、残りの数カ月もまだまだ楽しみたいと思います。
フィンランドでは、特別支援学校中等部や通常の学級の支援級卒業後は、特別支援学校高等部ではなく、主にこうした専門学校(職業訓練校)への進学となるようです。調理、メディア、木材加工、コンピューターなど様々な専門領域のクラスに加えて、その専門を決めるためのクラス(VALMA)、将来の就労や自立した生活の準備のためのクラス(TELMA)があります。
半月ずつ入らせていただいた2つのTELMAクラスでは、それぞれ生徒が必要とする支援やその度合いが異なっていましたが、どちらのクラスでもクラス担任の他に多くのアシスタントの先生(教員ではない)がついていて(そのうちの一つのクラスでは、マンツーマン)、生徒たち一人ひとりがとても手厚い教育・支援が受けれているように思いました。そして、どちらのクラスも先生とアシスタントの先生との間での情報共有・意見交換が活発に行われていて、チームの連携を強く感じました。
専門学校なので、日本の特別支援の生徒の一般的な進学先である高等部(普通科)との簡単な比較はできませんが、より就労への実践的な経験を積む時間や、個々、少人数での活動が多かったです。障害者の就労についてはどちらの国でもまだ厳しい現状がありますが、学校を卒業した後の特別支援の生徒の将来について考える、よい機会となりました。
まず違うこと、先生たちが怒らない、子供もひとりの人格として認めている。その状況の最たるものが子供は教師をファーストネームで呼ぶ。(違和感)
次に、日本から持って行った教師の必須用具赤ペンが何の役にも立たない。教師は評価しない。〇×をつけない。〇などの評価を教師からもらうために学習するのではなく内発的動機で学習に臨むことを1年生の段階から経験させる。型にはめる日本の教育と違って、なんでもあり、教室にはソファーがあり、学校は楽しいところをアピール?×だなんて付けたら子供のモチベーションが下がる。(つい間違いを指摘してしまう)
そして何より、少人数指導!!クラスの人数も多くて20人程度、それでも2グループに分けての指導が行われる教科もある。それだけ専科の先生やアシスタントの先生がたくさんいる。子供たちの教材はもちろん給食費も無料、教育にお金をかけていると感じる。1日4時間から6時間の授業、掃除もなければ給食指導も委員会活動もない、ランチ、スナックをとり、子供も教師も3時には下校。(プレッシャーが少ない)
つくづく日本の教師は頑張っていると思います。でもそれが子供を幸せにしているでしょうか?教師自身も身を削って、子供たちもそれにこたえようと頑張っている姿は美しくもあり、悲しくもあるような気がします。少なくとも今の日本の教育に耐えられなくなっている教師や児童がいることは事実です。
文化が違うのですべては受け入れ難いですがこれからも新しい教育の形を考えていきたいと思います。
他の参加者の方も利用しているようですが、おりがみくらぶは様々な折り紙が様々な言語で紹介されており、ビデオもアップロードされているのでインターン活動を助けてくれるウェブサイトの1つだと思います。
日本語で生徒の名前を書いていくことも人気でした。生徒に直接名前を聞けば、生徒との距離感も縮まります。生徒の名前の意味を教える等もかなり喜ばれました。例えば、エラという子がいたら、エラは日本では魚の一部分を表すんだよといった感じです。もちろん日本語には同じ発音でも違う意味を持った言葉が多数あるので、それも含めて教えるとより興味がひけるかもしれません。
日本とフィンランドの面積はほとんど一緒なのに、人口は?とかやると意外と食いつきがいいです。日本とフィンランドの全体の土地面積における森林面積がほとんど同じ(フィ69%・日67%)など、日本は都会というイメージが強いらしく驚かれました。身近な話題や生徒のイメージを覆すようなものがいいのかもしれません。
海外研修で大切なことは、「自分のやりたいことを諦めずに挑戦すること」です。そのためにも、自分の意見をしっかり口に出して積極的に行動することの重要さを学びました。また、「異なる環境でも柔軟に対応し、適応すること」の必要性です。思うように物事が進まない時、想像と異なる環境でもその場を楽しむことで適応していくことの大切さを痛感しました。
まず、ロンドンの語学学校には、本当に様々な国から学びに来ていました。授業中は静かに聴くというイメージの日本とは違い、常に質問や感想を発言し、会話しながら進むことに最初は戸惑いました。しかし、「英語での会話力を磨きたい」思いを忘れず、臆することなく発言する中ですぐに慣れていき、楽しくなりました。積極的な会話によって適切な英語表現も学ぶことができ、多くの友達もできて、授業外でも海外生活を満喫することができたと感じます。
次に、フィンランドの研修校(日本でいう小学校)では授業アシスタントをしました。そこでも進んで先生方や子供たちに話しかけることで信頼関係を築くことができ、より日本に興味をもってもらうことができました。また、自分の希望や思いを伝え行動した結果、研修校以外の学校見学も実現し、日本文化を紹介する機会も多く与えていただきました。積極的な行動によって現状を変えられることを実感したのです。もちろん慣れない海外生活の中での不満や、日本と異なる習慣や環境での戸惑いもありました。そこで「何事も学びのチャンスだと思い、どんな状況も楽しむこと」で柔軟な対応ができたと感じています。最後に、丁寧な説明と多くの支援をいただいたインターンシッププログラムスのスタッフの皆さん、アドバイスをいただいたOGの先輩、現地での多くの仲間や先生方に大変感謝しています。本当にありがとうございました。
研修校とは異なる小学校からも要請があり「折り紙授業」を行った。小学1年生~4年生では、簡単な「魚」を作り、好きなデザインを描いたり好きな色で塗ったりした。絵を描く作業がとても好きな生徒が多く、楽しんで行うことができた。また、動物がとても人気で「キツネ」や「ネコ」を作った。
<映像での日本紹介>
パワーポイントで日本の季節やイベント、自分の勤めている学校の紹介を行った。教室にはパソコンやプロジェクターが設置されているため、授業が進めやすく自分のUSBも使用することができた。子供たちは感想や質問をどんどんしてくれるので、説明する方もやりがいを感じた。
(日本で言う)2年生から英語の授業が始まる。4~6年生にもなると、英語をスラスラ話せる子供も多くて驚いた。もちろん、町中(お店など)はほとんどの人々が英語を話せる。また、フィンランド語(母国語)の他に、スウェーデン語の授業もあるため、子供たち学習は多岐にわたっている。また、私の研修校は自然豊かな町中にあり、広い敷地と敷地ないに森林がある。
先週の土曜日は、年に1回の「オープンスクール」があった。これは日本で言う「親子行事」みたいなものだと感じた。教室によって色々な体験コーナーを設けて自由に体験できるものだ。校庭では親子フットボールも盛り上がっていた。
9月中旬にインターナショナルウィークというヨーロッパの各地から先生たちが来て、それぞれワークショップを行う機会がありました。私もそこで日本文化のクラスをもたせていただき、様々な活動をまるまる2日間行いました。やってみて学ぶことがたくさんありました。
先生たちが様々なアイディアをもっているので、それと自分ができることを組み合わせながらやっていくのは楽しいです。
なので、夏休み中に9月から授業で使う教材を準備したり、ヨーロッパ国内の旅行をしたりして過ごしています。時間がたくさんあるので、じっくり考えながら生活できます。メンターの先生は一人で夏休みを過ごしている私を気にかけ、家に呼んでサウナに入らせてくれたり、ごはんを作ってくれたり、、、本当にお世話になっています。料理が好きなので、日本食を作ってお礼をしましたが、喜んでいただきました。
今回の研修を通して日本とフィンランドの教育の相違点と共通点、働き方や文化など本を読んでいるだけではわからないたくさんのことを経験し、学ぶことができました。また、研修先の学校の先生や子どもたち、ホームステイを受け入れてくださった皆さんに本当によくして頂き、毎日とても楽しく生活することができました。今後は今回の経験を多くの方と共有し、意見をもらうことで自分の中でさらに学びを深められたらなと思います。
この4ヶ月で得たものは大きく、この場に全てを書くことは出来そうにないので特に大きかったと感じた2つについてご紹介いたします。
また2つ目は本当に学校のスタッフの一員として扱ってもらった事です。私も実際に3ヶ月間受けもたせてもらった"Japanese Club"では本当に教員のように全てを任せてもらい、自分で考えて自分で工夫し、時には分からない事や悩んだ事を他の先生や校長先生に相談した際には待ってましたと言わんばかりにたくさんのディスカッションにアドバイスをいただきました。
最後の1ヶ月は通常の授業だけでなくフィンランド特有のプロジェクトなどを見せてもらいながら、これまで以上に充実した月にしようと思います!
まだまだやりたいことが頭の中に浮かんでいるので、どれだけ紹介できるか楽しみです。8時から始まり、14時には先生たちも帰るので、放課後も自分の時間が過ごせ、その中で授業案を考えることができます。自分のパソコンを持ってきてよかったです。
日本の学校の改善点、良いとところも自分なりに感じれました。教育そのものの違いますが、先生たちの働く姿勢が全然違っていて、いい具合に凝り固まった考えが解されたように思います。4月から仕事に復帰し、今の私は、仕事への向き合いかたが変わりつつあります。
日本文化クラブでは書道と折り紙をメインにやっていますが、児童生徒から日本の生活を知りたいというリクエストを受けたため、前回それについてのレクチャーを行いました。ただ説明するだけでは面白くないので、クイズを混ぜたり、実際に日本にいる友人に動画や写真を撮って送ってもらったものを使用してリアリティを出したり、少しの工夫をしてみました。すると、日本のリアルな生活を感じることができたようで、児童生徒たちにはとても満足してもらえました。
一番貴重な経験だったのは、アシスタントして様々な授業を見学させてもらえたことです。英語の授業では、7・8歳がどんなふうに英語の授業を受けているのか、どんなことをテーマにして授業を進めているのか、先生方がどんなことに気をつけて授業をされているのか、を勉強することが出来ました。
授業以外のことで気付いたことは、「趣味の重要さ」です。日本で現役で働いているときは19時に帰宅するのは当たり前でしたが、研修期間中は遅くても17時には学校を出ていました。帰宅してからの時間が研修前より長くなり、その時間の使い方が分からずはじめは戸惑ってしまうほどでした。
そして最後に、心が折れそうになったときもホームシックになっていたときも、その気持を忘れさせてくれたのは研修校の子供たちでした。子供達と遊んでいれば悲しい気持も忘れられたし、話していれば楽しい気持ちになることが出来ました。最終日にはサプライズパーティーも準備してくれ、手紙ももらい、最後まで先生方や子供達に支えてもらった感謝の気持でいっぱいの研修期間でした。
イースター休暇に入る前は学校の子どもたちと一緒に折り紙でうさぎを作りました。うさぎの折り紙は何種類かあると思うのですが簡単なものが多くて、子どもたちも楽しそうに作っていました。以前に折り紙をした時はクリスマスバケーションに合わせてサンタクロースをみんなで作りました。季節や行事に合わせて折り紙の題材を決めていくと、何にも関係のないものを作るより、子どもたちも楽しそうに作ってる印象を受けます。残りの実習期間も2ヶ月となったので残された日々を大切に過ごしていきたいです。
低学年のクラスが異文化理解の授業をするので、私も何クラスかを回って数時間ずつ日本の学校のことや、折り紙のレッスンをしました。私のいる地域では、他にもメキシコ人の先生やイタリア人の先生を呼んで異文化理解の授業をしています。また、高学年のクラスはフィンランドに来ている留学生(大学生)を呼んで、自国のことを紹介してもらう時間を作ったり難民センターの人の話を聞いたりと他機関を頻繁に活用すること、柔軟な授業の組み方に日本との違いを強く感じました。
①YouTubeのPPAPを流す。(子供達も知っていて、一緒に歌っていました。動画が終わったら「この人どこ出身かしってる?」という質問をし、子供達から「Japan」という単語を引出しました。
②自分の名前
③概要(都道府県、国旗の色など)
④東京
⑤自分の出身地(観光地を紹介しました)
⑥季節の写真(四季がはっきりしているということを強調しました)
⑦日本の位置(飛行時間)
⑧時差
⑨人口(フィンランドより多いか少ないか。数がだいぶ大きくなりますが、どれくらい違うか示すために国、首都、自分の出身都市と学校のある市のそれぞれの人口を表にしました。
⑩寿司(あちこちに寿司のお店はあるので、みんな知っていました。)
⑪日本の食べ物(うなぎのかばやき、みそ、たこやき、ラーメン)
⑫ポケモン・任天堂(マリオやポケモンはよく知ってくれていました。)
⑬他のキャラクター
⑭アニメ
⑮Kawaiiファッション(Kawaiiという言葉やHarajukuという単語を知っているようだったので)
⑯コスプレ
⑰日本の学校制度について(制服、時間割、体育祭など)
⑱給食の配膳、清掃時間(YouTubeの動画を見せました。)
低学年ということもあり、45分~50分どれだけ興味を引き続けられるかということを中心に授業を計画しました。写真を中心にして、あちこちで質問したりクイズを出したりして進めて行きました。
最後の動画では、給食当番の配膳の様子を見てなんでマスクするの?」と聞いてくれる子がいたり、お箸箱を見て「いいね。」と先生が言っていたり、自分の教室で給食を食べるということも驚きだったようです。
最後にポッキーを配りましたが、「美味しい」と言ってくれる子も多く、思っていたよりも興味を示して積極的に話を聞いてくれたので、こちらもとっても嬉しい時間となりました。
学年が上がればトピックも変えなくてはいけなくてはいけないかなと思いました。今回は「家に帰って家族に話せるような話題」「子供達が知ってるであろう日本の知識と絡められるもの」にしたことが、よかったなと思います。
研修期間はのこり2週間なので、最後まできっちり頑張りたいと思います。
先週は校長先生の紹介で隣町の小学校に訪問してきました。そこでは日本の人口や面積、食文化やスポーツ、さらに日本の学校などをプレゼンしてきました。クイズ形式で紹介したことで授業も大盛り上がりでとても楽しい時間を過ごすことができました。
たくさんプレゼンをこなしていく中で自分の中でももっとこうしたらわかりやすいんじゃないかと試行錯誤を繰り返しています。今回の研修を通してフィンランドの教育だけでなく、自身の授業の仕方についても考えることができています。
学校に行き始めてから2週間程度経ちましたがこの2週間は学校に慣れるため他の先生の授業補助をして回っていました。英語が中心ですが、教科に捉われずに体育や家庭科、技術に音楽と様々な授業のお手伝いをさせてもらっています。
その後1週間ラップランド旅行を挟んだ後、日常生活に戻りました。週4日、計6時間クラブを行っています。今月は「忍者」と「相撲」をテーマに。低学年グループには、講義とビデオを見せた後に手裏剣を使ったチーム対抗ゲームを。高学年グループは、手裏剣を自分たちで作り、それを使ってゲームを行いました。高学年の子どもたちはとても手先が器用なので、短い時間でたくさんの手裏剣を作りました。
今までも私が今いる市では電子教材が多く取り入れられていましたが、今年に入ってからは、学習アプリの活用についての教員向けの研修も多く開かれ、ますます授業にICT機器が多く使われるようになりました。もちろんそれらの導入には費用もかかりますが、子どもたちのモチベーションの向上や教員の負担軽減など多くのメリットがあります。将来的に日本の学校現場にも多く活用されてくることが予想されるので、ICT教育先進国であるフィンランドの取り組みを身近で学ばせていただけることにとても感謝しております。
また、11月から行なっていた教会と一緒に企画したJapaneseクラブは、1月いっぱいで終了しました。私自身も毎回楽しい時間を過ごすことができ、終わってしまったのは悲しいですが、貴重な機会をいただいたことに感謝します。
10ヶ月過ごして見て、他の先生の授業や子どもたちとの関わり方、これを自分の学校でもやって見たいな、真似したいなと思うことがどんどん増えました。残り、こちらで過ごすのも1ヶ月半なので1日1日を大切にしたいと思います。
そこで改めて気付いたのは、「キャリアの差に関係なく、授業者が観察者に対して同等に扱ってくれる」ということです。
研修校はかなり大きな学校で、学年によっては教室がかなり離れていることや担任の先生だけでなく第二言語専門の先生、アシスタント、特別支援教育専門の先生もおられ、しばらく経った後初めて会った時に「あなたのことあんまりみたことないんだけど...」という会話も行われるほどです。
相手の経験等で判断することなく、学びたいという意欲に100%の姿勢で答えてくださると、自分の授業観察をする姿勢もよりいっそう高まりますし、「邪魔かな」とちょっとでも考えていた自分が恥ずかしくなります。「学びたい」と姿勢を見せる人に対して、自分 もできる限りの事で応えること、これはこれからの教師人生においてもとても大切な事だと考えされられました。
来たばかりの頃は毎日の生活に精一杯でしたが、少しずつ研修校先生方や子供達のおかげで、上記のようなことにも気付けるようになりました。今まで自分が日本で経験してきたこととこちらで感じたり思ったりしたことを学びにかえ、改めて残り少ない期間の過ごし方を考えて行きたいと思います。
研修校は義務教育の9学年が在籍していますが、高校生の様子を見学出来る機会はなかったので、大変貴重な機会でした。
英語の授業にも文学や文法の授業があり、文学の授業では「グレート・ギャツビー」の原作を読み映画を鑑賞し、自分で成果物をまとめるという内容でした。
成果物のまとめ方もいくつか選択肢が与えられており、自分の得意な方法で最終的な課題を提出出来るようでした。
私の簡単な自己紹介やフィンランドに来た目的などを話し、生徒にも「今なにしてるの?」と聞くと、とてもフレンドリーに説明をしてくれ、逆に私にも質問をしてくれるなど、参加しやすい居心地の良い時間でした。
クリスマスはホームパーティーに呼んで頂き、伝統的な家庭料理をごちそうになりました。ひとつひとつ料理の名前と食べ方を説明してくださいました。サンタも登場し、子供たちに渡されるプレゼントの量に驚愕しました。
お正月は日本の方が賑やかなイメージでした。なので1日や2日から働き始める人も街にはいたので、クリスマスがどれだけ大きなイベントか分かった冬休みでした。
こちらのでクリスマスは家族とゆっくりと過ごす、穏やかな時間でした。私の滞在するホームステイ先でも、離れて暮らす家族が集まってきて、食事をしたりおしゃべりしたり、運動したりいつもは静かな家がとても賑やかでした。
残りわずかな研修期間で、帰国したくないという寂しさも時より押し寄せますが、素敵な家族と過ごせること本当に嬉しく思います。
また、はじめてクリスマスを異国で過ごし、同じ「クリスマス」というイベントでも日本との違いを強く感じました。こちらのクリスマスは日本でいう正月と似ていて、家族でゆっくりと過ごすことが多いようです。お店や公共交通機関も24日の午後から26日の朝までは閉まっていることも驚きでした。
習字の授業を美術の授業で行いました。習字をしたことのないもしくは習字が何なのか知らない子供達に、一から説明しなければいけないことで、持ち方やはね、とめ、はらい、など字をきれいに墨を使って筆で書く」ということについて自分も考えさせられた機会でした。文字は「花」を選び、呼び方や意味を話しただけでも「へえ~」と言ってくれました。思っていたよりもスムーズに書いてくれたので、片付けも時間内に終わり、先生も楽しんでくださいました。
最近は、子供たちが育った環境や過ごした場所がどんな風に人に影響するのかということについて考えます。
日本で丁寧に細かく指導する部分をこちらでは子供の判断や想像に任せたり、逆に日本で細かく指導されているからこそ日本で出来るようになることもあり、それぞれ教育の違いがそれぞれの良い部分につながっているんだなあと思います。
そして放課後のアフタヌーンクラブという日本の小学校にあるような児童会にも参加しています。そこで折り紙がとてもウケました。
はじめは、ひとりの子が折り紙の遊び道具を持っていて、「あれ作れる?」というところから始まりました。それを作ってあげると、他の子も興味を持ちだし、「新しいのが作りたい」と言ってくれる子が増え始め、毎日のように新しい折り紙の折り方を家で調べて学校へいく日々でした。作った2種類のものを糊で貼って新しい作品を作ったり、持って帰って飾っているといてくれる子もいました。何枚かを組み合わせて立体を作ってあげると、目を輝かせて喜んでくれました。
まだまだ自分の動き方が分からず戸惑うこともありますが、一日一日を大切に過ごしていきたいです。
11月に入り、月末に一気に冷え込んで積もった雪も解け、『魔の11月』が始まった。暗くて陰鬱な、一年で最も鬱が増える季節だと言われる。確かに、一日中暗く気持ちが沈むのがよく分かる。私も気候とホルモンの関係で、何も手につかないやる気の起きない日々があった。北欧デザインが日本でも近年人気であるが、あの白木の家具や、ビビッドな色・柄のテキスタイルなどは、この陰鬱な日々を少しでも快適に過ごすための知恵なのだと思える。
また、ここでは誕生日を迎えた場合、「誕生日おめでとう!」とケーキが出てくるのではなく、「誕生日です!」と当事者がケーキを振る舞う。うちの学校だけかと思っていたら、この国の習慣なのだそうで、おかげさまで無事にまた一つ年を重ねられましたよという周りへの感謝の表れなのかもしれない。最初は衝撃であったが、郷に入ってはということで、私も今月の誕生日にはベイクドチーズケーキとレアチーズケーキを作って行った。自分の誕生日にケーキを焼いたのは初めてだったが、いい経験だった。人間関係の希薄なこの国にあって、これは職場の環境作りに一役買っていると言えるのかもしれない。
先月ら引き続き、一年生対象のtiimijakso(チームビルディング)に見学に行かせていただいている。ただし、こればかりが一日中続くので、生徒も飽きてしまい、集中力が続かない。参加する生徒、しない生徒にも分かれてくるし、舵取りの仕方は難しい。気になるのは、やはり担当の先生方の疲労度合いである。3学期は教科指導はなくこれだけ、しかも一日中、しかも初の取組、となると疲れるのも仕方ない。一年を通して割り振る、週のうちもしくは一日のうち一時間とか数時間とか、バランスを考えた方がいいのではというのが個人的な感想である。今月28日に3学期が終了したが、それとともにtiimijaksoも終了した。29日から4学期が始まっているが、やっと普通の授業に戻れるという声が聞かれるのは、やはりそれだけしんどかったということでもあると思う。この取組に関しては、趣旨に関しては賛成するけれど負担が大きいという意味で反対されている方も多い。日本の総合的な学習の時間を、負担が少ないと教科科目に読み替えてしまうのと考え方は似ている気がする。以前近隣の学校でもこれに取り組まれたが、負担の大きさからその一度きりで終わってしまった経緯があるそうだ。今後この学校がどうされるかは分からないが、今回を失敗と結論付けて終わってしまっては残念である。それに実際チームビルディングはフィンランドの生徒に必要であると自信を持って言える。「自主自立」を小さいころから叩き込まれるこの国の子どもは、自分自身の責任はとれるが、組織で動くということは本当に苦手のようである。決して眠ることなく授業にはきちんと向かえる生徒が、こういったチームでの取組になったとたん、床に寝そべり、頭上には紙飛行機が飛び交い、外部講師が話すも、携帯から目を離さず、私語ばかり...と、参加姿勢としては最低なのではと思えるもので、あまりの変貌ぶりに驚きが隠せなかった(本校は市内でもトップレベルの学校である)。日本であれば体育の先生の怒号が飛んでくるところであるが、フィンランドの先生は嫌な顔はするが、叱り飛ばすということは絶対にしない。それも国民性なのかもしれないが、これは講師に対する礼儀や話をきくマナーという意味でも、世界的なスタンダードという点でも、しっかり指導するべきところなのではないかという風にも感じる(そう思うのは日本人的考え方なのかもしれませんが)。
そして、こういった協働作業の機会が少ない問題点は、協調性が育たないのもさることながら、リーダーシップが育たないことが大きな問題であると思う。チームによって、何人かはきちんと活動をする生徒はいるが、チーム全体を仕切る、まとめる、という生徒の存在は皆無である。やる人はやる、やらない人はやらない、そしてやらない人を誰も注意しない、と、ここでも個人に任されている感があり、チームビルディングであってチームビルディングでないというのが正直な感想である。そこには、チームのメンバーや講師など、相手に対する敬意というものが全く感じられなった。こういった状態を自分たちが問題視していないというのが一番の問題ではないかと思うし、この子達にこの科目が必要だと思われた先生方の意見は正しいと思う。
フィンランドの学校教育は世界的に有名ではあるが、大学教育に関しては耳にしないように思う。ここの大学院におられる日本人研究者によれば、学者は他国での学会に行ったところで、横のつながりを作らずに帰ってくる、とため息をついておられた。また、どこかの国とのプロジェクトでも、その国出身者がいるのにその人物に声をかけず、アドバイスも受けず、そこにある人脈の使わず、ということが多々あるらしい。本当にプロジェクトなどの活動や人脈作りなどが不得意、というよりやり方を知らないという方が正しいようだ。現状では、協調性やリーダーシップを育もうにも学校の教育活動にその機会がないため、形を変えてでも、こういった活動は継続した方がよいと思う。ただし、講師側のコーディネートの仕方にも問題を感じた。数人での活動は成り立っても、1チームの人数が多くなればなるほど統率しづらくなり、蚊帳の外の人間が出てきてしまうのは当然だ。与える側の力量が問われることを痛感する。まずはマテリアルの充実や、方法の見直し、講師の育成が急務である。
一年に一度の、救命救急講習があった。座学に一時間、実技に一時間である。私は最初の一時間の時間帯には授業があったため、実技から参加。人工呼吸や心臓マッサージ、AEDの使い方など、やることはほぼ日本と同じであった。ただし、日本のように「大丈夫ですか!」「誰か救急車お願いします!」「意識なし!」「気道確保!」など指差し確認、声出し確認はなかったが、これは絶対にあった方がいいと思った。心臓マッサージでは、なんとBee GeesのStayin' aliveがかかり、この速さで心臓マッサージをするようにと指示があり、びっくりした。実際に人形を使ってやっていると、少しスピードが速いと言われ、救命士さんに、真横で"Stayin' alive"を歌われた。今後心臓マッサージをするときには、私の頭には永遠にこの歌が流れると思う。
Now, I satisfied with everything in Finland life. The most important reason is that I can challenge everything I want to do.
In this month, I challenge to do sport festival in Finland school. I have prepared for this event for two months with my friends and teacher. I had a great time with everyone.
フィンランドでは、特別支援学校中等部や通常の学級の支援級卒業後は、特別支援学校高等部ではなく、主にこうした専門学校(職業訓練校)への進学となるようです。調理、メディア、木材加工、コンピューターなど様々な専門領域のクラスに加えて、その専門を決めるためのクラス(VALMA)、将来の就労や自立した生活の準備のためのクラス(TELMA)があります。
半月ずつ入らせていただいた2つのTELMAクラスでは、それぞれ生徒が必要とする支援やその度合いが異なっていましたが、どちらのクラスでもクラス担任の他に多くのアシスタントの先生(教員ではない)がついていて(そのうちの一つのクラスでは、マンツーマン)、生徒たち一人ひとりがとても手厚い教育・支援が受けれているように思いました。そして、どちらのクラスも先生とアシスタントの先生との間での情報共有・意見交換が活発に行われていて、チームの連携を強く感じました。
専門学校なので、日本の特別支援の生徒の一般的な進学先である高等部(普通科)との簡単な比較はできませんが、より就労への実践的な経験を積む時間や、個々、少人数での活動が多かったです。障害者の就労についてはどちらの国でもまだ厳しい現状がありますが、学校を卒業した後の特別支援の生徒の将来について考える、よい機会となりました。
幼稚園、新設の小学校、2学年が合同で勉強する比較的小規模な小学校、英語を主言語とする小学校(こちらも2学年合同)、英語を主言語とする幼稚園、専門学校(高校生)、この辺の地域で最も大きな小学校等をそれぞれ1週間ずつ回りました。同じ学年、地域、人数でも学校間の数多くの違いを見ること、経験することができました。
本研修校の先生方が、「どんな学校を見たいか」と私自身の意見を聞きいれてくださり、1つ1つアポイントを取ってくれました。自分は何がしたいのか、どの学年と活動をしたいのか、常に自分の要望を持っておくことが大事です。受け身でいると何も起こりませんが、ダメ元でも自分の希望を伝えてみるのがいいと思います。
フィンランドでは100回目の独立記念日やクリスマスなど、それぞれの学校がそれぞれのテーマを持って、プロジェクトを進めています。日本人の私らしく、そのお祝いに参加できるように計画を練っているところです。
折り紙の授業のリクエストが多くて、折り紙が手に入らない時は色付きのコピー用紙を代用して使っていますが、日本の折り紙のようにあんなに折り易くて薄い紙はお店でも注文するしかないし、やっぱりどこか違うし、もっと日本から持って来ればよかったなと思います。
2学期の取り組みで特筆すべきは、"tiimijakuso"("tiimi"つまりチームで学習する"jakso"学期)であり、これは従来の「個人主義、自己責任、自主自立」から、「協調性」にフォーカスした全く新しい取り組みである。
来週の美術の時間に授業をさせてもらうことになり、今のところは習字を予定しています。
今現在の悩みどころは、学校内での子たちの振る舞いに対する意識が日本と違うところです。業態度や時間に対する意識など、こちらではかなり自由な印象を受けます。しかしその「自由さ」が良い面で現れているのが、授業中の発言に関してです。
質問でも意見でも、自分の体験談でも子供たちは「発言したい」と思ったらすぐに挙手し、当てられたら発言します。先生の話の筋と違う内容の発言をしたとしても、「じゃあそのことについて話してみよう」と言って他の生徒からも共感する意見や体験談を聞く時間になったりするのです。
肝心の活動ですが、折り紙と歌を紹介してきました。基本自分から「これやりたいんだけどやらせてくれない」といった積極的な発言などはまだせず、「次の時間なんかやりたいことある?」みたいなことを先生たちから尋ねられて「あ、時間もらえるんならこれやりますね。」みたいな感じです。これだけ聞くとやる気がまったくないやつみたいに思うかもしれませんが自分は決してやる気がないというわけではありません。
そもそもの僕の目的がフィンランドの教育が見たいというものなので日本の文化の紹介というものに意識が向いてこないだけなのです。しかし、世の中はgive&takeであります。フィンランドの教育を見せてもらった分、こちらとしてもそれ相応のお返しをしようと思っています。アイデアはあるのですが、それをするためにはどうしてもフィンランド語を覚えてからにしたいのでもう少し後のほうで。
あ、そうだ。日本の歌紹介では「こぶた・たぬき・きつね・ねこ」の歌を紹介したんですけどめちゃくちゃ反応よかったです。先生からもかなり褒められました。ちなみにこの歌は前に僕の先輩が授業でやったよということを言ってたのを思い出して使わせていただきました。先輩ありがとうございます。
ぜひ、活動中の皆さんもこれから活動する皆さんも「なんかやって」と当日無茶振りされた時には使ってください。
英語の授業から始まり、1週間ずつ各学年を見学させてもらっています。現在2年生の子どもたちと一緒に生活をしています。フィンランド北部、ラップランドについて学習。教科書の写真と文字を眺めた後は先生が読むラップランドの物語を聴きながら、頭に浮かんだ映像を画伯のように絵におこしていきます。BGMはサーミの民族音楽で、大きな地図で場所もしっかり確認。たった45分の中で、ラップランド小旅行を体験することができました。先生のお家で取れた林檎を頬張りながら勉強したり、自然の中にあるものを使って音楽を奏でたり、音楽が聴こえてくれば踊り、まるっと1時間雪遊びをしたり。毎日、ゆるっと、なめらかに時間が過ぎていく感覚です。
NZの小学校や中学校は15時で学校が終わり、先生方もそれと同時に帰る先生もいたり、遅くても17時には学校を出ていたりと、「日本に比べると帰るのとっても早いな~」と驚いていましたが、フィンランドはもっと早い!13時、遅くても15時に先生方は帰って行きます。子どもにとっても、先生方にとっても、授業の中や放課後に余白がたっぷり。遊ぶことのできる休み時間はランチの時間を含め合計、NZでは1時間半、フィンランドでは1時間15~30分あります。日本にいた時、私の学校では30分でした。子どもたちは落ち着いた環境の中で学校生活を送っています。息を吸うのと同じような感覚で、自然に教室に馴染み学んでいる姿が印象的です。
放課後や休日には、教会で開かれるミサや音楽会に頻繁に足を運んでいます。音楽学校を紹介していただき見学している中で、ピアノの教え方や、音楽の学問を学んでいます。趣味のピアノ、英語やヨガ、現地の日本語教室、大きな街への観光、友達とのハイキングなど、自分の勉強、趣味、興味関心が満たされていて、今の生活がお気に入りです。
放課後は、ヨガに通ったり、子どもたちが帰った後の教室でピアノの練習、英語のレッスンの受講、買い物、友達とチャットや電話をしたり、とても充実しています、休日はバスを使って隣町に出かけ、図書館で勉強したり観光なども楽しんでいます。フィンランドに来て1週目で周りの方々に協力していただきながら自分の1週間の生活リズムを作れたのは、とても良かったです。
授業のリズムが整って来たら、放課後にJapanese clubを立ち上げて、合唱グループや、ソーラングループを作りたいと思っています。学校がとても寛容なので、9ヶ月間、やってみたいと思ったことはチャレンジし尽くします!
教師たちはデジタル教材とSMARTという機材を使いこなし授業を展開させています。教育予算が充実しているフィンランドの教育現場を羨ましく思います。また、教科書も優れていると私には感じるのですが、教科書はあくまでも参考書であってもっと他の活動を取り入れて授業を進めるようにと打診されているそうです。
ほんの少しですが、私も日本文化紹介の時はやはりプレゼンテーションソフトを活用したり、動画を多用して授業を行いました。
各学年に一人程度の転校生が仲間入りをしたり、6年生は初めてのスウェーデン語の授業が始まったり、新しい先生が来たり、新しいことが目白押しで、学校全体がワクワクしているのを感じました。
私の研修校では、6年生と1年生がペアを作り、これから1年間6年生が様々な面でサポートしていきます。学校案内から始まり、声かけ、学校全体で集まる時には一緒に座って注意を促すこと、また冬になればスケート靴を1年生に履かせるのは6年生の役目になります。彼らはすでに十分独立していて、これまでの6年生の行動を見てきているので、初日から戸惑っている様子は見られませんでした。
私の研修については、この学期から本研修校を出て、他の研修校を回る予定でしたが様々な事情が重なり、しばらくは本校で活動することになりました。こちらでは全ての学年と活動をし終えており、そして近々大きな行事があることも重なり、日本文化紹介という時間も取れず、授業を見学、机間巡視、コピーや教科書を運ぶ雑務等をしています。少し空白のような時間で、モヤモヤする時もありますが、次の活動に向けての準備期間と考えて、アイデアを練ろうと思います。
また、今年の夏に一番好評だったのが浴衣です。見せる機会があれば...くらいに思って持って行っていたのですが、ぜひ着たいとのリクエストがあったので、みんなで着る日を決めました。とは言っても恥ずかしながら、今まで人に着付けをしたこと、ましてや自分で着たこともなかったので、急いで動画を見ながら練習しました。
その他、宗教や歴史等の科目で授業を行いました。「日本の宗教について」では、神話や妙心寺の副住職のTED KYOTOより、日本人の宗教に対する寛容性や自然崇拝という点から話を進め、塩や水での「清め」や、年中行事や暮らしの中の祭礼、神社仏閣と庭や文化、祭りとの関わりなどの紹介をしました。そこに儒教を加え、準備にかなり時間を要しましたが、何とか概要をつかんでもらうことができました。
その他、受けた質問の中に、「オタク」に対する偏見や、それに関連して「ひきこもり」や過労死の問題、また大学生による集団暴行から「日本における性教育」など、思わぬところから質問が飛んできました。答えは出ない質問とも言えるかもしれませんが、自分なりの見解は持つ必要があるとともに、他府県や他校種、公私による違いを知る必要も感じました。
後半からは、夏の間に開かれているフィンランド語の講座に参加しました。1週間のものがレベルごとに開かれていました。様々な国から様々な目的で生徒さん達が集まっていました。基本的には英語で行われますが、先生が語学堪能な方だったので、ロシア語も話されていました。ちなみに、その学校は研修地ではなかったので、近くにアパートを借りて通っていました。
フィンランド語を日本で使うだろうか...、もちろんこの研修中に使うというのが第一目的だけど...と最初は少し迷っていました。でも授業を受けている生徒さん達と話すのはもちろん英語で、授業も英語なので、英語もかなり練習できました。その一方で、英語が苦手な方も受講されていましたが、基礎は日本で勉強されていたからか、不自由なく楽しく受講されていました。とても楽しかったので、残り半年は地元のカルチャーセンターで講座を続けようと考えています。
最終日は卒業式でしたが、雰囲気は日本の大学の式に似ていました。
卒業生1人1人に証書と白い帽子を手渡す様子は日本の高校までの式と似たところも感じました。卒業生や在校生が演奏を披露したり、全員で歌を歌う場面もあったりと、感動的な式だったと思います。
の授業に参加させていただきました。
事前に「何か準備することはありますか」と聞いていたものの、特に教えてはもらえず、当日授業に行ったら、「ニューヨーク市場に上場
している日本企業についてプレゼンしてくれ」とのこと。突然のリクエストで正直焦りました。
今後への展望、東京オリンピック・パラリンピックについて、投資家向けの英語のサイトによる株価や売上高などの紹介、為替変動による売上高への影響などの話をしました。
音楽の授業で先生が日本の歌を教えたいとのことだたったので、すごく簡単ですが、チューリップの歌を1,2年生に教えました。すぐ歌詞を覚えてしまう子どもたちの力は凄いなと思います。
6月になり、夏休みも始まりホストファミリーに相談しながら休み中の計画を立てています。楽しい夏休みになりそうです。
英語とフィンランド語の勉強も集中して取り組みたいです。
色々な点で日本と制度が違うことにも勿論驚いていますが、今回のお話で最も印象に残ったのは私達が思っている以上に障がいに対してネガティブなイメージもポジティブなイメージも持っていないことでした。
作図の手順や式の展開など、パワーポイントのアニメーションを準備しておいたので、生徒も理解できたと同時に、現地の先生にもよい提案となったと思います。また、1人の生徒にテスト対策の個別指導を実施しました。
日本文化を紹介する授業を英語や地理の時間に実施しました。
先方からいただいた「日本まるごと事典」に助けられました。ありがとうございます。
授業の中で紹介した「ありがとう」「さよなら」などと声を掛けてくれる生徒もいて励みになりました。
春季タームの最後2週間は、テストウィーク、プロジェクトウィークと続きました。
テストは試験時間3時間、生徒が集中して取り組んでいました。また、ノートPCを使った試験などもあり、日本よりも進んでいる面を見ることができました。テストでも使われていた作図ソフト「Geogebra」は日本でも活用したいと思いました。
プロジェクトウィークは、フィンランドの学校は年に2回どこでも実施されている取り組みのようで、日本で言う総合学習のような時間です。タンペレ科学技術高校は職業訓練校が同じ敷地内にあるので、ハイスペックな装置を使ってのロボティクスやプログラミングの学習が印象的でした。
またテストウィークには、授業がないからと職業訓練校を見学させていただきました。
デザイン、流通、木材加工、金属加工、電気・電子、レストラン、ホテル・・・中学を卒業した学生は高校へ進学するか職業訓練校に進むかの選択ができます。職業訓練校で生徒が制作したものは、安価で買うことができます。
また、企業とのインターンシップや就職後の研修もあるので技術者が育ちます。文系学部出身のプログラマーがいる日本との違いを感じました。職業訓練校を1つの企業とする考え方もあります。人口わずか500万のフィンランドが、世界でも最先端をいく源が理解できた気がします。
今週末がいよいよ卒業パーティーとなりますが、できることならここにもっと長く住んでいたいと思える場所です。
本当に良い経験をさせていただいています。ありがとうございます。
最初の1ヵ月は慣れる事に必死で、出来るだけ多くの授業に出て見学し、質問をしていました。2ヵ月目に入る頃には何となくわかってきた気がした英語。先々週くらいから今までより意思疎通が難しくなったように感じました。英語の市民向け講座に出たり、家でも英語のディクテーションなど積極的にしていたはずなのになぜなのか、考えた末に思ったことは、話す内容が今までより込み入ったことになってきたからだとわかりました。「今何してるの?」から「なんてアドバイスしたの?」に、「何を描いているの?」という質問に答えてくれる生徒もただ描いている対象を単語で答えることから「なぜこの対象にしたのか、何を伝えたいのか」など話してくれるようになってきました。(先生がそう促してくれています) それらに対して、語学力がついていかず、もどかしい気持ちの2ヵ月目でした。
授業は折り紙の授業を3コマ開催しました。
こちらもまた、何を作ろうか、何を教えようか悩みました。授業はindustrial art(工業デザイン、空間デザイン)だったので、ただ折り紙を作って教えるだけでなく、何か授業に結びつけて考えたいと思っていました。0D(点),1D(線),2D(面),3D(立体)を、折り紙を通しても感じてほしい。悩んでいた時、先生から「issey miyake」を知ってるかと聞かれました。三宅一生は世界的なファッションデザイナーで、作品に折り紙や紙のプリーツを活用しています。伝統的な芸術というだけでなく、最新のファッションにも組み込まれているということを伝えることで、少しは生徒の興味を引くことが出来たのではないかと思います。ちなみにボツ案は「ミウラ折」で、宇宙開発に繋がっていることを組み込むこととミウラ折体験でした。折り紙をしよう!だけで盛り上がれる年齢でもない高校生は、興味を引くのがとても難しいと思いました。
今月は書道の授業を3コマと、秋学期に向けた授業に関する会議がありまし。また、英語の講座も週3日に増えました。頑張りどきだと思うので、体調に気を付けて、環境を生かしてしっかり成長したいです。
フィンランドの学校教育、外国語としての英語教育、日本語教育、の視察・体験がメインのつもりで来ましたが、その他にも改めて気づかされることももちろん多く、例えば親の仕事の関係等で日本の公立学校へ入れられた外国人児童生徒への支援(学校生活、日本語指導)という問題や、実際に難民の方に出会った中で気づいた難民問題、日本の国防、安全の問題などがそれに当たります。
先日、3年生のクラスで折り紙でのモンスターボールの折り方を教えたのですが、ひとつ折り進めるたびに想像以上に子どもたちがとても興奮して喜んでいて、私自身もとても楽しんで教えることができました。
学校での授業は、自己紹介と折り紙と習字をやらせていただきましたが、自分で英語、フィンランド語をもう少し勉強した方がいいと感じたため、今は他の先生の授業に入らせてもらったり、フィンランド語の勉強をさせてもらっています。もう少し慣れてきたら、他の授業をしてみようということになりました。
教えたことのない高校数学、フィンランド語、英語を勉強する日々です。
先週、先生方が出張だったので、出席を取って、youtubeを見せて演習させる、を1人で行いました。
ICT機器も最新鋭といったところで、使い方を教わりました。
毎日の昼食券、デスク、校務支援PCアドレスの権限をいただくなど良い待遇をいただいているので、恩返しできるよう頑張ります。
美術科の先生は3人で、1人あたり1週間に4コマ、各コマ3講義で1単位なので計12講義をこなしています。同じ内容の授業を同じ先生もしくは違う先生が持っている場合もあるので今期(第4学期)は全部で8コマ×3講義の開講で24講義、毎週順番に見れるだけ沢山の授業を見学しました。
どのコマも予想以上に内容が先進的、専門的で、少人数制ということもあって非常に丁寧な指導がされていました。最初の1・2週間は見学しているだけで「あの人は誰?」という目線を痛い程感じましたが、逆によく目に入るよう長い時間学校にいることで慣れてもらいました。
先進的、専門的な授業が進む中、1年間しかいない自分が、日本に興味のない生徒にも何かを得てもらうために何が出来るのか、絶賛考え中です。日本の言語はひらがな、カタカナ、漢字と種類が多い上、とても繊細な描写ができます。また、日本の伝統色も言語同様に様々な由来を持つものが多くあります。生徒達の色彩感覚、感度の幅を広げられるような授業を作りたいと思った1ヵ月でした。
そのため、この数週間あまり学校にはいけませんでしたが、その分良くも悪くもフィンランドの医療システムについて少し詳しくなりました。フィンランドでは、公立の病院も私立の病院もどちらも事前予約が必要です(救急搬送されたときは公立の病院に運ばれますが、このときだけは予約はいらないみたいでした笑)。フィンランドの社会保険が受けれる人は安い公立病院に行く人ももちろん多いみたいですが、予約してからの期間を含め、長く待たなければならないことがほとんどのため、高価であるが待ち時間のほとんどいらない私立の病院を選ぶ人もまた多いそうです。
最後の最後に新しい出会いなどもあり、それもまたよかったです。
先生達とのパーティーは幹事の先生達のアイディアで、皆で日本に旅行に行こうという設定でパーティーを考えました。チケットや、手荷物検査などを行い、飛行機に見立てた教室に入って飲み物などを振る舞い、扉を開けると浴衣を着た私が出迎え皆で寿司作りをし、日本食を食べるというものでした。私は料理担当だったため二十人近い人数の料理を作ったり、寿司の準備をするのは一苦労でしたが、皆さん喜んでくれてよかったです。
生活面でお世話になった人達とのパーティーでは餃子を作り、ふるまいました。皮は売っていないので、料理の得意なホストファミリーのおかげで一緒に作ることができました。年いるといいことも嫌なことも色々体験しますが、お世話になった気持ちを伝えられる機会をもつことができてよかったです。
学校では、最初に2・3週間ずつそれぞれのクラスの先生の授業を見学することになっています。
見学とはいっても、見ているだけではなく、メモを取ったり、机間巡視・机間指導をしたり、アシスタント的な役割で活動したりします。
それぞれの期間で先生と相談をして、授業との進度の兼ね合いで可能であれば、私が担当する時間を設けてもらえるとのことです。
最初に担当してもらった英語の先生からは、英語の授業のアクティビティを何回か任せてもらい、生徒から「日本のゲームがしたい」とリクエストがあったので、その場で急遽1時間を任せてもらい、日本の手遊びやゲームなど道具なしでできるものをやりました。
今担当してもらっている先生からは、何回か私に授業を任せてもらったので、今週末に向けて準備を進めているところです。
日常生活でも、ホストファミリーのおかげで様々な体験をさせてもらっています。普段の料理に加えて、日本料理(とはいってもオムライス)をホストマザーと一緒に作ったりもしました。
さて今月は、現地の方向けの日本語講座にお邪魔しました。講師はフィンランド在住の日本人。久々の日本語。外国人の視点から見ると面白い言語ですね。そして、この講座で出会った方から小さなコンサートに招待され、「カンテレ」という民族楽器の演奏を聞く機会に繋がり、日本人講師の方からは近くに住む留学中の日本人を紹介していただき...というように、面白いほど出会いが広がるフィンランド。ひとつだけの行動でも、そのひとつの行動がすべてを変えます、予想外の何かに繋がります。海外だから、より強く実感するだけなのかもしれません。でも日本でだって同じです。とりあえず、余裕のある時に、何か一つだけ、行動してみることをおすすめします。きっと素敵な出会いが待っているはず!
校長先生も何でもやっていい、困ったら何でも言いなさいと言ってくれ、「こうあるべきだ」「すべきではない」等の縛りがない中での活動は、どうしたら喜んでくれるか・楽しんでくれるかと考えたり行動したりするという目的は同じでも、日本とはまた違う雰囲気があります。
まもなく一年が経とうとしているのに全然英語力が向上していないのではないか、と落ち込んでいましたが、自分がフィンランドでやりたかったことを改めて思い返すと、教育現場をみる、とか、フィンランドの自然にふれる、文化に触れる、など目的はほぼ全て達成していたのでほっとしました。語力はいろいろな方法で、向上させたいです。
①やりたいといえばなんでもやらせてもらえる。
これはお国柄かもしれませんが、フィンランドはコネクションが非常に重要な国です。でも、やりたい、といえば基本的になんでもやらせてもらえます。私は授業で生徒が学習したことを発表する場がほしかったので、たまたま知り合った現地在住日本人の図書館司書の方に相談して、市の図書館で日本の短歌と俳句を生徒が紹介する、というイベントを行いました。
イベントというより「発表会」という感じでしたが、それでも集まってくれた方々も多く、日本の文化に興味を持ってもらえたことがうれしかったです。生徒もやりがいを感じていました。
②現地の日本人留学生と交流してみる。
たまたま同じアパートに9月から3か月間の短期留学でこちらに来ている日本人の大学生が住んでいました。彼らも大学の勉強だけでなく、時間があればいろいろな経験をしてみたいということだったので、私の日本語の授業のアシスタントを時々やってもらいました。生徒の会話練習のペアが増えたりして助かりましたし、学生のみなさんもよい経験になったのでは、と思います。
また、アシスタントを頼むにあたって在籍校に相談したときも、「いいね!」という感じだったので、①でも書いた通り、やりたいといえば大体何でもやらせてもらえます。
③ビデオを撮って共有してみる。
こちらに来て初めて知ったのが、スマホの動画編集アプリは素晴らしい、ということです。スマホで撮ったビデオをスマホで編集してYOUTUBE上にアップロードすることができます。また、アドレスを知っている人だけに公開をする、などのプライバシーもある程度確保できます。なので、現地校の様子を日本の学校に知らせたり、生徒の活動をまとめたりするときに活用してきました。
生徒が日本語で自己紹介している動画を日本の学校に送り、交流をしたりもしました。
④現地の言葉はある程度話せた方がいい。
私はホームステイをしているわけではないので、日本で勤務していた頃と比べると圧倒的に自由な時間が多いです。7月から12月の間は、コミュニティカレッジに通ったりしてフィンランド語の勉強をしてきました。今が一番フィンランド語ができるのでは?と思い、1月末にあったYleiset Kielitutukinnotというテストも受けました。受験料が1万円以上と高いのですが、中級を持っているとフィンランドで仕事をしたりするときにも役にたつ場合がある、とのことで、せっかくなので受験しました。各都市によって受験日は異なりますが、1年滞在する方は一つ目標にしてみてもいいのではないかと思います。
また、編み物の教室に行ったりホットヨガのクラスに通ったり、最後の3か月は現地の人たちにまざってのんびりすごそうと思っています。そんなときにも、フィンランド語が多少できるとなじめるので、やっぱり現地の言葉はできた方がいいんだなと思いました。
後半の休暇では、フィンランドのクリスマスをホストファミリーと過ごし、教会でオペラ鑑賞、クリスマスマーケット巡りなどをしてゆっくりしました。タンペレやロヴァニエミなど、休暇を利用し旅行もできたのでとても満足。これまで、一人でどこかへ行ったらその地域のミュージアムと教会には必ず行っていましたが、皆さんにもお勧めです。同時に、帰国したらもっと日本中、名所と言われる場所も、身近な地域の見どころも、色んな場所を訪れようとも思いました。住んでいるからこそ、知らないこと、気に留めないこと、気づかなかったこと、たくさんある気がします。
クリスマスの前は準備があるからお休みになるよ、と聞いていましたが、本当に前日がお休みなだけで、今年で言うと日本と変わらない日程かと思います。そして、学校は最後までいたって平常授業でした。楽しそうではありますが、浮足立った雰囲気はなく、授業やテストにも平常通り臨む生徒の姿が見られました。小学校では催し物があるようです。
また、クリスマスにはお店等はすべて閉まる、と聞いていましたが、その通りで、前日からクリスマス用の出店も撤退し、当日は通りを歩く人もほとんどおらず、かえって少し警戒してしまうほどでした。
今月のメインは料理。研修校ともう一つの中学校で日本食をつくりました。メニューはお寿司とお好み焼き。日本人はどちらも感覚や目分量で作る料理ではないでしょうか。日頃料理をするときに使う英単語の知識のなさに愕然としつつ、インターネットで適切な分量を調べるのに苦労したのがいい思い出です。巻きずしをつくりましたが海苔の苦手な人がほとんど。けれど、巻きずしの内側に海苔があれば(気づかずに)食べられる、という人もいます。お好み焼きは大好評。日本から持参した粉末の本だしとかつお節が活躍しました。
学校以外では幼稚園・プレスクールと老人ホームへ。プレスクールでは全力で遊び、折り紙でピカチュウを折り、老人ホームでは美術選択の中2と高齢者が一緒に作品づくりをする場にお邪魔しました。フィンランドでは誰もが英語で話しかけてくれるのでコミュニケーションに不便を感じませんが、この二か所は英語が通じないのでフィンランド語を使ういい機会。そして満足な意思疎通もできないのに一番別れを惜しんでくれるのもこういった場所。毎回心が温かくなります。
日本でも生徒と高齢者の交流をはじめ地域とのつながりはありますが、こちらのほうがより積極的。小1と中3が一緒に家庭科、スウェーデン語の授業と歴史の授業が合体、など周りを巻き込んで深い学びができる機会が充実しています。しかし最近の先生方やニュースの話題は小4の算数と理科の学力低下。ITに強い国だけあり、子どもたちのスマートフォンなどが問題だという課題の面は日本と同様のようです。
4月から6月の頭までは、よくわからないことが多かったので自分の授業をしつつ他の教科の先生の授業を見学したり、他の校種の見学にいったりしていました。私が在籍している高校は、これまでもIIPを通じた日本人の研修受け入れをしていたので、担当してくださっている先生の方からいろいろ見せてくれたりもしましたし、私の方からお願いすればいくらでも授業見学させてくれました。ただ、最初はカリキュラムがよくわからなかったので、2か月くらいかけて、学校がどう動いているのか確認した感じです。6月から入った夏休みは3週間ほど旅行をしました。
7月から9月の間は、フィンランド語教科月間としました。英語でもなんとかなりますが、国語の授業の内容をきちんと理解するためには、フィンランド語が分かったほうがやっぱりいいなと思ったからです。6月までの間も独学はしていましたが、難しいものがあったので、7月にユバスキュラ大学のケサユリオピストという3週間のフィンランド語の夏期講習に出ました。最初は完全初心者コースに振り分けられていたのですが、ひとつクラスを上げてもらい、なんとかついていった結果、頑張れば日常生活をフィンランド語で送れるようになりました。8月の頭に学校が始まってからは、職場の先生にもフィンランド語で話してもらうようにお願いしました。また、9月からカンサライスオピストというコミュニティカレッジでフィンランド語の講座が始まるので、それに申し込みました。中級クラスに入るためには試験があったので、試験までは自分の授業のあとはひたすらフィンランド語の勉強をしていました。カンサライスオピストには、他にもいろいろな講座があるのでおすすめです。ただしお金はかかります。
9月後半から11月は、フィンランド語の講座に出る、高校の授業に出席する、自分の授業をする、という3つが中心的な活動になりました。夏休みあけから、高校の国語の授業に継続して出席し(生徒のように)、単元をどのように組んでいるのかを記録しています。(時には私も生徒と同じようにフィンランド語のレポートを書いたりもします。)また、フィンランド語と国語の授業の方が落ち着いたので、自分の授業を多少充実させようかと、現在UEFに留学している日本人学生にボランティアで来てもらったり、カンサライスオピストの日本語の授業をしている先生が図書館司書の方だったので、私の授業に出席している生徒と一緒に日本の俳句や短歌を紹介するイベントをすることになったりしました。
残りの期間は、新しいことに挑戦するというよりも、自分がこれまでに行ってきたことや学んだことをまとめて来年度以降の自分の活動の道を探りたいなと思っています。
例えば、open school(文化祭のようなものですが日本ほど凝っていません)の準備で、地域の歴史や学校について調べるグループ。2人一組で周囲の学校にアポなし訪問。とりあえず校長先生にこんにちは。その後は、インタビューしに来ました。あら、そうなの。どうぞ。と授業中の先生が廊下に出てきてくれたり、教室に招き入れてくれたり。
あるいは、フィンランドの学校には学校図書館やプールがありません。そこで使うのは市立図書館に、公共の体育館、スタジアム、競技場(サッカー、野球、陸上など、公式の試合にも使えるほど立派)。学校周辺に充実した施設が備わっているので、先生が付き添わずに、数人の生徒が授業中に町の施設へ行くこともしばしば。今の日本では不審者が、安全が、責任の所在が、手続きが、と難しいのではないでしょうか。どんなに小さな学校でもそれぞれの学校に一つずつ設備が備わっている日本、個々には何もないけれどその分公共の施設が豊かで地域と繋がる場にもなるフィンランド。皆さんはどちらが好きですか?
さらに小中学校の建物に歯医者さんや心理カウンセラーのいるクリニックも併設されているところにもお邪魔しました。
20人のクラスに教科の先生一人、スクールアシスタント一人、スペシャルティーチャー一人の3人体制の授業もできる。掲示物はスクールアシスタントにお任せ。スクールカウンセラーが教師と同じ立ち位置にいて、イベント事で仕切るのはカウンセラー。専門性に特化しているフィンランド。
一方、日本のように一人の教師が担任から掲示から学級通信、行事もバリバリ一緒に盛り上がることで深く生徒を理解できるのもまたその通り。
違いや気づきを挙げればきりがないので、興味がある方はぜひ一度フィンランドへ、ということが私の言いたいことで、百聞は一見に如かずです。
夏休みの間お世話になったホームステイ先の方に、先日スモークサウナのあるスパへ連れて行ってもらいました。伝統的なサウナだそうです。独特の香りのするサウナでしたが、通常のサウナ同様、温かく、また、スモークの香りでリラックスできました。いい体験でした。
活動においては、こちらの学校の先生のつてで、別の小学校に行かせてもらう機会がありました。校外の小規模校だったこともあり、街の中心部の中学校とは違う学校生活を体験することができました。小学生は気軽に話しかけてくれるので、中学校よりもなじみやすい場面もあるだろうと感じました。
私の研修校は生徒数約220人の中学校。ホストマザーがlanguage teacherとして今年は英語とスウェーデン語を担当されているので、多くの時間をホストマザーの授業で過ごしました。英語では生徒とペアになって英会話をしたり、今週が1学期最終週ということで一対一で5~10分のインタビューのようなspeakingの相手になって英語力を評価する立場を任せていただいたり。7年生(中1)のクラスではスウェーデン語を一緒に学んでいて、フィンランド語の語彙も増やせるので一石二鳥。
また、私は大学で英語と教育を学んでいることもあり、私の目的はフィンランド教育に直に触れること。そのため全科目の授業を見学、中には参加した授業もあります。付近の小学校や特別学校にも訪れました。今後はvocational scoolや高校にも伺う予定。
研修先の生徒たちはシャイで中々積極的ではない様子。火曜日にJapan Clubで日本文化の紹介をしてと言われていたのですが、誰も来ない日も。インターン開始当初は、これでは何も紹介できない、どうやって生徒を集めよう、と焦りました。でも、ふと思い出せば、私の第一の目的はフィンランド教育を知ることで、日本文化をどうしても広める必要があるわけではないし、生徒がどうしても知る必要はない。知りたい生徒が来てくれればいいし、例えば家庭科や社会の授業にお邪魔して日本料理や宗教を紹介すればいい。研修校でできないなら他の学校ですればいい。そう思ってからは随分気が楽になりました。実際に先日訪れた特別学校で丸一日かけて日本の紹介をすることも決定済。特別学校の生徒たちは日本に興味津々で、時間がたつのがあっという間。日本語や折り紙や着物や家や震災、ずーっと質問攻めでした。学校が変われば生徒や先生や校舎の雰囲気もがらりと変わるのはどの国でも同じようです。
誰もが言うことだとは思いますが、すべては自分の行動次第、正解はない。この今までの日本の生活や経験でも十分わかっていたはずのことを、海外に来るという今までとはちょっと場所とすることが変わった生活をすることで、気づく機会に恵まれました。海外だから行動する、ではなくて、常に行動し続ける人間にパワーアップする一歩として、日本を離れる経験は素晴らしいものだと思います。
半年という期間を充実させるために、改めて、やりたいことを紙に書き出し、自分の目的や目標を明確にさせました。
英語で話している内容を理解できるようになること。話せるようになること。
フィンランド語で話している内容を理解できるようになること。話せるようになること。
フィンランド内の他の土地や、他の国を訪れ、世界を広げること。
フィンランドの秋、冬を楽しむこと。
多くのフィンランド人が「暗くて寒い長い冬が来る。」と憂鬱そうに話していましたが、フィンランドの四季を楽しめるよう自然に触れたり現地の生活を体験したいと思います。
最近は放課後図書館でYouTube を使って英語の勉強をしています。携帯電話とイヤホンさえあれば、英語圏の国でなくとも、英語の勉強ができます。様々な種類の英語を聞くことができ、また分からない単語があればインターネットを使って調べることができます。図書館ではwifiが使えるので通信料なども気にせずインターネットを使えます。
秋から始まったフィンランド語講座も受講し、週に2日通っています。こちらは少しでも現地の言葉がわかるようになれば、という気持ちでいるので楽な気持ちで通っています。そこに通っている他の国の人とも交流がもてます。
フィンランドに研修に来たといえどもやはり退屈に思うこともあるので、ちょっとした休暇や土日を活用して他の町や国へ遊びに行っています。日本にいる時より、ヨーロッパ圏の他の国に行くのは格段に楽なので、多少お金がかかっても、自分の時間を活用して出かけています。
今、この研修制度でしかできないことを存分に楽しみ、残り半年、充実した生活を送りたいと思います。
入学式はなく、生徒の活動に、委員会や係はなく掃除や給食当番もない、教員も教科指導以外の生徒指導や進路指導、事務的な仕事が、他の各専門職に分業されている、など新しいことを知るたびに、生徒や教師の活動が学習に特化されているのを感じます。まだまだ、知らないことに出会える、と期待できる新学期です。
のどかな田舎町で車がないとどこにも行けませんが、遅くても15時には学校が終わるため、ホストマザーが学校帰りに買い物に連れて行ってくださいます。週末は2匹の犬とお散歩したり、TVをみながらおしゃべりしたり、のんびり過ごして、まさにフィンランドの"普通"の日常を体験中です。
テーマは日本とフィンランドの教育の違いについてです。記者の方と話す中で、改めて日本の教育の課題や良さなどがわかりました。
これまで生活してきた中で感じた大きな違いは「フィンランドは個を大切にし、日本は集団に重きを置いている」ということです。フィンランドで行われている充実した個別指導は今の日本ではできないだろうし、学校行事などで見せる団結力あってこその演技や発表はフィンランドではできないと思います。これには人口(子供や教員の数)や国の政策、教育の歴史なども関係しているので簡単に変えられることではないと思います。しかし、どちらも大切なことであると思いました。
エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、デンマーク、スペインを見て回りましたが、どこの国もキリスト教の教会がたくさんあり驚きました。むかし学習した世界史を振り返ったり、新たに学び直したりするなど、勉強になりました。
また、町並みやその国の人達を見て改めて日本の街のきれいさや礼儀正しさなどを感じました。日本を誇りに思い、今の日本のよさは変わらずにいてほしいと思いました。
夏休み入ってすぐの頃は学校の先生の紹介で、近くの幼稚園に見学へ遊びに行っていました。幼稚園といっても日本の保育園のようなところで0歳児から同じ教室で過ごしていました。子供達と一緒に遊びながら言葉の勉強もすることができます。昼食後、お昼寝の時間になるので、その頃帰り、図書館へ行ったり自分の時間を過ごしたりしていました。
最近は天気のいい日が続いていたので、散歩やサイクリングに出かけています。日本の都心に住んでいるとこんなに緑の多いところはそうないので、一日2時間以上歩くということを目標に地図を持ち行ったことのない道を歩いています。午前中、午後と歩き街の様子がわかってきました。リフレッシュと健康づくりにもつながり、充実した日を過ごしています。
生活面では、学校の先生に、週末や夏休みの計画に誘ってもらい、学校だけでなく、仕事以外の時間の過ごし方を少しずつ感じています。
夏休み中は教育機関はほとんど動いていないので、その時期にフィンランド語を学ぶのは難しいようです。(ヘルシンキではそうでもないかもしれません)しかし、日本のことを生徒に伝える機会を楽しみにしてくれている先生が、色々と声をかけてくれるので、そういったことにゆっくり時間を使おうかと考えています。
フィンランドの高校は、朝学活も帰り学活もなく、自分で時間割を組んでそれに合わせての登下校なので、日本の大学のイメージに近いです。また、先生たちも自分の授業に間に合うように来て、特にやることがなければ帰ります。私自身は、中学校でずっと勤務していたので、部活がないというのはこんなにも楽なのか!ということに感激しています。(もちろん部活を行うことのメリットもありますが)。
しかし、このようなスタイルになったのは、10数年前のことだと言っていました。それまではホームルームがあって、同じクラスの生徒は同じ時間割で授業を受けていたそうです。メリットとしては、自分の好きなように時間割が組めるので学習に対するモチベーションが上がることと、学年をこえていろいろな人と話したり協力したりできることの2点。デメリットとしては、そうは言っても結局小グループで固まってしまう点、集団としての一体感や団結力はあまりない点の2点が挙げられると言っていましたが、自ら学習に向かう姿勢を大切にすることはいいことだと思う、というのが私がお話を伺った先生の意見でした。
先生方はとても親切で、聞けばなんでも教えてくれるので、授業終了後等のあいた時間を見計らって、ネットや本で調べたことだけではわからなかったことをきいたり、実際現場で働く立場としてどのように感じているのかを聞いています。特に現場の声を聞くことはなかなかできないので、非常に興味深く、良い経験をさせてもらっていることに感謝しています。
学校では1年生のクラスに入る機会が多いです。先生の補助(コピーをとる、紙を配る、掲示物をはる等)や勉強が苦手な児童についてフォローをしています。また、他の学年の授業を参観するようにもしています。フィンランド語の授業の際は、子供と一緒になってフィンランド語を学ぶようにしています。(絶好の学習の場です。)
この1か月は、日本の教育の良さを感じることが多くありました。食育、子供ありきの授業、板書計画など。外国の教育の良さを多く見つけられるようにしたいと思っています。
1月末からは仕事の後にい事としてフィンランド語と英語の学校に通っています。
かなり簡単な内容しかわかりませんが、フィンランド語を習うことでより生活が楽しくなりました。
仕事中の(他社との)ミーティングなどは全てィンランド語で行われるので、もっと理解できるように勉強しようと思います。
フィンランドにはフリーマーケットストアがたくさんあります。
ヴィンテージのステキな食器などが安く販売されているのでとても楽しいです。
物価が高いフィンランドですが着・食器・家具なども日本の古着屋よりも、とても安く売っているので、まく買い物をすればかなり節約できるのでは...と感じました。
中学校にも行かせていただき、Shintoや日本の学校生活について説明。着物を着て生徒にも実際に浴衣を着させた。茶道について説明し、実践。お寿司を一緒に作る、折り紙を教える、音楽の授業で日本の音楽についての授業を行った。
同じ科目ということで、自分が教えていた内容と比べることができ、新たな授業体型を知ることができました。実際に、日本でも取り入れることができる活動(ペアワークなど)を見学できたのは、有難かったです。
スクールカウンセラーの先生には、3日間ついて活動しました。授業中には気づけなかった様々な課題(問題)を生徒たちは抱えていることに気づかされました。いじめ、ネット掲載による問題、けんか等々です。日本では、生徒指導は担任団、心の問題(登校拒否など)はスクールカウンセラーがと分かれていたのですが、こちらの学校では、生徒指導も心の問題も一人のスクールカウンセラーが担当していたのに驚きました。スクールカウンセラーが常駐していることで、生徒や教員が話しやすそうでした。
フィンランドに来て、11ヶ月になろうとしています。フィンランド語については、わからないことの方が多いですが、日常的な会話がだいぶできるようになりました。生徒同士や先生同士、生徒と先生の会話はフィンランド語で行われています。これから渡航される方、フィンランド語は難しい言語と言われていますが、フィンランド語がわかる、話せるようになるとさらに研修の幅が広がると思います。自分自身が楽しいです。
つまり、この1月で感じたのは、自分がやりたかいことをはっきりさせ、それに合わせて行動する(能動的に)。さらに現地の言語をあきらめないで学ぶとさらに楽しいということです。
あと1ヶ月、学んだことを持ち帰るように、アウトプットしていくことが目標です。
(毎年11月は雨が多いみたいです)
12月は天気の日も増えてきました。
1月に入り、雪も降り本格的に寒くなり、
外に出ると顔が痛くなり、
芯から冷えていくような寒さを味わっています。(現在-10度くらいです)
フィンランドのデザイナーにとって
12月は繁忙期で、かなりバタバタしていました。
クリスマスマーケットの準備で
商品の準備・タグ付け・梱包・搬入など大忙でした。
毎週末開催されるクリスマスマーケットの
店頭に立って接客のお手伝いをしたり、いい経験をさせて頂きました。
クリスマスは研修先の方のご家族のお家に呼んでいただき
フィンランドのクリスマスの雰囲気を体感しました。
フィンランドのクリスマスは
日本の年末年始のような雰囲気で
家族で集まり、ご飯を食べたりテレビを見たりゲームをしたり
のんびりと過ごすそうです。
外にはほとんど人がいません。
お店やバスも営業していません。
フィンランドでは、クリスマス以外にも
ナショナルホリデーには
スーパーや各店お店が閉まってしまうので
事前に確認しておいた方がよいです!
残り2ヶ月半。
『 やりたいことに焦点をあてる。 疑問に思ったことは質問する。質問できるように、予備知識を蓄える』
をしていきたいと思います。
学校でもクリスマス行事に参加する機会がありました。研修先の高校ではクリスマス前のセレモニーと教会への礼拝、クリスマス給食程度でしたが、隣の中学校では生徒たちがカフェを開いたり、小学校では学年や担任の先生にもよると思いますが、トントゥ(サンタクロースのお手伝いをする子供)を図工の時間に作ったり、先生お手製のアドベントカレンダーを開けたりしていました。私の小中高校時代、宗教や伝統など文化に関連した行事を学校で扱った記憶はないので新鮮でした。
フィンランドの学校では、クリスマスに限らず実際の生活に基づいた授業が行われていると感じています。例えば、小学校の図工の時間に父の日に贈るトースト用のトングを作ったり、高校の保健の時間に鬱病に関して扱ったり(フィンランドは鬱病患者が多い)、中学校の地理の時間にフィンランドに多く自生している木について勉強したり、研修先でも生徒たちが3Dプリンターを使っていつも何かを作っています。私にはそれがどう学校での学習と結びついているのかはわかりませんが、先生方はかなりそれらを評価しているようです。(もしかしたら先生方もわかっていないかもしれませんが)どこかで繋がっている、もしくは繋がる可能性があるのだと思います。
そしてこのクリスマス、宗教行事、宗教教育について興味深いと思った点があります。フィンランドでは小学校から宗教教育の時間がありますが、生徒がキリスト教徒ではなく、親が受けさせたくなければ受ける必要はありません。その時間は同じように宗教(キリスト教)を勉強しない少人数のグループで他の事を勉強します。個の尊重をフィンランドの教育現場で痛感しました。それを可能にするの少人数教育の重要性を私はフィンランドに来てから何度も実感しました。
今月で私の研修は終わりですが、この研修中にフィンランドの"可能性"と"個の尊重"によって柔軟な教育が生み出されていると感じましたし、これは教育現場だけに限らず、フィンランド社会全体で言えることで、日本にはないチャレンジ精神や他者との共存のようなものを発見しました。教育現場を通してフィンランド社会を垣間見れたという点でこの1年はとても有意義でした。
フィンランドでは、11月の下旬頃からクリスマスまで"Pikku Joulu"(ぴっく ようる)<small Christmas>というパーティーを会社や親しい友人と一緒に開きます。私も研修先の市全体の先生方向けのに参加しました。日本で言う忘年会に近いものだと思います。どんな会かはそれぞれ違うと思いますが、グロギやピパルカック(ジンジャーブレッド)場合によっては、ヨウルトルットゥ(プルーンジャムの載ったパイ)が出される会が多いのではないでしょうか。ワインなどのアルコールも入り、みんなで軽いお食事をしてカラオケやダンスを楽しむ会もあるでしょうし、日本の忘年会と違いおめかしをして出かけることもあって、フィンランド人にとって暗い時期の楽しみなのではないでしょうか。フィンランドも近年、景気悪化で行政でも至る所でコストの削減がされているようで、このPikku Jouluも例外ではなく、盛大に会を催せなくなってきていると聞きました。それでも気分の沈んでいた私には充分でした。
11月の後半から研修先の学校でテスト期間が始まったため、近隣の小学校とその小学校付属のエシコウルを訪問していました。以前にもこの学校にお邪魔したことがありましたが、今回はエシコウルの子供たちと過ごす時間が圧倒的に多くそこの先生方とお話しする機会もたくさんありました。大学で男女参画や家族社会学などの講義を取って以来その分野に関心もありましたし、丁度日本の待機児童の問題に関する記事を読んでいたので、先生方とお話できたことも含めエシコウルの訪問が本当におもしろかったです。
小学校訪問中毎朝、お世話をして下さった先生と一緒に7時過ぎに登校するとエシコウルへ子供をつれてくるお父さんやお母さんを見かけました。エシコウルの先生によると朝番の場合、6時半に学校へ来て、子供たちを迎える準備をするそうです。もちろん子供全員がそんな朝早くに来るわけではありません。帰る時間も子供によって違います。13時ごろに迎えに来ることもありますし、17時ごろに迎えに来ることもあります。お迎えで驚いたのが、お父さんが大抵来ることです。
朝早く登校してくる子供には学校から朝食が提供されます。そして11時半頃に昼食を取り、13時半頃にはおやつの時間が設けてあります。朝シフトの先生がいらっしゃれば、晩シフトの先生もいらっしゃいます。11時ごろに登校して子供たちの世話をします。
ひとつの教室に先生が二人、三人いることは珍しくなく、子供たちが遊んでいる時間に一人の先生は教室でパソコンに向かって事務作業をしている姿をよく見かけました。先生によると、一週間の労働時間は家で残業をすることもあるようですが、仕事場で仕事をするのは40時間以内だそうです。日本で保育師の給与が低く、保育士不足が問題になっていますが、フィンランドでもエシコウルで働く先生方に支払われる給与は学校の先生のよりも低いそうです。学校の先生にはスキルが求められるけれど、エシコウルの先生には求められておらず、先生方の気持ちで子供たちを"面倒を見ている"と考えられているからだそうです。
また、エシコウル滞在中にすぐそばの保育園を訪れる機会もありました。エシコウルは小学校入学前に文字や数字などを勉強する場所で、この場所ではじめてそれらに触れるのだと思っていたので、保育園の壁に数字やアルファベットが張られていたのには驚きました。先生によると、保育園、エシコウル、小学校と徐々に易度が上がっていくそうです。数字に関していえば、保育園にもエシコウルにも数字のカードが張ってありましたが、エシコウルでは足して10になる組み合わせ(1と9、2と8、3と7...)も張ってありました。アルファベットに関しては、エシコウルではアルファベットがずらりと黒板の上に張られて、その文字から始まる絵とその綴りが張られていました。一方小学校3年生の教室では、音節で区切られている掲示(YK-SI, KAK-SI ...)をいくつも見ました。
私の研修もあと1ヶ月を切りました。漠然と教育に興味があると思っていましたが、今回エシコウルの訪問は、教育の中でも初等教育や幼児ケア、教育とは離れた家族社会学にも関心があったこをを気づかせてくれました。エシコウルに関してまだまだ疑問が沸いてきそうです。たくさんのことを学んで帰国したいと思います。
フィンランドの仕事は6時くらいまでで残業せずきっちり終わる!イメージでしたが、私が働いている事務所は少人数なので、っきりとした終了時間は決まっておらず、日によって変わるとのことです。
私の仕事内容としては
・プロダクトの物撮りやデザイナーの写真
・イメージ動画撮影、
・プロダクトの梱包やタグ付け、在庫確認、
・ポストカードなどのテキスタイルデザインの制作
と、幅広く経験させて頂いています。
だんだん日が短くなってきていることと、の日が圧倒的に多いので、影などの日程を抑えるのが日本に比べて難しいです。
フィンランドのみなさんは、本当にとても優しく日とても楽しくお仕事しています!
今週は自分の持っている週6回の授業の他に宗教の授業に招かれ日本の宗教について質問に答えたり、近隣の中学校の家庭科の授業でお寿司を作るので日本の食文化を少し紹介してほしいと頼まれ、計4回調理実習に参加し簡単なプレゼンを行い、一緒にお寿司と白玉を作りしました。
尋ねられたときには、日本人がお寿司を食べるのは特別な時で大抵レストランに行くと答えます。最近では100円で食べられるお寿司もあり一概には言えないと思いますが、フィンランド人の中には日本人は毎日お寿司を食べると思っている人もいるようで、2、3ヶ月に一度ぐらいしか食べないと言うととても驚かれます。
また、他の高校から授業で日本の文化について話してほしいと依頼され今月の後半に参加する予定です。日本に興味のある生徒や一般のフィンランド人になぜ日本に興味があるのか尋ねると、アニメや漫画に関心があるというのもひとつの理由ですが、違いが幾つもあるからそれがおもしろいという回答をよく貰います。フィンランドと日本の文化や生活様式は違う点ばかりで、どこが違うか尋ねられるといつも答えるのに困ってしまいます。来たころには驚いたことでも最近ではすっかりそれが当たり前になってしまって日本ではどうするか尋ねられて違っていたことを思い出したり、なぜそうするのか理解できるようになってきた気がします。
私に残された滞在期間が残り数か月となりました。日本と違う点を見つけると共に、なぜ日本ではそうするのか、なぜフィンランドではそうなのか自分なりに見つけたいと思います。
興味のあることについて、レポートを作成するというのがこの授業のテーマです。日本の歴史の中でもインパクトのありそうな江戸時代、平安時代を選び授業をしました。日本の生徒に教えるときとは、授業作りが少し違いました。まず、英語です。フィンランド語よりは英語の方が伝えやすいので、英語を使っていますが、普段つかわない単語は改めて調べなおすのに時間がかかります。例えば、貴族、大名などです。フィンランドの高校生は、私よりもはるかに英語を流暢に使う生徒が多いです。授業作りに時間がかかり、つらいですが、英語を学ぶよい機会になっています。
次に、授業の課題作りについてです。生徒に体験したり、考えたりできる授業を意識しています。まだまだ課題が残りますが、やってみると高校生は考えたり、意見を伝えたりする力があるので、とても楽しいです。たとえば、自分が将軍だったら、どのように大名を配置するか、、という課題を出したところ、様々に意見がでてきました。外様大名は、監視するために自分の陣地に近い場所にするとか中国からの攻撃に備えるために、日本海側に置くなどです。フィンランド人の先生も楽しい授業になったと言っていました。
自分の専門分野である社会科。生徒とともに考えながら授業を作ってみたいと思っています。英語にフィンランド語に、学ぶことがおおい毎日です。
今回お世話になったのは、生徒数が多く市の中心部近くにある中学校で、特別支援やフィンランド語が母国語でない移民の生徒たちへの支援が充実したとても興味深い学校でした。私の活動内容としては今までと同じように日本語や日本文化をパワーポイントを用いて紹介するというもので、空き時間にはさまざまな授業を見学させていただきました。
フィンランド語が母国語でない生徒たちに対してはヘルプティーチャーとして彼らの母国語が話せる先生がクラスに入りサポートしていました(アラビア語やロシア語など)。特別支援学級もいくつかあり、少人数のレッスンが徹底されていて、生徒一人ひとりを大切にしている点がすてきだなと思いました。
私のプレゼンに関しては、日本の学校制度や、やはり日本語(自己紹介の仕方、簡単なあいさつ、自分の名前をカタカナでどう書くか)などといったテーマが人気だったように思います。おりがみや寿司作りも興味を持って楽しんでトライしてくれていました。
この学校では、校長先生の方針で図工作品を多く作っていました。エスカリの児童でも作れるように工夫されており、勉強になりました。
高校の授業にて、授業内に、体験的なことを取り入れると、生徒や先生から好評でした。例えば日本の宗教紹介で、おみくじや座禅体験を取り入れたのは好評でした。自分もやっていて楽しかったです。
9月の下旬から高校生はテスト期間が始まり、授業のない私は滞在している街にある中学校や小学校を訪問しました。 行く先々の学校で、フィンランドにはいつ来たの?いつまでいるの?そして既にフィンランドに長い間いることを踏まえて、この街のどこが好き?離れるときなにが恋しくなると思う?フィンランドの食べ物で何が好き?などフィンランドに関する質もをされ答えを考える度に、フィンランドに半年も滞在していたことを実感しました。
特に"義務教育"に興味のあった私にとって小学校や中学校の授業に参加できたことは、それが1週間という短期間だったにも関わらず、幾つもの発見ができ大きな経験となりました。例えば、フィンランドで使われている教科書は絵がたくさん使用されている点や、その授業が行われる教室には、パソコンとネット環境、プロジェクターがある程で作られている点など、私が小中学生の頃に使っていたものとは全く違うものでした。2つ目の点に関しては、先生が授業中に出版社のサイトにアクセスして、該当する教科書のページを開き、英語の発音を生徒に聞かせることや、絵では説明しきれない点をアニメーションで説明してくれます。私が参加した小学校のクラスでは、殆どのクラスで黒板が使われていませんでした。
先生方とお話した際、日本に帰ってからフィンランドで学んだことを日本で活かせると思うか(教育現場で)と尋ねられました。私は、その時"できない"としか答えることができませんでした。それは、フィンランドと日本の教室の環境があまりにも違うからです。日本の出版社がフィンランドと同じような教科書を作っても、日本の学校にはプロジェクターもパソコンもネットも常備されているわけではありません。
そのことを先生方に伝えると、"なんで!あれらの機械を作ってるのは日本でしょ!"と、とても驚かれました。そうなんです、プロジェクターもエプソンや、NECなど日本製のものばかり。パソコンも、富士通のもをよく目にします。私も驚きです。
算数や、英語など理解が難しい授業はクラスを二つにわけるという発想は、日本にもあるとは思いますが、フィンランドでの方法はちょっと違います。その少人数授業を朝の2時間で行い、たとえば。Aクラスのはいつも通り8時に登校して、残りのBの子たちは10時ごろに登校してきます。もちろん、Bのクラスの子が8時に登校し、Aの子たちが10時に後で登校してくる日もあります。元々クラスには25人程しかいないのに、少人数授業だと10数人になります。生徒一人ひとりを見るのはずっと容易になりますし、生徒たちは授業に積極的に参加せざるをえません。
またこの訪問の最中に日本の学校の良さにも気づきました。日本の学校はただ"学問を勉強する場"でないことを感じました。例えば、掃除。フィンランドでは生徒が掃除をする時間はありません。掃除の時間を通して、決して掃除の仕方を学べるわけではありませんが、私は小中学校の9年間で、物や場所を大事にすることなど、"掃除"という行為以上に大事な物を学んだと思います。また、日本の中ではそれが当たり前すぎて感じたことはなかったのですが、日本人は礼儀正しいといわれる所以を実感しました。
滞在期間が残り3ヶ月となり、帰国の文字が頭をよぎり始め焦りを覚えますが、残された日々を大切にすごそうと思っています。今年はオーロラの当たり年なようで、頻繁にオーロラが出てる!と情報をもらいます。そういった、フィンランドならではのことも、最後まで満喫しようと思います。
私の場合は各校3週間ずつの研修なので、本当にあっという間にお別れのときがやってきてしまいます。こちらの学校での研修最終日、全校集会で体育館に集まったときに生徒たちが歌のプレゼントをしてくれました。それと一緒に全員のサインが書かれたカードや素敵なプレゼントも渡してくれて、気持ちがおさえきれずに泣いてしまいました。「Hei, Yuki」「Kiitos Yuki!」「Moi moi」「Hello!」と言ってくれる言葉がいつもとても嬉しくて、私を受け入れて学校の一員としてやさしく接してくれる生徒と先生方のことが私も大好きになっていました。離れるのはとてもさみしいですが、みなさんと一緒に過ごした時間は本当にかけがえのないものです。
フィンランドの人の特徴として、反応が薄いことやあまりフレンドリーではないといったネガネティブな印象は否定できないと実感しています。自分の授業に自信がないと、相手も自分の授業を楽しんでいないのではないかと思い込んでしまうのではないかと思います。さらに、フィンランドでは授業中にクラスメイトとの会話は禁止されていませんし、授業中にバナナなど軽食を取りながら勉強する姿も見受けられるので、そんなことが起きたら、しかもクラスメイト同士の会話がフィンランド語だったら、その場に他に先生がいなかったら、日本人は自分が蔑ろにされているのではないか不安になるのではないかと思います。
不安な時は思い切って彼らや先生方と話すべきだと思います。特に周りの先生方に相談する(確認)するのが最善の解決策ではないでしょうか。私にはそれができなかったので、回り道をするはめになりました。
私のクラスは必修の枠外で、日本に興味のある子が取るといった感じです。ですから、元々そこには日本に関心のある子しかいないはずです。もし彼らが私の話している最中に会話していても、私の話していることに関して会話していることが十分にあり得ます。さらに、先にあげたフィンランド人のネガティブな印象が教室の雰囲気を、空気を呼んでしまう日本人の私にとって耐え難いものにしていました。日本の学校なら授業中に会話している生徒を見かけたら、"大丈夫?"(静かにしなさいよ、の意味で)と声をかけます。それは注意された生徒たちを傷つけない配慮からでしょうか、日本で通じる言い方ではないかと思います。だから、フィンランドでは通じません。また、"何か質問ある?"の意味で"大丈夫?"と聞いてもその時には解決している可能性もあり得ます。だから、"どんなこと話してる(た)の?"と聞いてみたらよかったのでしょう。
その代わりに、"もし質問があったらその時に私に聞いてね。そしたら、誰かが私よりもうまく、フィンランド語で説明してくれるかもしれないし、それにみんなでもっと勉強できるでしょ。だから、みんなで勉強してるんじゃない?"この言葉で漸く想いが伝わりました。
そしてその悩みがひと段落した後、ご飯を炊いておにぎりを作りました。教室にいては黒板と椅子の距離は縮まらないと実感しました。その場においてあったお箸を見て、"お箸の使い方教えて!"とお願いしてくる子や、"おにぎり三角にできない~"(結局全員のを三角に成形しました) 全員、私より背が高く大人に見えますが、日本に興味のある"高校生"です。私のつたない英語も必死に聞こうとしてくれますし、私が授業の終わりに書かせている感想カードもしっかりかいてくれ、教室を出るときには"ありがとう"と"ばいばい"を必ず言ってくれます。
これから暗く長い秋と冬がやってきます。気分が落ち込むだろうと思います。また不安になることもあると思います。そんな時は、周りと会話が気軽にできればと思います。
私が知ってる限りでもマニラに10個以上、もちろんセブ島にもありますし、
もっと田舎のほうにも大きなショッピングモールがあります。
そして、毎日混んでいます。
平日はビジネスマンが、喫茶店やドーナツ屋さんでノート型パソコンを操作していたり、
休日はカップルや家族連れが、レストランで楽しそうに食事をしていたりします。
(喫茶店の中にはフリーWi-Fiが使えるところも多数あります。先進的です)
ショッピングモールはどこもスーパーマーケットが併設されており、
食料品や衣料品、お風呂グッズや電化製品まで何でもそろいます。
電化製品以外は日本よりも安く手に入るので、フィリピンで買ったほうがお得です。
映画館やボーリング場もあり、中にはスケートリンクが併設されているところもあります。
週末は先生も生徒も「モールに行こう」と言って、楽しんでくる人がたくさんいます。
私は渡航前、フィリピンでは不便なことも多いのではないかと思っていましたが、
ことショッピングに関しては、日本以上に充実していると思います。
数々のハプニング続きでしたが、工夫一つで何とかなるものです。授業は、1時間の実践を振り返りながら、改善を加えていくことで、もっともっと挑戦してみたくなってきます。多くのことを伝えることよりも、シンプルで簡単なことをしぼり込んで伝えることの方が、多くの手応えを感じます。また、休み時間もあやとりやブンブンゴマで遊んでいると、子供たちは興味津々で話しかけてきます。そして自分の知りたかったことは、つたない英語ではありましたが、先生方に積極的に質問をすることや、子供と一緒に授業を受けることで理解できることがたくさんありました。語学力がもう少しあったら、より深い質問もできたのにと、次回の挑戦での課題も明確となりました。
ホストファミリーにも恵まれ、毎日がとても充実した時間でした。毎日の授業終了後は、ホストマザーがショッピングやお茶タイムに連れて行ってくださり、変化に富んだプライベートタイムも過ごすことができました。休日には湖近くのサマーコテージにご招待していただき、サウナを初体験しました。ゆったりと、のんびりとした自然に包まれ、北欧時間の流れの中にどっぷりと浸かることで、フィンランド人のものの考え方やどんなことを大事にして暮らしているのかがとてもよく理解できます。あまりにも忙しすぎる日本での自分を振り返る良い機会でもありました。できればもう少しフィンランドにいたかったというのが本音です。ちょっと癖になりそうです。
3週間1つのクラスに入ったことで、これまでに気づかなかったことに気づくことができました。
実践した授業で、喜んでもらえたものを紹介します。
・実物を見せる。(浴衣、風鈴、扇子)
これまで写真で紹介していましたが、実物はインパクト大でした。
・おり染めで封筒をつくる。
おり染めは、半紙を広げたときの反応がとてもよかったです。さらに、ラミネーターを使って、封筒を作りました。ポケモンカードを入れたり、シールを入れたりして使ってくれています。
私にとってコミュニケーションツールである食事、一方、ストレスの要因にもなりうる食事。日本の食材がほとんど手に入らない環境で日本食をいかに作るか日々、挑戦しているところです。
先日は、クックパッドで調べたお好み焼きソースを使って、お好み焼きパーティーをしました。イタリア人、イギリス人、スペイン人、フィンランド人、マルタ人、オーストリア人、マルタ人、インドネシア人...様々なバックグラウンドを持つ人たちに好評でした。
海外には日本と違い、ベジタリアンに遭う機会も多いです。ベジタリアンがいる場合には、お肉や魚介類は一切使わず料理を作らなければならないので、苦労もします。"お好み"焼きなので、私は、冷蔵庫にあった、マッシュルームや豆、にんじんなど適当な食材を入れてみました。
お好み焼きソース;http://cookpad.com/recipe/2100942
もう一つ、ベジタリアンがいる場合に丁度良いメニューがあります。キーマカレーです。キーマカレーは、挽肉を使って作られるカレーですが、挽肉の代わりに様々な豆で代用して、他にもなすやにんじん、玉ねぎなどを炒めて、最後に水適量とカレー粉適量、出汁適量(カツオだなど日本のものでも、コンソメなど洋風の物でもどちらでも大丈夫だと思います)、塩、胡椒、とろみをつけるための小麦粉を加えて数分煮込めば完成です。
キーマカレーも、スペインやポルトガルなど様々な国の方に食べてもらいましたが、好評でした。カレー粉が手に入れば簡単に作れるものなので、現地の人に教えてあげるのにもぴったりだと思います。
お好み焼きにも、カレーにも日本の出汁を使っていましたが、フィンランドで手に入る"Kalaliemi"(Fiskbulijong)で代用できるのではないかと思います。kalaliemiを使って、お味噌汁を作ってみたところ、いつものお味噌汁と変わりはなかったので。
もうすぐ学校が始まります。学校には調理室がないので、日本食を授業で作ることは稀だと思いますが、授業で作るのにぴったりな品物をもう少し探してみようと思います。
日々自分の英語力のなさを実感していますが同時に日々成長している実感も持てるようになりました。英語圏以外の国の人たちと話すことは、フィンランドで英語を使うためのいい練習になっています。
例えば、フィンランドやドイツなど北方の国々では、ライ麦の黒パンを食べるけれど、西の方や南の方の人たちは、白いパンを食べます。フィンランド人は、毎食パンにたっぷりのバターを塗ります。イタリア人も、ほぼ毎食パンを食べます。ラスクのようなかりかりのパンを朝に食べることもありますし、お昼にパスタを食べたって、パンを食べます。水分の全くないパンを、水に浸けて戻して食べることもありますが、パンにバターを塗ることは、ないように感じました。パンにバターを塗って食べた私を見て、食卓の会話がそれになってしまったほどです。
ポルトガルや私が訪れたイタリアでは、タコは食べ物として定着していますが、フィンランドでは食べものとしては認識されていませんし、寧ろ気持ち悪がる人もいるかもしれません。友達のルーマニア人も、初めてたこを食べようとしたときは、恐る恐る食べていたように感じます。
キリスト教を一つ見ても、西や南のカトリックのお宅に行けば、イコンなどを目にすることは珍しいことではないと思いました。しかし、フィンランドで目にすることは殆どないような気がします。フィンランドもルーテル教会が多数を占めていますが、クオピオは東フィンランドに位置していることもあり、オーソドックスの人もたくさんいます。
今回感じたことが、秋からの授業に役立つかはわかりませんが、私にとっては貴重な体験でした。
・鯉のぼり
折り紙でも作れますが、私はマスキングテープと綿棒を使って作りました。
茶色系、水色(青色)系、ピンク(赤色)系、それ以外の色の4色のマスキングテープを使って作ります。まず、茶色系のテープを綿棒にぐるぐる巻きつけます。次にそれ以外の色のマスキングテープを旗のように綿棒に巻きます。水色系がお父さん、ピンク系がお母さん、それ以外の色が子どもになるので、長さに注意してください。そして、はさみでしっぽの切り込みを入れて、修正液で白目を描き、乾いたらマジックなどで黒目を描き鯉のぼりの完成です。
これは子供の日に作りました。これは、研修先の高校生がかぶとを作って被って喜ぶのか不安だったので代替案として持って行って作りましたが、作る前にどちらを作りたいか聞いたところ、"両方"と言って、作ったかぶとを被って、小さいこいのぼりを持って喜んでいました。
・ういろ
riisijauho(米粉) とperunajauho(じゃがいもの粉;片栗粉)で作れます。作り方はcookpad参照(http://cookpad.com/recipe/2621244)
・白玉
riisijauhoとperunajauhoで作れますが、冷えると仲がぼそぼそになるので、水の代わりに豆腐で作ることをお勧めします。
豆腐も自分で作れます。プレーンの豆乳を買ってきて、にがりがあればそれを使って、なければ薬局でエプソムソルトとう名で売っているようです。豆腐がおぼろ豆腐のように柔らかくたって大丈夫です。豆乳ににがりを100mlに対し、ティースプーン1杯の割合で入れるとcookpadでは見ましたが、私はもっといれます。そうしないと固まりません。その後、あれば電子レンジ、なければ湯銭を使って温め、できあがりです。
その豆腐を使って、riisijauhoとperunajauhoを大体3対1ぐらいの割合で入れます。耳たぶぐらいの柔らかさになるまで粉で調整します。生地ができたら、お団子を沸騰している湯に入れ、白玉が浮かんで来て数分たってから冷水にとり出来上がりです。 これで、白玉フルーツポンチもできますし、醤油とみりん、お砂糖、お酒があればお団子も作れます。
・おかき
puuroriisiという、お粥用のお米をご飯用に炊き、perunajauhoを適当に混ぜ潰していきます。そこから、小さなボールを作り、後は揚げるだけです。お米に水分があまりないので、油はねすることはあまりないと思いますが、作ったボールを数時間から1日冷蔵庫で寝かせてみてもいいと思います。お好みで、ここにゴマやあれば青のりなどを入れてみるといいと思います。味付けは塩やお砂糖のシンプルな物や、醤油、砂糖、みりん、酒を使った甘辛いものなどお好みで。
・紙漉き
牛乳パックを使って紙すき体験ができます。木枠は学校の技術の先生が持っていました。なければ、ストッキングとハンガーを使うという方法もあるようです。
思い返してみれば、時間の流れは速かったと感じますが、様々な場面が思い出される、とても濃い時間を過ごすことができました。
5月も基点としている学校以外の高校に訪問し、習字のワークショップをおこないました。日本語の授業のない学校でしたので、限られた時間の中でひらがな、カタカナ、フィンランドに関係ある漢字などを紹介して、自由に書いてもらいました。自分の名前をカタカナでどう書くかや、墨のにおいなど、それぞれ興味を持ってもらえたみたいです。
最後には、中学校の最後のセレモニーでフィンランド語でのスピーチにも挑戦させていただき、無事に研修が終了しました。これから、自分自身が感じ取ったこと、考えたことをひとつひとつまとめていきたいと思います。
日本の学校の校則を中学1年生に、教えたところ、非常に驚いていました。髪型や服装が決められていることに、理解ができなかったようです。
文化の違いを良し悪しではなく、楽しんでもらえるように、これからも伝えていきたいと思います。
授業で教えた「あっちむいてほい」は、とても楽しんでもらえました。遊びは世界共通。言葉が通じなくても楽しめます。どんな遊びを紹介できるか、夏休み中に考えたいと思います。
ずっとあこがれていたフィンランドでの生活、学校。1年しかないのだから、アクティブに動いていこうと決意し、この1か月間やってきました。
職員室では、空いている先生に話しかけたり、折り紙ピカチュウを話のついでに紹介したりしました。
その成果かどうかわかりませんが、先生方に依頼され、現在授業をしています。日本紹介から始まり、折り紙(ピカチュウ)、音楽(三味線)、調理実習(巻きずし)、歴史(第二次世界大戦)などと、自分の予想以上に授業をさせていただき、うれしい限りです。
現在1か月、外国人というもの珍しさで、授業を依頼されていると思います。継続的に、授業の依頼がもらえるように、一つ一つ手を抜かずにやっていきたいと思っています。
今では、フィンランド語で簡単なコミュニケーションがとれるようになりました。おりがみの折り方を教えるときなどは、英語よりもフィンランド語の方が使いやすいし、フィンランド人も多少間違っていても理解してくれます。私は、このような簡単な指示や、おりがみのときに使う単語をホストファミリーの子どもたちに教えるときに覚えましたが、最初にこれらの言葉をピックアップして覚えると、伝わりやすいのかなと思います。
残り1ヶ月、時間を大切にして過ごしたいと思います。
しかしなかなか慣れないものと言うと、フィンランド人の名前。一度綴りを見ないと覚えられません。学校の先生方には一人ひとり綴りを教えてもらって、そのお返しに折り紙で折ったトトロに名前を書いてプレゼントしています。そのトトロに私の名前も書いて、日本名に馴染みのないフィンランド人も私の名前を覚えられるようにしました。折り紙は、外国人に喜ばれるのでそこに自分の連絡先なども書けば、名刺代わりになるのではないかと思います。
今期はあと3週間しか授業がありません。最後の1週間は、テスト週間のため授業はお休みです。テスト期間中は地元の小中学校か、南フィンランドの学校へ行く予定です。
南フィンランドの学校では、中高生への日本語教育が活発に行われていているので、様々なアイディアなどを学びに行ければと思っています。そこの学校で日本人のインターン生がいるので、その方とも交流できればと思います。また、ここの学校は日本の教師団の視察を支援しています。この点にとても感心があるので是非訪問できればと思っています。
また、秋からは学校での本格的な授業に加え、コミュニティーカレッジで日本の文化紹介と日本語教室を開くことになる予定(月曜日に打ち合わせに行くのでまだ正式には決まってませんが)なので、その学校を訪問して様々なことを吸収できたらと思います。
As for checking gate at the airport into the country, I went through the Auto-gate. I wasnt asked any questions and didnt got a stamp on my passport. Since I didnt know that stamps are not given at that case, I worried about it so much. That´s why I reported it.
On the first day of starting my life at apartment I had a big mistake and have learned a important thing to stay at a share-apartment. I left my room for share-kitchen without my key even though the door is a auto-lock type... Although I maneged to open the door thanks to neightbors help, I lost 35EUR... Now I always wear the key using the chain I got from Kuopas, a lessor
毎日があっという間に過ぎていっています。
今月は、他校へ訪問してのひなまつりのプレゼン、日本の教育制度についてのプレゼン、その他にも授業など充実した日々が送れたと思います。日本のことについて授業をするたびに、私自身が日本をより知ることができていくようです。ただ、興味を持ってもらう、印象に残るという授業をするのはとても難しいと感じています。他の授業を見学させていただくことも多いのですが、そのときの先生方の授業の進め方から、学ぶことも多く、それを自分なりに応用できるように考えています。
また、今月は、授業とは別に折り紙を教える機会も多かったです。折り紙はとても反応がよく、説明するのは難しいですが、よく使えるコンテンツです。毎回、いくつかサンプルをつくっていって何をつくりたいのかきいてつくるようにしていて、私がつくるものを見ながらつくるという方式をとっています。ただ、このやり方だと、家に帰ってからもう一度つくるということが難しいので、作り方画書かれたものを、配るべきだと感じました。
来月は、幼稚園の訪問もあります。内容などかなり工夫が必要だとは考えていますが、子どもたちが楽しかったと感じてもらえるように構想を立てています。また、今回はフィンランド語での授業に挑戦する予定です。
フィンランドのイメージと教育システムに興味を抱き、このプログラムに出会って即決した一年半前。その時抱いていたよりももっと大きな経験ができました。
まず第一に人に恵まれたということ。学校の先生を始め、その家族、そして生徒たちに本当にたくさんのことを教えられ、与えられました。この関係はこれからもずっと途切れないように保っていけたらと思っています。
それから未知の言語をゼロから習得できたということ。最初は皆の話すフィンランド語が全く分からず放課後や週末が待ち遠しかったのですが、会話をしたい一心で独学し、さらに時が解決してくれて今では不自由なく会話ができるようになりました。4か月ころからは生徒とコミュニケーションが取れるようになったことで、授業にもより積極的に参加できるようになりました。英語も知らず知らずのうちに少しは上達していたようです。
そして日本の文化を教えるうちに私自身日本にさらに興味を持てました。今まであたりまえに受け入れていた日本の文化を外から見ることで、その魅力に気づかされました。もっと日本の中も旅をしてさらに良さを発見していきたいです。
「また絶対に帰ってくるんだ」という場所ができたこと、私の夢へのモチベーションの大きな財産になりました。今インターンをしているみなさん、これから行こうかと考えているみなさんには自分で決めた期間の中でできるだけたくさんの人に出会って、出かけて行って、様々な生き方をできるだけ見てほしいと思います。それはきっと自分の生き方にもつながってくるはずです。
小学校の先生を日本でいつかやりたいという夢や、教育を通して世界、地域そして世代をつないでいきたいという未来を抱かせてくれたこのインターンシッププログラムに感謝します。
朝は9時近くになってようやく太陽が昇ってきて、夕方16時は真っ暗になっている日照時間の短さに、心身を慣らすことが大変でした。フィンランドの11月は「死の月」と言われる。皆太陽とともに気持ちが沈んで、精神疾患を患いやすいから。かつてうつ症状を訴えた生徒と向き合った身として、フィンランドでは教育現場がどう対応するのかを研修したかった。そんな自分自身が、そこまでひどい症状に見舞われなかったのは、現地で出会った剣道のおかげだった思う。ヨーロッパ大陸に根ざす剣道を愛する者達と共に稽古し、発散する場、会話する場を定期的に持つことが出来たから、12月末の現在、精神は安定している。
その恩を返す場は、研修期間もあとわずかとなった1月に訪れる。「Yutaが全て企画・実行する子どもたち向けの剣道キャンプをやってみないか」、という提案を頂いた。「俺だったらこうする」のようなアイデアを自由にやってみろ、お膳立てはするからって。そうだなあ厳しい稽古も提案するさ、けれどそれが終わったらみんなでお味噌汁を作って和食を楽しんで、サウナに入った後は折り紙教室も開く、大人も一体になって参加出来るイベント。フィンランド語に敬意を払いつつ、楽しく日本語を学べるイベント。1月2日~4日開催!
その為の準備という目標を持った今、留学した自分に満足かなんて答えられるわけがないんだ。きっとイベントが終わっても、帰国しても、復職しても分からないと思う。何年かして、参加した子どもたちが、剣道や日本に一層興味を持った大人になった、という知らせを聞いて、始めて「全てが終わった」と言えるのだろうから。
1日目・日本紹介、ゆかた
2日目・絵本、箸
3日目・習字
4日目・カレーを作ろう
5日目・音楽、トトロ鑑賞、かるた
"日本に旅行に行こう"というテーマで、
日本パスポートを発行しました。(遊びのです)
それぞれのページに文化紹介を載せて、それを終えるとスタンプを押す。
という、パスポートです。
どんなことをしたのか、紹介します。
○日本紹介
タブレットを使って、国旗・食べ物・警察官・消防士・夏祭り
などを紹介しました。クイズも入れつつ、"日本では食事と一緒に何を飲むでしょう"
とか、"たこ焼きの中に入ってるものは何でしょう"とか。
○ゆかた
日本から、子ども用の浴衣を男女1着ずつ、購入
ちなみに、120cmサイズで、フィンランドの6~7歳サイズぐらいです。
特に、女の子はすごく喜んで着ていました。
○箸
日本から、子ども用の箸を購入
日本では、どんな食べ物を箸で食べるか、食べ物の絵カードを使って紹介しました。
折り紙の箸置きも使って、茹でたマカロニを食べました。
そのあと、給食も箸を使ってたべたいということで、スープの日も、
マッシュポテトの日も箸で食べました。
○習字
半紙、筆、すずり、墨を100均にて購入
私のクラスは、だいぶ日本語に興味をもっていたので、
それぞれの名前をカタカナと漢字に訳したものを配布しました。
硯を使って、墨を作る工程を見せて、本番では、液体の墨を使いました。
○カレー
子どもには野菜を切ってもらい、あとの工程は私が調理しました。
カレーのルウは、ヘルシンキの東京館というところで買いました。3.2ユーロです。
カレーは子どもも、先生もみんなおいしいと言って食べてくれました。
もちろん、箸で食べようとする子どももいました。
米は、Purroriisiというのが一番日本の米に似ています。
○音楽では、タブレットを使って雅楽を聴いたり、
日本語で、歌をうたったりしました。日本の歌のCDを給食時にかけて聞きました。
○トトロ
図書館にジブリの作品は必ずあると思います。
トトロの映画の中にも、畳・ふすま・風呂釜・お地蔵とか、
初めてみるものがたくさんあるみたいで、とても興味を持って見ていました。
ひぐらしの鳴き声を聞いた子どもが、"これ、なんの音?"と質問。
○かるた
日本のカルタを、フィンランド語に訳して遊びました。
例えば、ジュースは、"mehu(メフ)"というのですが、
"me me me mehu"という感じに。
かるたの中にも、日本を紹介できる絵がたくさんあるので、
楽しめると思います。
"はいっ!!"と、元気に言ってカルタを取っていました。
○折り紙
折り紙は普段から、使っていたのですが、
今回は、箸袋を作りました。とても簡単に作れます。
そこに、箸を入れて持って帰りました。
毎日、子どもたちが「ねえ、今日は何をやるの?」と、
すごくワクワクして待っていたのが嬉しかったです。
私のクラスは、子どもが9人だったので、また小学校の大人数とは
条件が異なるかと思いますが、その年齢によって興味をもつものが違うんだろうな
と、思います。
例えば、幼稚園の子どもたちが気になることは、
・動物がいるのか
・ネコはいるのか
・鳥はどんな鳥がいるのか
・日本の子どもは、箸を使うのか、などなど
そんなこんなで、楽しい1週間でした。
各クラスの始まりは一斉ではなく、ずれています。例えば、3時15分スタートのクラスの隣で、4時スタートのクラスが持たれると言った具合。最終のクラスが終わるのは20時になることもあります。そのかわり午前中のクラスは少なく、月水はありません。
美術専門なので、一般の学校のように算数・国語・外国語・社会・理科・体育といった授業はありません。音楽は3年生までの児童向けに美術とセットのクラスがかなりあります。
授業の構成には工夫と伝統があり、材料・道具はバライティーに富んでいます。美術に関わろうという方には学ぶものがたいへん多いと思います。
ただ、一般の学校に関わってきた人や今後そうしたい人にとっては足りないものがあります。私は、7日間だけでしたが一般の学校にも紹介していただき行かせてもらいました。
結果的には両方の学校で学べ、授業をさせていただけてかえってよかったと思っています。
また、この学校では先生方の登校下校時間がずれており休憩時間もずれているので、先生方が集まって休憩する時間がありません。自分から話しかけにいかないと、話すきっかけがつかめません。話しかけると先生方はとても親切熱心に教えてくれました。
また、週に1回の参加ということでカリキュラムは変更しにくく、授業をさせてもらうなら、かなり早くから相談しにいかないと難しいと思います。
これから行かれる方は、この辺りの事情をわかっているとよいと思います。
人数は8人と少ないのですが、普段の様子ではあまり授業に熱心に取り組んでいない生徒が多く在籍しているクラスです。
パワーポイントを使って写真を見せながらマカロニをつまむ練習、そのあとにチーム対抗でどちらが早くマカロニを移動できるか競争をしました。
すぐに使えるようになる生徒、てんで動かせない生徒さまざまでしたが、競争のときにはどんな持ち方でもいいからマカロニを掴もうという姿勢になり、積極的に参加してくれました。
ただレクチャーするのではなく、それをゲーム感覚で楽しめるものに発展させると食いつきがとてもよくなります。
特に始業式など特別な行事があるわけではなく、いつも通りに授業が始まりました。
今月は、2日間にわたり小学校を訪問し、1年生から6年生まですべての学年で授業を行いました。
クイズを交えた日本の紹介やおりがみ、簡単な日本語を学年に応じて教えました。
折り紙は、どの学年でも楽しんでくれたみたいでした。
小学校での授業は、日本の紹介よりも、日本のもの(おりがみや日本語の数字)を使って楽しむことに重きを置いて構成を考えました。
結果的に、日本の紹介と言われて最初に紹介するようなことを省いた学年もありましたが、これから学校で習ったときに、japaniという国と今回やったことがつながって、興味を持ってくれたらいいかなと思います。
また、今月は、研修している学校とは違う中学校・高校にいき、折り紙を教えました。
普段の授業とは違い、土曜日の特別授業の中の一コマという位置づけでした。
以前、折り鶴を折ったことがある生徒もいると聴いていたので、オーソドックスなものよりも、
出来上がりが面白いものをつくろうと考え、動物やポケモンのピカチュウの顔が描かれた風船と、駒を考えました。
折り鶴などとともに、それらの見本も事前につくっていき、どれをつくりたいかをきくと、ピカチュウとの答えがありました。
こちらでもポケモンは有名で人気なようで、ピカチュウの風船はとても受けが良かったです。
また、時間が余ったグループでは駒も作ったのですが、こちらも、つくった後に遊べるので楽しんでもらえたようです。
来月は、研修校の美術クラブで折り紙を教えてくれないかと言われているので、これらをまた、つくってみようと思います。
最近では、先生方が朝出会ったときにgood morningと言ってくださっていたのが、huomentaに変わってきました。おはようございます、と言ってくださる先生もいます。
本当に簡単な会話ならフィンランド語でもできるようになり、研修終了までには日常会話ができるまで上達したいなとかんがえ、日々練習しています。
12月はクリスマス休暇もあったのでいつもよりも活動期間が短かったのですが、2つの小学校への訪問や日本のシスタースクールの生徒の訪問などたくさんのことを体験することができました。
普段は中学校で授業を行っているため、小学校出の授業は時間の長さ、雰囲気などの違いを感じました。高学年になると、英語もある程度通じるようですが、下の学年の子たちには通じないので、フィンランド語で指示の仕方だけでも言えるようになっておくべきだと感じました。今後もいくつかの小学校の訪問が決まっているので、もっと工夫していきたいと思います。
日本のシスタースクールの生徒の訪問は、私がここに来てから感じたことを改めて考えて伝えるいい機会になりました。
学校のある地区にはスエーデン人が多くすんでいて、学校の児童の多くがスエーデン人だということが最近分かりました。
フィンランド語を少しずつ覚えて使うようにしているのに、いっこうにわかる言葉が出てこないクラスがあることに気づき、聞いてみるとスエーデン語中心のクラスがかなりあるとのこと。
授業の流れやポイントが分かってきたので、手伝えるところを増やしたいと思うのですが、やはり言葉が通じないことがひっかかり、多くの事はできていません。
一般の小学校に行った仲間の情報では、同じクラスに1週間ずついて、週の始めに自己紹介をし、週の終わりには授業をするというパターンの繰り返しだそうです。これなら、子どもとも担任の先生とも馴染みやすいし、担任の先生に通訳などの手助けをしてもらえば授業をすることも可能だと思いました。
私のお世話になっている学校ならではの長所もあるのですが、子どもたちは週に1回しか来ず、私は1日に5つ程度の授業を巡っているので、なかなか子どもたちとも馴染めません。
とはいうものの、2週間ほど前に授業案を作って会議で見てもらいました。
11月末からの時期は、クリスマス週間に向けたワークショップの企画や準備、さらには学期のまとめで学校中が忙しく、まだ授業はできそうにありませんが、年が明けたらチャレンジしたいと思って準備を進めています。
先週の1年生のクラスでは、日本語の自己紹介を教え実際に友だち同士でやってみたり、日本語の数字を使ってゲームをしたりしました。数字を教える際は、IIPの資料からヒントを得て、に(ni)はkani(フィンランド語でうさぎ)のniだよ などと似ている音とともに教えました。ややダジャレ大会のようになってしまいましたが、子どもたちには楽しんでもらえたのではないかと思います。
今週の2年生のクラスでは、自分の名前をカタカナで書く活動をする予定です。coやje(ジェではなくイェ)など名前の中にはアイウエオ表によっていないものもたくさん。表を配るべきか、それぞれの名前の見本だけ配るべきか、苗字も書きたいって言うだろうなあ、など悩むことはたくさん。もう少しよく考えてみたいと思います。
日本にいたころから想像はついていたものの、いざ暮らしてみれば寝付くという概念自体が、「暗い夜だから眠る」ことから「遅い時間だから眠る」ことへ覆り始めていると感じます。幸い、授業の準備や学校見学等やることがたくさんあるため、暗さによる鬱屈はさほど感じずに過ごせていますが、後進でフィンランドへ向かわれる方は是非、この暗さをきっかけに友人を多く作っていただけると思います。
寒さに関しましては、着込めば不便なことはないと思っておりますが、いかんせんこれからより一層気温が下がってくるかと思われますので、まだ分かりません。
さて、本題となりうる授業に関しましては、さすが高校生、ちょっとやそっとではウケが取れません。彼らが主に興味を置いているのは、現実味のあふれた文化的側面と言えましょうか、日本の学生生活であったり、市街地の高層ビルはもちろんのこと、その周りを歩く人の様子など、日本の暮らしに根付いて理解を深めたいといった様子であります。つまりは日本語を学ぶにあたっても、実際に日本を訪れた時や現地人と会話する際はどのように使うか、発音やイントネーションなど実践的な部分に重きを置こうとしているなという印象を受けています。教本から学ぶことも多かったものの、私自身がこれまでに使ってきた日本語から生徒へ教えることへのヒントを得ることも少なくはありません。
9月~11月の学期ではそういったことを生徒から学ばせていただきました、一週間ほどテスト期間があり、また先日から新しく授業を始めたところです。今期で最後となるかと思われますので、生徒が日本を訪れた際に少しでも日本語が使えるよう、指導して参りたいと思います。
しかし海外滞在期間の数え方が、いつのまにか「何ヶ月経った」から「あと何ヶ月」にシフトしている。パスポートにどっかりとスタンプを押されてから奇しくもちょうど7ヶ月経った今日までに、北欧の人情に触れ、融合すればする程、私を寄る辺無い気持ちにさせるのだ。そして脳裏では、新たな計算が始まる。日暮れの4時、学校帰りに自転車を転がしながら、7をたす。日本は夜の11時か。
帰国後について全く考えなかったわけではない。けれど最近は7をたすことが多く、そして今夜は眠れそうにない。ふと、日本の同僚・知人に手紙を書いてみようと思う。お元気ですか。
日本語の授業では先日、巻き寿司の調理実習をして、生徒たちは和風の味に挑戦しました。BGMとしてジブリの和楽器アレンジ 曲を流すと、ハミングしながらお米を研ぎはじめる女の子が印象的でした。授業では形象文字の成り立ちを教える為に「Well, let's go to Kyoto!」と題して、古都を旅しながら「京」「都」「清」「水」と紹介しているうちに、なんだか私まで京都に行きたくなってしまいました。文化紹介の他に、私は現地校の英語の授業を代役することがあります。母語が違う人間同士が、意思疎通を含め英語のみを教え学ぶ80分は、実に有意義です。帰国後は英文法を黙々と演習させる時間の代わりに、ペアワークで英文を口にしながら演習する活動を導入するつもりです。そのための教材作りのヒントを得、生徒の意欲を観察することが出来ました。また、世界各国の特色を、一人一カ国プレゼンをする活動を温めています。ネットが普及した昨今でさえ、生徒一人が共有する世界の情報は限られています。学級というユニットがある日本だからこそ、友達の発表を聞きながら、知らない世界を広げることが国際理解教育の一助とな
ると考えています。
いつも下宿先のサウナに入りながら、翌日の指導案を考えます。先日は原子力発電を授業で取り上げ、日・フィンの比較を高校生に討論させたのですが、自国の政策について明快な意見を持つ生徒たちと、充実した時間を共有しました。オンカロ(世界で初の、放射性廃棄物の最終処分場)は滞在先から近いので、年内に訪れようと思います。
日本に帰ったら、作り方を覚えたフィンランド料理を紹介します。私はマッシュポテトが大好きで、同じ味を日本でも振る舞いたいです。また、現地の剣道場に通い続けている中で、剣道の国際的な普及と活性化というテーマに大変興味を持つようになりました。自信を持って取り組めるよう、なお一層、残りの数ヶ月を精進しなければなりませんね。~7をひいた北国より~
中学校にはフィンランド語がしゃべれない生徒がいて、その生徒たちとともにフィンランド語の授業を受けることができているため、少人数で楽しくフィンランド語の勉強ができています。職員室でフィンランド語の教科書を開いていると、いろいろな先生がその教科書を見ながら、フィンランド語を教えてくださいます。フィンランド人は確かにとても英語が上手で、コミュニケーションは充分に英語でとれるのですが、普段の会話はもちろんフィンランド語です。先生同士や生徒同士の雑談に入ることができないのは、とてももどかしいです。雑談に少しでも参加できるようになることを目標にして勉強しています。
他の方の体験談にもあったのですが人口に関する質問がとても多いです。「日本にはどのくらいの人が住んでいるの?」「あなたの街はどのくらいの大きさなの?」などなど。私自身自分の生まれた町が小さいほうだと思っていたのですが、ここの方々からすると比較的大きい街のようです。
子どもたちの質問に片言のフィンランド語で答えると、とても嬉しそうにしていました。彼らの表情を見ていると少しでもフィンランド語を話せるようになりたいなと思います。
「それはね、私が日本語を話せなくて、Yutaがフィンランド語を話せないからだよ。」
英語を第二言語として学ぶ国民として、英語は海外人とコミュニケーションをとる手段である。国家予算の大半を社会保障と教育にかけたフィンランドでは、一方で海外の産業的娯楽を取り入れたいという気持ちが本当に強い。日本を例にとっても、学生が漫画を読むという行為は日本の彼等と何も変わらない。一つ決定的に違うのはそれを何語で読むかだ。フィンランド語に翻訳されてなければ英語で読むわけだ。英語でyoutubeのanimeを見るわけだ。彼等にとって英語はいわばマスターキーのようなもので、あれば世界が広がり、あった方が良いと考えている。日本の武道であればなおさら、未知の日本語は英語訳されていれば幾分ハードルは低く、しかし英語からのみ文化として取り入れ、脈々とこの地にkendoを根付かせてきたのである。ヤルノの答えはその意味ではまったくの正論だった。しかしもし、私が日本の教壇に立ち続けていたら、同じ答えを生徒に返すことが出来ただろうか。「なんで英語やんなきゃいけないんですか。」日本の学生が抱くその質問は、字義通りの解釈では納得の行く答えは返せないのだ。すなわち「大学受験で点配分が高い教科だからだよ」とか「将来役に立つからだよ」といった、誰もが知っている自明の再確認や、米国・中国を主軸に潜ませた日本式グローバリズムの抽象化表現は、生徒の求めるところではない。まして英語教師の求めるところでもない。「なぜ英語を教えるのか。」
日本の学生が聞いてくる「なんで英語やんなきゃいけないんですか。」とは、背景心理を突き詰めれば「なぜ第一言語の日本語は世界共通語じゃないんだろう。なぜ第一言語が英語である人に英語に合わせて会話をしなければならないんだろう、はじめから英語しゃべってたら欧米(先進国)の人との会話が楽で、非英語圏の人に英語を強制出来る優位に立つのに。そして結局、日本の尺度でのそれは点数化することだけなのか、しゃべれないの前提でさっ!」というやり場の無い苛立ちに過ぎない。それを現場の教師が質問の文字通りに捉えて答えたところで不満が増すだけなのだ。日本の地理的環境が欧州・欧米から遠いので、グローバル化と言っても地続きに共感が得られない。そしてアジアにはアジア特有の政治的課題があり「世界と繋がろう」という平和的キャンペーンは、まずは環太平洋圏という地域からの構築を強いられる。先の日本式グローバリズムとはそのことだ。もちろん同様の問題は欧州にも発生していて、一見強い絆で結ばれたように見えるEUという土台はそれ以上肥大化せず勢いを失うことを迫られている。一国家にとって地はあまりにも広いようだ、一地域をまとめていくために近隣諸国との対応で手一杯になってしまう。けれど、一個人の文化の享受は違う。
EU圏に住み、アジアの島国の伝統武道を愛してくれる。内省的な国民性や互いの言語に類似性を見出し、けれど出来る限り発祥の地の特色を失わないように取り入れたい。そのために英語がどうしても必要なのだ。読めるだけでなく話せることも必要なのだ。お互いが英語以外の第一言語であるから、思うように流暢な表現が出来ないけれども、確かに意志が疎通されていく。グローバル化とはこのことだと思う。自分の国籍に誇りを持つことが前提にあって、その上で他国を尊重する時代のうねりに生じた産物が英語だったから「私が日本語を話せなくて、Yutaがフィンランド語を話せないからだよ。」という大人も子供も納得出来るシンプルで素直な答えが生まれたのだろう。
少年は「I can speak Finnish and "Englanti" a little.」と言った。私は「Mina puhun vahan suomea.」と答えた。
現在、フィンランド語の学習をしながら、先生方とは英語で話して授業の見学研修を進めています。私の英語が未熟なのが主な原因ですが、先生方も母国語のようには表現ができないようなのですらすらとは会話できませんが、分かりあえることがたくさんあります。
一般の学校の様子も知りたいのですが、これだけ幅広い年齢の子供を発達段階に応じて計画的に教育していくシステムに出会えたことは、むしろ幸運だったと今は思っています。
始めは何でもないように見えた授業内容が、長年の理論と経験の積み重ねで確立されていることが分かってきて、毎回感心しています。
少人数指導(先生1人に5人から15人)。だからこそできる部分が大きいのですが、先生方の工夫や努力がそのまま共有され、実現されていて無理や無駄なく進められていると思います。
教材も工夫されたものが毎週変わって出てくるので、子供たちは知らず知らずのうちに色々な表現手段を体験しています。絵の具、筆、紙をはじめとして様々な材料、道具がすべて学校で用意されていて、個人や家庭の用意はありません。
学費は、学校の案内書によれば、年400ユーロ程度。かなりの部分を国の財政で賄っていると思われます。
でもちょっと、間違っています。
① 本棚にある日本の絵本を手にとって、
「おれ、中国語分かんないから読めない。」
② 何の肉をフィンランドでは食べているかという話になって、
「犬の肉を食べるのは、中国と日本だよね?」
③ "祭"とプリントしてあるハッピを着てハチマキをつけて、
「おれ、忍者!」
④ 「"みかに"、って言うんでしょ、日本語でオレンジのこと。」
⑤ 調理室から持ってきたジャムを見て、
「なんで、日本からジャム持ってきたの?」
私 「これ、フィンランドのジャムだけど。」
⑥ 「日本には、ドラゴン何匹位いるの?」
最近はよく、「これ、日本語でなんて言うの?」っていう質問をされます。
日本語とフィンランド語は比較的発音が似ているので、
日本語の響きが面白いようです。
何はともあれ、興味をもってくれているのはとても嬉しいです。
現在段位を取得している私は「級」大会には選手として参加できない為、審判員の役目を仰せつかった。フィンランド人同士であれば、フィンランド語で審判をする。といっても初心者の部で「Kaksi Kelta Men.(面打ち2回!)」と指示するだけなので困難ではない。ロシア人をはじめ各国の留学生も混じるため英語が基本公用語となる。そして身振り手振りも交えて「One-step forward(一歩前へ)、Nine-step apart(九歩の間合)」と選手の立ち位置を促したり、鍔競り合いの反則を英語で説明したりする以外は全て「日本語」の発声となる。大会には日本人の先生が名誉会長としていらっしゃる。剣道国際化の先駆者として、Finlandでkendoが親しまれる為に欠くことのできぬ存在として認知されている。
アンナは銀で終わった。ポリ道場では一週間前から朝練も導入し、気迫充分に挑んだが判定制の基本稽古の部で負けてしまった。誤審ではないけれども判断基準が違う審判の価値観がもたらした結果であった。名誉会長の先生も後に、アンナが一番声が出ていて打ちもキレイだったと褒めてくれたが、その感覚は日本の感覚なのだろう。声と手と足が三拍子揃う打突(剣道ではこれを「気・剣・体の一致」と呼ぶ)よりも、手足バラバラでも打ちに威力がある・良い音がした方が優勢になってしまった。アンナの兄オスカリも一回戦で負けた。ポリ道場には、負けて悔し泣きする門下生が集うからこそ、私も続けて通いたくなる。とはいえ今日の個人戦は早々に敗退してしまったので、明日の団体戦にかけることになった。
私は主審に入る前に、高校剣道で一本になる基準を頭からぬぐい去ることと、海外で剣道をする剣士にとっての一本は何なのかを考えながら挑もうとしたけれど、結局結論が出せなかった。先の基本稽古の部の判定が余計に混乱させた。気・剣・体の一致は?残心は?間合いは?そんなことを考えているうちに場外反則で一本取られてしまう選手以外、誰も一本を取れずに引き分けになる試合ばかり続いてしまった。名誉会長の御教示を仰ぐ。「阿部さんね、厳しすぎ」
「incentiveを与える為にはちょっとした良い当たりも一本としよう。足と手が合い残心までの全てを見たかったのだろうけれど、そこまで技術があるわけではない。引き技も同様で強く打てる子と力がない子が一緒に戦うわけで、日本のように低学年の部、高学年の部と年齢制限をしないから、打突部位をしっかり見てあげて当たったら一本!審判が取ってあげないと「今のは一本にならないのかな」と子どもは思ってしまって次からは打たなくなってしまう。」全てのヨーロッパ地域に、日本の風土で剣道を享受した先生がいるわけではない。言葉の壁を超えて、日本人としてkendoを根付かせるための姿勢がそこに在るような気がした。既存の価値観を教えるのは容易い。「I don't think so. In Japan~」という押付けだけは私も回避したが、ただそれには何度も何度も各地で集まって合同稽古を開き、多くの人間たちと見解を統一していく必要があろう。有段者が上から物を言うのではなく、選手に気付きを与えて成功体験を積ませる。その信頼が図らずも、剣道に対する敬意と愛、さらには日本語を勉強したいと思う門下生が現れることにつ
ながる。名誉会長は他のフィンランド人審判にも一本になる打突の議論を持った。それは指示ではなく、どう思ったか意見をすくい取り話し合うという、紛れもない議論の場だった。
以降は翌日まで、我々審判団はガンガン旗をあげ、打ち消し合い、試合後に反省検証を行っていった。Turku大学の団体戦を名誉会長の先生と共に見ていた。「あのインド人の女の子は10ヶ月前に始めたばかり。副将の彼は医学部でもう2年くらい剣道やっているかな。すぐ小手に行っちゃうんだ、気が小さいのかね、まっすぐがーんと面に行けば良いのに。ほらまーた小手行った。面だ面、行けっ行けっ!そうそう、それで一本だ。」小声で独り言を言いながら表情は楽しげであった。団体戦はOuluの北風兄弟(道場名)が優勝した。袴の下にヒートテックを履く必要もないほど、エキサイティングな1日であった。
まだ、2週間ということですが、こちらに来て感じたのは日本のアニメ、漫画に興味を持っている人がやはりたくさんいるということ。もともと聞いてはいたのですが、本当にたくさんいます。ですので、もっとアニメや漫画について知識を持ってからこれば良かったなと思っています。私のすごく少ない知識でも、アニメ、漫画の話をすると生徒たちの反応が良くて、話し始めるとっかかりになっています。
学校では週30時間(6時間×5日)を目安にタイムスケジュールを組んで下さり、全学年+障害を持った子どものクラス3クラスを回れるようになっています。今のところ授業見学と言う形が多いですが、低学年の算数、英語のサポートや先生に頼まれて、授業中に2人教室から出て来て10分程英語でゲームしたり、質問して答えてもらったりなどをしています。その英語の授業の区切りがついたので次回からどうする?と聞かれ、先日毎授業の最初に5~10分程日本について英語で紹介し、その後各生徒が教室外で5分程フィンランドの事や紹介したいことについて英語でスピーチしてもらうと言う提案をし、いいね、それやろう!と言ってもらいました。他にも3クラス程で日本の折り紙やものづくりをやって欲しいと依頼してくださっているので、期待に応えられるよう考えています。
また、来月に学校の教員ミーティングの際の日本の小学校の紹介15~20分程と、イギリスから13人の先生方が見学に来られる際に1ヶ月で感じたことや日本と違うことなどを15分程で紹介して欲しいと言っていただけたので現在作成中です。 この学校は結構色々なことに積極的で、私にも色々声をかけてくださるのでとても動きやすいです。来月には給食で日本の料理を出して見たいので手伝って欲しいなど...もちろん日本のことだけではなく、普段の授業のサポート依頼もあります。
フィンランドには、「エスカリ」と言って、
小学校に通う1年前の子どもたちが集まるクラスがあります。
たいていは、幼稚園の中にあるクラスの一つか、小学校に併設されています。
日本で言うと、年長にあたるクラスです。
私はこの9月から、エスカリの子どもたちと一緒に生活しています。
折り紙を一緒にしたり、工作をしたり、鬼ごっこ、ボール遊びをしたりしてます。
こないだ、色鬼を伝授しました。
子どもたちはすごく喜んで遊んでました。
でも、フィンランドの子どもたちの服がカラフルすぎて、何色を言ってもすぐに
見つかってしまうので、「金色」と言ってみました。
しばらくして、「どこにもないんだけど。」と言われました。笑
欲的です。現地の先生いわく、別の作業として編み物に同時集中することで、授業そのものの集中力も上がるから良い効果だと言います。事実、彼女の編むスピードは、眼を見張る程早く、ここはフィンランドなのだということを改めて思い知ります。
のかを自覚していません。むしろ日本の東京のような大都会の最先端テクノロジーやそういった類いの利便性に興味を示しています。彼らも日本に関してそのようなことしか知りませんし、そのようなことを紹介すると喜びます。わたしは、いま持っているものが当たり前だと思っていては、いつかそれが崩れてしまうように感じてしまい、彼らに対し、いわゆる「もったいない」に似た感情を抱いています。フィンランドと正反対と行っても過言ではない日本社会の善し悪しを学ぶことを通して、便利さを追求することと住みやすい社会をつくることは違うということをなんとか伝えてみたいと思います。生徒たちがどのような意見を出すか楽しみです。結果はまた翌月のレポートにて報告させていただきます
フィンランドの夏を経験して面白かったのが、世界一コーヒーを飲む国だといわれているのに、アイスコーヒーがないことです。どんなに暑くてもホットコーヒーをひたすら飲んでいました。アイスコーヒーと言ってもわからない人が多いです。
3ヶ月経って気づいたことです。
・ゆっくり歩く(ヘルシンキの人は早いです)
・日曜日は街が静か
・車は横断歩道で必ず止まってくれる
・日焼け止め塗るけど、日傘とか長袖を着たりしない
・ハローキティーが人気
・鳥や植物に詳しい人が多い
・アイスクリームが好き
・コーヒーの粉がなくなると騒ぎが起こる
・(私の職場だけかもしれませんが)Facebookとか、携帯をよく見る
・フィンランド語はスラングが多い
まだまだありますが、フィンランドとっても楽しいです。
ちなみに、フィンランド人は日本人だと分かると、車とか電化製品とかを
思い浮かべる人が多いです。あと、アニメ。
セイナヨキでは同じ世代の日本人学生にも会うことができ、日本食などをつくってたまに息抜きをしています。また現地の方に誘っていただき伝統的なパンをつくったりと充実していました。
7月は完全にサマーホリデーに入ります。活動がないので積極的に動いて言語習得に励みたいと思います。
授業では、書道を4年生から6年生まで教えました。筆の使い方と止め、跳ね、払いを説明し、日本と同じように新聞紙で練習してから本番を書きました。名前を縦に書く時、母音を伸ばす記号「ー」が縦になるのが不思議だったようです。低学年は折り紙や、トトロの歌を一緒に歌いました。折り紙の時間では、色と形の名前を教えることが出来ました。
フィンランドはメインはフィンランド語ですが、4年生くらいになると英語もある程度は理解できます。それでも全部を英語で教えるのは難しかしく、教材を配布する場合はフィンランド語で用意した方がスムーズだと思います。
フィンランドの学校では時々先生や友だちが何かしらの理由でキャンディーを配ることがあったため、5月5日のこどもの日はキャンディーを配りました。日本はクリスマスは祝日ではないけれど、こどもの日は祝日だと言ったらとても驚いていました。祝祭日は宗教や歴史を説明するのにもとても良い機会だと思いました。
授業や、その他の時間をどのように使うか、あらかじめ学校と相談、もしくは提案をしておくと良いと思います。授業の用意は具体的な内容まではたくさんは必要ないと思いますが、どのようなトピックを扱うかと、大体の流れはいくつか用意しておくと良いと思います。特に滞在期間中の日本と滞在先の行事は大いに利用できます。
自分は日本文化を紹介する一方で、各校の特色ある授業を見学させていただき、とても勉強になる毎日でした。小学校ではサムライハットが大人気でした!!
こちらでは着々と夏が近づいていることを感じています。美しい自然をフィンランド人は思い切り楽しんでいるように思います。ホストファミリーにはミュージアムに連れて行っていただいたり、national parkに連れて行っていただいたりと、フィンランドについて本当にたくさんの情報をもらっています。6月は小学校はお休みなのでセイナヨキの大学で幾つかの活動に参加する予定です。
学校では玉子やひよこやうさぎの絵を描いたり、キリスト教の授業でも詳しくイースターの学習に取り組んでいました。
また学校の先生のお宅にお邪魔させていただき、イースターのときにだけ食べる食事をご馳走していただいたり、フィンランド特有のお祝いの仕方などを教えていただきました。
フィンランドで過ごして7ヶ月になりますが、こちらの人たちは何か行事がある度に一つひとつ丁寧に取り組む人が多いという印象です。もちろんすべての人ではなく、私の個人的な印象です。しかしこれまで過ごしてきた中でクリスマスや独立記念日などいくつか行事を経験してきましたが、行事の度に私の周りのフィンランドの方々は特有の飾りや食事などに取り組んでいました。
インターンをする中で小学校のことだけでなく現地のライフスタイルを知ることができるということはとても重要なポイントです。
現地の人たちのライフスタイルを知ることでさらに学校での子どもの様子や取り組む内容も理解できることが多くなったように感じます。
各クラスの先生方は生徒と保護者が一緒に学べる授業に取り組まれていました。内容は学年によって違い、組みひも作り、サッカーなどの体を動かすゲーム、グループで動物を調べるプロジェクト学習などがあり、各クラスの特徴が出ていてとても興味深い一日でした。
私も3年生と6年生のクラスで1時間日本文化を紹介する授業をさせてもらいました。
3年生のクラスでは授業参観がある週に相撲を紹介する授業をしていたので、その延長で授業のメインは紙相撲作りに取り組みました。事前の授業で相撲について知っている生徒は少なく、相撲の試合のYoutubeを見せたところ生徒たちは予想以上に盛り上がって試合を観戦していました。そこで授業参観でもYoutubeで相撲観戦を授業の一部に入れました。
授業参観の日は3年生のほとんどの保護者の方が参加されていました。相撲の試合をスクリーンで観戦しているときに、保護者の方は初め、"何が始まるのか?"と真剣な表情で見ていました。そして試合の盛り上がる所で、声を出して応援し始め、とても楽しんでいる様子でした。試合を見た感想の中に、ある生徒が「どちらが勝ったのか顔が似てるから分からない!」という感想があり試合を見る視点が面白いなと感じました。また、紙相撲では生徒と一緒に保護者の方も参加してクラス全体で盛り上がりながら紙相撲大会が出来ました。
6年生のクラスでは着物の紹介をしました。内容は浴衣を実際に着る体験と折り紙で着物のブックマーカー作りをしました。事前の授業で生徒には着物と浴衣についての概要を紹介していたので、丈の長い浴衣と約3mある帯をどのように着るのか真剣な表情で観察していました。保護者の方からは「浴衣は一人で着ることが出来るのか?」、「なぜ袖が長いのか」など素朴な疑問がたくさん出て、着物について興味を持ってもらうことが出来ました。また着物のブックマーカー作りでは初めて折り紙をする保護者の方を生徒が手助けをする場面があり、生徒と保護者が一緒に楽しめる時間になりました。
これまで保護者の方と話す機会はなかったので、学校で日頃何を生徒に教えているか保護者の方に知ってもらういい機会になりました。
ここ数週間で強く感じたことです。研修の場を広げること、自らの意見を提案すること、英語、現地語を話すこと、、、すべてにおいて「間違ったら、拒否されてしまったら...恥ずかしい、嫌だ」このネガティブ思考が自分の行動を制限していたことを痛感し、変わらなくては、せっかくの海外での研修のチャンスを「ただ過ごしただけ」で終わらせないようにしなくては、と格闘し始めてから数週間...ようやく1歩を踏み出せ、その後、驚くほどに事がどんどんと進んでいきました。
毎日学校は15時に終わるため、寝るまでにかなりの時間があります。
もちろん授業の準備もしますが、ずっとしているわけではありません。
私がしていることを少しご紹介。
①フィンランド語の勉強
日本から持ってきた文法本と辞書を使ってできるだけ毎日勉強しています。始めのころはなかなか単語が聞き取れずにかなりもやもやしていたのですが、最近語彙が増えて会話も所々理解できてきて、勉強もはかどるようになってきました。
いままで英語を勉強してきた方法と同じように、間違えたところをチェックしてやり直しをしています。英語圏の方には必要のないことかもしれないけど、言葉が通じるって嬉しいことだと日々実感しています。まずは読んだり書いたりできるように、それから話せるようになりたいと思います。文法本の他にはムーミンのアニメを朝に見るようにしています。さらに絵本を図書館で借りて読み始めました。
②編み物
今までほとんどやってこなかった編み物に挑戦しています。ホストマザーが手芸が趣味なこともあって時間があるときは編み進めています。フィンランドは例年4月になってもマイナスの気温が続くような冬の長い国なので、ウールものが欠かせません。今年は異常気象なのか、日本の冬くらいの気温なのですが...。物を手作りする楽しさを味わっています。
③ホストマザーとの会話
夕飯の時間が17時半~18時と早めなので、21時頃にデザートを出してくれるのですが、その時にホストマザーとよくお話しします。やはり学校ではフィンランド語の会話になかなか入れないので、ホストマザーとの会話は欠かせないものです。文化が全く異なるので何を話しても驚いてくれます。消費税のことから学校の課題まで。フィンランドの教育は世界中で注目されていますが、問題がないわけはありませんね。
2月は後半から少しずつクラスに参加させてもらいました。6年生の理科+社会のような授業で、ちょうどアジアの単科で日本を学ぶ時間があり、日本のことを紹介しました。教科書的なないようでは人口や、地理、またプラスαとして、新聞や雑誌、本を持っていって見せました。日本語にはひらがな、カタカナ、漢字があること、またこれらが混ざった文章はやはり面白いようです。ただ、授業に関しては娘のクラスを見ていても、フィンランドは登校時間が少ないため、それぞれの1時間ずつの内容が多い感じがします。各先生に声を掛けていますが、現段階で全時間を埋めるのは難しい雰囲気です。ここはもっと強気に出たいと思う気持ちもありますが。ただ、図工の時間で日本の絵を描いたり名前を書いたクラスもあるので、そういったことをこれから増やせていけたらと思います。
また日本のクラブも木曜日の1時間の設定で始めましたが、この1時間は授業のある生徒もいて、全員参加は不可能なため、現在別の時間を増やすことを検討し、各生徒に都合の良い時間を聞いて調整中です。いろいろやり始めてわかったことが多く、なかなか先手先手でいくもの難しいですが、少しでも多く、子どもたちに日本語と日本文化を増えれてもらえたらと思います。
内容に関して1つ、市販のひらがな、カタカナ表や、いただいた教材の文字一覧では、外国語表記に不十分なため、
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19910207001/t19910207001.html
こちらを参考に、自分で作成しました。また教材はやはり日本語と英語では不十分なため、フィンランド語を入れた教材を作成しています。
生活面では、アパートが便利な場所にあり、また用意して頂いた物で十分です。ただ、洗濯に関しては、アパートの共用のものであり、また1日2組限定なので、なかなか都合の良い時に毎回、とはいきません。ちょっとしたものは手荒い洗濯で済ませているため、そういった雑用では時間がかかっているかもしれません。それでも、乾燥しているフィンランド、夜洗えば翌日に乾くので、その点は助かっています。
娘の学習に関しては、もちろん理解は不十分ですが、先生のフォローが大きく、またクラスの子どもたちがとても助けてくれるので、授業に関しては心配していません。宿題に関してはもちろん、そこまでしっかりやる必要もないのかもしれませんが、1ヶ月頑張ってみて、少しずつ理解できることが増えてきました。算数は日本でやったことのある内容なので、言葉のパターンが分かってくると何とかなる状態になってきました。英語は3年生からスタートなので、半年分のハンディはありますが、読むことに関しては然程遅れを感じません。今は現在進行中の単科でいっぱいいっぱいですが、教材がとても良いので、少しずつ前の単科を遡って勉強する余裕がでてくれば、と思っています。ただ、毎日の宿題はそれなりに時間がかかるので、自宅で過ごす時間はほとんどが娘の宿題、家事、教材作成です。
生徒が作っていたのは、車、船、竹とんぼのようなものなど様々でした。その中で4年生の一つのグループがビー玉の通り道をパイプやダンボールを使って、上から下まで落とす装置を作っていました。
その様子を見たときにNHK教育テレビの「ピタゴラスイッチ」を思い出しました。こちらの学校では各教室にプロジェクターとネットがつながったパソコンがあるため先生方はよく授業中にGoogleやYouTubeを利用していて教材の一つになっています。そこで、YouTubeにあったピタゴラスイッチの動画を日本の文化紹介の授業中に見せることにしました。
生徒が作っている装置と同じ様なものを日本のテレビでは一つの番組の企画として流している、そして装置を作る研究グループがあることを伝えて動画を見せました。生徒は自分達と同じアイディアのものがテレビ番組になっていることに驚いていました。さらに番組の内容自体にとても興味を示し、15分くらいの動画を5分くらい見せたのですが「もっとみたい!」と言う生徒が多く授業の時間的に見せることが出来なかったので、動画のURLを生徒に伝え、家でも見れるようにしました。
約5ヶ月学校ですごしてきた中で、先生方の授業の取り組み方や内容、また生徒がどのように授業に取り組んでいるかを理解深めてきました。今回の取り組みは1ヶ月間くらいの時間では取り組めなかった内容だと思います。長く学校の中で過ごし生徒や先生の様子を観察し、教科内容や方法を知ることが出来ていたので、現地の授業と日本の授業をつなげることが出来たと思います。また生徒にとって日本の文化をより身近に感じられる授業にする為には、生徒が学んでいることと近い所のトピックを考えることも大事だとこの取り組みで学びました。
残りの3ヶ月では生徒や先生の様子をよく観察しながらフィンランドの教育についてさらに理解を深めて、それを日本文化紹介の授業につなげていきたいと思います。
ホストファミリーもホストスクールの先生たちも本当にあたたかく迎え入れてくれ、私はいつも笑顔で過ごすことができました。恵まれたことに、「辛い」「悲しい」と思うことは一度もありませんでした。唯一「悲しい」ことと言えば、帰国後ここに戻ってくる日が確定していないことくらいです。でも、いつの日か必ず、もう一度フィンランドを訪れたいと強く思っています。
一年間続けた「日記 兼 レポート」はかなりの容量になりました。日々の出来事を日記形式で写真ととも書き溜めたので、帰国後はこれを一つの本にまとめたいと思っています。成果を形に残すことができるということは達成感にも繋がるので、毎日コツコツと続けてきて良かったなと思っています。(これは、今後留学を予定している人たちに自信をもっておすすめします)
帰国に際し、たくさんの人たちから「ありがとう」という言葉をかけてもらいました。今の私の心は、一言では到底表すことのできない、充実した温かい気持ちで満ちています。
今後の私の目標は、この経験を活かして次のステップに進んでいくことです。まだまだ自分の可能性を信じているので、今後も学び続け、飛躍を目指していきたいと思います。それと同時に、自分を同じように学ぼうとしている人たちへのアドバイスや、子どもたちの可能性を広げるサポートに力を入れていきたいと思います。自分に何ができるのか、考え始めるとワクワクした気持ちになります。
最後になりますが、このような充実した経験ができたのはたくさんの人たちのサポートがあったからです。支えてくれた全ての人々に心から感謝し、同時に今後も成長し続けることを約束することで、少しずつ恩返しをしていけたらと思います。ありがとうございました。
土曜日曜は、家族とゆっくり過ごすのが基本のようです。比較的近くに住んでいる家族には会いに行ったり、向こうから会いに来たりします。兄弟姉妹の数が多いため、親戚がたくさんいて、複数の家族が集まることあっていろいろな年代の家族が揃い、とても賑やかです。家族の写真が家の至る所に飾ってあるのもなんだかほっこりします。
また、どこかに一緒に出かけるというのではなく家を訪れるというのもこちらの文化だと思います。これは家族に限らず、友人もよく招いてお茶をしたりしています。今月は私もいろいろな方のお家にお邪魔させてもらいましたが、どのお家でも素敵なおもてなしを受けています。
・スポーツに夢中
フィンランドの国技はアイスホッケーです。オリンピックということもあり、ほとんどの人が中継を見て応援していました。子どもたちもしっかり応援していたようです。こうやって一つのものを全員が応援しているということは素敵なことです。同時に、他の協議では日本の選手も同じくらい応援してくれました。
・フィンランドの教育法
たくさんの日本の学校との違いを毎日発見しています。ここでは先生が全員に向かって知識を教えるのと、生徒たち自身が調べて発表するのと半々くらい。みんなで一つのことをする行事などが多い集団主義の日本と比べるとそれぞれがそれぞれのペースに合わせて、興味のあることをするという個人主義だなと思います。少人数のクラスで一人一人に目が行き届くように助手の先生もたくさんいます。また、実生活に役立つ授業もたくさんあって、技術、家庭科、などは毎週行われていて、生徒たちの腕には驚かされるばかりです。この学校に毎日通っていて日本のいいところも真似したらいいんじゃないかというところもたくさん見つけては書き留めています。
・少しずつ単語をつなげて...
全く未知の言語を毎日聞いて、自分なりに勉強していると、少しずつ単語が聞こえてきます。自分から話すことはまだ少ししかできませんが、聞こえた単語をつなげて何を話しているか推測しています。よく聞く単語には日本語で言う「えーっと」のように意味を持たないものもあっておもしろいです。
このように6年生クラスで継続的に授業をさせてもらっていることは文化を伝える為にはとても重要なことだと感じるようになりました。それは、他学年のクラスでも先生方の要望で何度か授業をさせてもらっています。しかし一度きりでその後授業をしていないクラスもあります。一度だけでも授業をさせてもらったことは大変ありがたいことです。それでも一度だけの内容ではまだまだ日本文化や異文化を経験する面白さを伝えることは出来ていません。6年生のように週一もしくは2週に一回でも継続的に授業をさせてもらうためにどうしたらいいかを考えました。これまで先生方には「今度授業お願いできる?」と声をかけてもらっていた時にだけ授業をしていましたが、自分から授業をさせて欲しいと提案していませんでした。そこで自分から授業をさせてもらいたいと提案する為に、私が何を教えることが出来るのかをテーマごとにリストアップして先生方一人ひとりに見せて、相談をさせてもらいました。すると先生方はとても真剣に話を聞いてくださり、またとても興味を示してくださりました。生徒にどのテーマを知りたいか聞いてく
ださった先生や毎週の授業日を決めてくださった先生など先生方はとても協力的に動いてくださり、一月の中旬から少しずつ授業をする回数が増えてきました。
これまでの3ヶ月受身ですごし、また先生方のとても協力的な部分に甘えていたなと反省しています。しかし自ら授業をさせてもらうための提案をしたことはこれまでの反省点を一つだけでも改善できたのではないかと思います。残りの3ヶ月半の間で継続的に授業が出来るように自ら動いて先生方とコンタクトを積極的に取っていきたいです。そのときに通常の授業でも忙しい中に日本文化を紹介する授業を組んで、協力してくださる先生方へ感謝の気持ちを忘れずに取り組むようにしたいです。
また、様々な場所を訪れると、そこに新たな出会いがあります。そこで「教師」「学生」「父親・母親」「祖父・祖母」「現地人」「外国人」など様々な立場の人たちと話をすることで、それぞれの視点から考える「教育」について意見を聞くことが非常に楽しいです。自分とは異なる経験をしてきた人たちの話しを聞くことは大変興味深く、貴重な体験をすることができています。
時間がいくらあっても足りないと感じる日々ですが、帰国の日は着々と近づいてきています。一つひとつの出会いを大切にし、また、支えてくれている人たちへの感謝の気持ちを忘れずに、最後まで充実した生活を続けていきたいと思います。
授業は、小中高と徐々に難しくなってきましたが、伝統文化以外に日本の中高生に人気のあるものや、私たちの普段の生活を話すことも彼らには面白いのだと気づき、「日本の学生の1日」をスライドショーにしたり、プリクラやカラオケの話をしたりしています。制服やランドセルの写真には反応が濃く、制服はあったほうがいいかなどディスカッションに発展させたりもしました。また、中高生の英語の授業では、日本の高校生に英語で手紙を書く活動や、旅行プランナーになったつもりで日本の観光地についてグループ発表を行いました。私の授業を通して彼らが新しい知識を身に付け、日本に限らず、海外に興味を持つきっかけとなれば良いと思っています。
私の学校は小学校から中学校までの子どもたちがいるのですが、まずはすべてのクラスを訪れました。調理実習やHandcraft、体育などは子どもたちと一緒に参加させてもらっています。
こちらでは英語を使っていますが、中学生は喋るのは難しくても言ったことは理解してくれるし、先生方に間に入ってもらって、小さい子たちともコミュニケーションを図っています。しかしやはり言語の壁がまだまだあって先生や子どもたちが何を話しているのかわからなくて少しつらいですが、帰宅後はフィンランド語を勉強しています。発音はしやすい言語なので、覚えた単語は口に出すようにしています。
すでにいくつかのクラスで、折り紙を使って立方体を作りました。最初は苦戦している子どもたちも彼ら同士で助け合って、完成させることができています。すれ違うと「Mariko!]と言ってくれたり、絵を描いてくれたり、子どもたちからもアプローチしててくれてとても嬉しいです。
来月からは授業の参加に加えて、「日本クラブ」なるものを週一回放課後に開催して日本に興味のある子どもたちにさらに日本のことを知ってもらう機会を設けてもらえることになりました。もともと日本との交流はある学校なので、興味のある子が多いと思います。ここにきて、フィンランドと日本の相違点をたくさん発見したので、それを少しでも共有できたらと思います。
フィンランドは自分の時間もしっかり大切にする国。夜は自分の、そして家族との時間です。日本の喧騒から少し離れて考える時間も増えました。何かこれを機に新しいことにもチャレンジしてみようと思います!
研修校では学期の最終日にクリスマス発表会が行われました。発表会では主にキリストの誕生にまつわる劇やポエムの発表やバンド演奏と歌などの内容です。フィンランドの学校ではキリスト教学が教科の一つになっているため、子どもたちもクリスマスの意味を理解した上でクリスマス発表会を行っているようです。なぜクリスマスに御祝いをするのか、発表会をするのか、行事を行う理由を知った上で活動に取り組む姿勢は大切だと気付きました。また、日本の小学校では一つの宗教を深く学ぶことはないので、日本とフィンランドの教育の大きな違いでとても興味深いことの一つです。
6年生のクラスでは日本のきよしこの夜の歌詞を覚えて暗唱することに挑戦しました。覚える期間は2週間しかなく、子どもたちにとって初めて聞く日本語のフレーズを覚えることはとても難しい取り組みでした。さらに一斉に声を合わせる、一斉に立つなど日本では当たり前のように伝えられることも、普段から一斉に動くことに慣れていない子どもたちに伝えることはとても難しい場面もありました。しかし、日本の文化にみんなで息を合わせて行動することも文化の一つということを理解してもらい、子どもたちは前日まで一生懸命練習に取り組みました。本番では沢山の生徒や保護者、地域の方々を前にして緊張した表情でしたが、上手に暗唱するだけでなく、声を合わせることや一斉に立つなどこれまで練習してきたことをしっかりと、たくさんの観客の前で発表する事ができました。
この発表会の取り組みは私にとって課題を知るきっかけとなりました。それは「日本で教えていたときの様な取り組みを研修先で同じように取り組んでも、理解してもらえないことがある」ということです。日本の文化を一方的に伝えるのではなく、まずは私自身がフィンランドの文化の理解を深め、それぞれの文化を重ね合わせながら、取り組む内容や方法を工夫し、子どもたちに日本の文化を伝えていきたいと思います。
このような楽しい時間の中で、「宗教」を強く感じた1ヵ月でもありました。私は、日本ではほとんど宗教について考える機会がなく、ほとんど全ての興味のあることに参加していました。しかし、「宗教上」ダンスをしてはいけない、パーティーに参加できない、などの話を聞き、自分の無知を痛感し、「宗教」についてもっと理解をしなければならないと感じました。
事前のパーティーではお友達とシャンパンを片手に朝まで踊って楽しむ!!当日は暖炉を囲んで家族としっとりと過ごす...。どちらも特別な思い出です。
12月に入ってから、各家(これまでのホストファミリーや学校の先生方、友達)のクリスマスパーティーに招待され、ゆっくり4月からのことを話す時間があったのですが、そこで私の英語力の上達を褒められる機会が多くありました。自分自身では感じていることではなかったので驚きましたが、複数の人たちからの言葉にとても嬉しくなりました。
ただ、特別英語の勉強を熱心にしているわけではないので、自身でその理由を考えてみました。「他の日本人とは違う」という言葉もあったので、何が違うのかも考えてみました。
私の結論は、「答えを出すスピード(判断力・決断力)が一つのポイント」ということです。
これは私が教師として子どもたちにぜひ身につけて欲しいと願っている力の一つですが、判断力・決断力の不足は、成長の機会を逃してしまうのではないかと考えました。
時々出会う日本人旅行者などの様子を見ていると、相手からの投げかけに(問い)に対して「どちらでも良い」「ひとりでは決められない」「分からない」という答えでモゴモゴしている人が多いような気がします。
これは私の性格ですが、基本的に相手からの投げかけに対してスパッと答えを出すので、その結果会話がスムーズに進行し、自然と会話量も増えていったのではないか。そしてこれが上達のポイントだったのではないか、と考えました。
(ふと、「Noと言えない日本人という言葉があったな...」ということも思い出しました。)
「空気を読む」「周りの様子に気を配ることができる」という習慣があるのは日本人の誇らしい部分でもあると思いますが、時にその度が過ぎるのは、自分の成長のチャンスを逃してしまうのではないかと思います。
さて、私は会話力の上達を褒められましたが、「英語で文を読むこと、書くこと」の上達はまだまだだと感じています。今後はそちらにも意識を向けつつ、それでもやはり今の「英語を使って実際にコミュニケーションをとることができる」という貴重な環境・時間を楽しんでいきたいと思います。
フィンランドで支えてくれている心優しい人々はもちろん、日本から「待っているからね」と応援してくれている人たちへの感謝を忘れずに、2014年も楽しみます。
それはホストマザーは毎日私の生活面をケアしてくださり、小学校でのインターンシップのことをとても理解してくださっています。また近所の方や友人を紹介してくださり、フィンランドでの交友関係を広げることも手助けしていただいています。この2ヶ月は助けてもらってばかりだったので、これから少しずつ私もファミリーの手助けができるように、食事や掃除など出来ることから今まで以上に率先して気付けるようにしたいです。
インターンの研修校にもとても恵まれていると毎日感じます。それは学校の先生や子どもたちが日本文化に対しての興味が強く、積極的に私とコンタクトを取ってくれます。おかげで全学年のクラスで研修させてもらうことが出来ています。最近は日本語で挨拶をしてくれる子どもたちがいて、日本への興味が高まってきているのかなと思うことがありました。
また、クリスマスシーズンを迎えた時期なので学校の中でも様々なクリスマスの行事が取り組まれています。来週の土曜日にはクリスマス発表会があり、6年生のクラスでは日本語の「きよしこの夜」をポエムとして暗唱して発表することになりました。とてもいい機会を与えてもらってとても楽しみです。子どもたちは初めての日本語に初めは恥ずかしがりながら練習していましたが、少しずつ覚えてくれてきています。その練習している姿を見ると、子どもたちが一生懸命日本語を勉強してくれている分、私も子どもたちが話すフィンランド語を真剣に勉強して、子どもたちとの交流を深めることが出来るようにしたいと思うようになりました。
あと2週間ほどで冬休み入ります。それまで子どもたちや先生方との交流を大切にしながら、少しずつでも信頼関係を築いていきたいと思います。
東京出身の私にとって、キラキラとしたイルミネーションは毎年の光景ではありますが、フィンランドでは日照時間が短いことが加担して、真っ暗な景色がデコレーションの美しさをより盛り上げています。また、「一人あたりのキャンドル消費量(使用量)が世界一」と言われている国ですので、キャンドルの灯火も多くの場所で目にすることができます。人工的な光とは異なる、温かみのある光にすっかり魅了されているところです。
さて、今回はこれから海外に留学する方へ一つアドバイスができればと思います。
それは、「まずは何事も積極的にチャレンジしてみること」です。当たり前のことかもしれませんが、私はこの「基本」のおかがでたくさんのチャンスを得ることができました。
日本文化(日本語)の授業依頼はもちろん、通常の授業のサポート、放課後や週末に映画やコンサート、パーティーへの招待など、本当に多くの誘いを受けることができています。それも特定の限られた人だけではなく、研修先の先生方やホストファミリー、友人、さらには「友人の友人」からも声をかけてもらっています。
これは、私が「とても温かい心遣いのできる、素敵な人たちに囲まれて生活することができている」という恵まれた環境にいることも理由の一つですが、先日ふと「私はたくさんのイベントに参加することができて幸せだ」という話をしたところ、「それは、あなたが『どんなことでも、なんでもやってみよう!!』という姿勢だからよ。私たちも誘いやすいもの」という返事が返ってきました。
これが、私がこれから留学をされる方に伝えたいエピソードです。
積極的な方、控えめな方、それぞれ性格は異なると思いますが、誘う側として考えたら「あの人なら楽しく参加してくれるかも」と思える人に声をかけることが多いと思います。
嫌なこと、辛いことを無理して続けることはありませんが、「まずは一度チャレンジしてみる」ということは、大切なことだと思います。(その挑戦の中で新しい出会いを得る機会も多くありました。)
当たり前のことですが、改めてお伝えできたらと思います。
これからも一つひとつの出会いに感謝の気持ちを忘れずに、残りの数カ月もまだまだ楽しみたいと思います。
研修校は小さい小学校で、一クラス23人ほどで一学年一クラスずつの規模です。研修中は基本的に6年生のクラスにいるのですが、どの先生方もとても好意的でいつでも授業見学に来てくださいとおっしゃってくださったので、一週間のスケジュールを自分で組み、全クラスに行ける様にしています。
また、6年生、5年生、4年生、のクラスでは日本の文化や言葉を伝える授業を研修1週目からさせていただいています。子どもたちは日本のことを詳しく知らず、インターネットやテレビからの少ない情報しか持っていないので、日本の地図を見せたり、日本語を書くだけで、フィンランドと日本の文化の違いの面白さを感じてくれています。そして、日本文化に対して興味を持ってくれているようです。子どもたちの興味や関心をもっと高め、そして日本のことを近く感じてくれるように、授業を考えていきたいと思います。
来週末になるとフィンランドに来て1ヶ月が経つことになります。この1ヶ月はとても早く感じています。研修中あのときああすればよかった、聞いとけばよかったと思うことが多々出てきています。反省を次の活動に活かしながら、あと7ヶ月しかないと思って、一日ずつ目標を持って、研修に取り組んでいきます。
しかし生活が単調化しているわけではなく、日常の生活が落ち着いている分、研修先となっている学校だけではなく近隣の中学校や高校へ行く機会も作ってもらう様にしました。校長先生や良くしてくれる先生に話をし、連絡先を聞いて、積極的に新しいことに取り組む努力を続けています。自分から動けば動くほど周りの人たちが助けてくれるので、いつも予定がぎっしりです。とてもありがたいことだと思っています。
最近は子供たちの名前も大分覚えてきて、コミュニケーションに深みが増してきた様にも思います。小さな学年の子供たちとフィンランド語で会話をすることはまだまだ難しいですが、やはり人と人。言葉が通じなくても信頼関係が築けていることには自信があります。昨日の出来事や好きなものについて嬉しそうに話してくれる笑顔からは、本当にたくさんのパワーをもらうことができて幸せです。
残りも4カ月弱。当たり前の日常をもう一度見直して、貴重な時間を楽しみたいと思います。
今は、日本に興味をもってくれている生徒となにかできないか考えているところです。
学校はPreschoolから高校まで同じ建物にあり、低学年から1週間毎に1クラスずつ教えていくという形で、1日に2~3時間日本文化の授業を行います。他の時間は、そのクラスの他の授業や中学校や高校の授業に参加したり、日本で英語教員をしているということもあって英語の授業を手伝ったりしています。1学年1クラス20人程度の規模で、下級生にはアシスタントティーチャーもついているので、日本の職場(高校)と比べるととても手厚いと感じます。
授業は、伝統文化はもちろん、今の日本も伝えられるように心がけています。どこの教室もPCとプロジェクターがあるので、スライド写真を多く使用しています。日本の折り紙、書道、箸の使い方、浴衣の授業は、今の所どこのクラスでも人気で興味を持って取り組んでいました。食文化の授業では、海外にはなかなかない「お弁当」を紹介し、自分たちの理想のお弁当の絵を描いたりもしました。
今後の課題は、学年によって授業のレベルを考慮することと、自分自身のフィンランド語の向上です。レベルについては、学年が1つ違うだけでも、できることが随分変わってくるなと感じており、1年生には折り紙やクラフトを多くしたり、3年生には発表学習をいれたりと工夫はしていますが、普段高校生と接していた私には小中学生のレベルの設定に苦戦中です。年齢が上がるにつれて知的好奇心も深くなり、できることも増えるので今後も楽しみです。フィンランド語は、もっと話すことができれば、さらに生徒たちとコミュニケーションがとれるし授業もスムーズに行くのに・・・と毎日もどかしい気持ちでいます。先生方とは英語で話していますが、生徒とはつたないフィンランド語とジェスチャーでの会話です。早く多くの単語を覚えて使いこなせるようになりたいです。
9月に後半に雪が少し降り、これからどんどん気温が下がるかと思うと心配ですが、それもフィンランドの名物のひとつと思い、楽しみつつ頑張ります。
日本での勤務校の先生からメ-ルが届き、知り合いの大学院生が修論作成のためにフィンランドの高校のある教科の先生方対象にアンケ-トをとりたがっているので、協力してやってほしいとのことでした。さっそく英文のアンケ-ト用紙を送ってもらい、訪問校も含めて何人かのその教科の先生方にお願いしたのですが、なるべく早く返事を送りますねという返事は来るのにアンケートの返答は一向に届きません。顔を合わせたときは愛想が良いのにと、教師不信に陥りかけていたのですが、ある日その理由に気がつきました。アンケートは英語の記述式で、あるていどの量の英文を書く必要があり、英語で回答する負担が大きかったのだと思います。はっきりと断りづらいので、出会った時はいつもより愛想よくしてたようです。この辺は日本人と似ているのかなと思いました。
フィンランドの先生方の中には英語を上手に使う方も多く、フィンランド語のできない私と普段は英語でしゃべっていますが、そういえば時々へんな英語を使っていることがありました。こちらではそういう言い方をするのかなと思っていましたが、英語で会議をしていたとき、記録をとっている先生から、わりと簡単な単語のスペルを聞かれたり、この話は英語でどうまとめたらいいのか尋ねられたりして気づきました。先生方は自分が話したいことのうち、自分が英語で言える範囲のことだけを話していたようです。私はその英語しか聞いていないので、当然それが彼らが言いたいことのすべてだろうと思っていました。ヨーロッパ人で英語の話せる人は英語で意思疎通ができるだろうと思っていたのが誤りで、とにかく自分の方が喋るという彼ら特有のメンタリティーが英語をどんどん喋らせていたようです。まずは相手の言うことをよく聞いてから自分の意見を言うという、日本人のメンタリティ-とは正反対です。
ついでに。。。
私が教員用のカフェテリアでコ-ヒ-を飲んでいると、フィンランドのコ-ヒ-はおいしいですか?とよく訊かれました。日本でもフィンランドでもコ-ヒ-豆は栽培できないし、いづれにせよ南米かアフリカからの輸入品だろうから、フィンランドのコ-ヒ-って何のことだろうと思っていました。言いたかったのは、フィンランドのコ-ヒ-は日本のお茶とくらべてどうですか?ということだったようです。日本人はお茶を飲み、コ-ヒ-は飲まないと思っていたようです。後日、私が自分でコ-ヒ-をいれて飲んでいるのを見てびっくりしたと打ち明けられました。
【教師としての経験をもとに、日本との比較をしながら学ぶことができる】
【学び続けることの大切さを改めて感じることができる】
ということは、一度社会人を経験した後の方が強く感じることができるものだと思います。私は今、その経験ができてとても幸せです。
日本の社会はとても忙しく、なかなか休みを取って学ぶということが難しい環境にいる人が多いように思いますが、私は自身の経験から、ぜひもっとたくさんの人にこのようなチャンスが与えられることを望みます。
長い人生で考えた時の「たった1年」が、「人生にとても大きな影響を与える1年」になることもあると、日本に帰ったらぜひたくさんの仲間や子供たちに伝えたいと思います。
私はヘルシンキ大学の講義を受けたり、幼稚園の見学に行ったりして過ごしています。「今あるチャンスを最大限生かそう!!学べることはどんどん学ぼう!!」と、何事も積極的にチャレンジ中です。もちろんヨーロッパ旅行をしたり友達とパーティーをしたり...と、生活も充実させています。
最近思うことは【同じ出来ごとでも、考え方によって相手の印象も結果も、大きく変わってくる】ということです。これは日本にいる時から感じることではありましたが、同じ境遇にいても受け取る人の考え方によってその後が大きく変わっていくということを、様々な場面で感じるようになりました。
フィンランドにいる日本人と話す機会がありますが、中には大変な経験をしている人もいるようです。日本人同士で行動することばかりだという人の話も聞きました。
そこで「私は現地の生活に溶け込むことができ、親切な人たちに囲まれ、恵まれた環境にいるからラッキーだ」という話を現地の友達にすると「それは、あなただからよ。その環境を作ったのも、あなたよ。」と言われました。ハッとする言葉でした。
今の思いやこの経験を、今後の人生に活かしていきたいと思います。そして、日本で待っていてくれる子どもたちに伝えたいと思います。
【たくさんの素敵な出会い】、【このチャンスにめぐり合えたこと】、【日本で応援して待っていてくれる人たち】への感謝の気持ちを忘れずに、これからもフィンランドでの生活を楽しみます。
gr3,4で習字の授業をしました。日本語には3種類の文字があること、習字で大切なことや注意点を説明し実演を始めると、子ども達は「書く時の力は、どれくらいがいいの?」「かっこいい!」と興味を持ってくれました。生徒一人一人の名前を漢字で書く授業内容にしたので、お手本作りにはかなりの時間を使いましたが、授業後に机の扉の部分にお手本や自分が書いた名前を貼っている子が何人かいたり、ノート1ページを使って漢字で自分の名前を書いている姿もあり嬉しかったです。先生にも好評で、「私の名前も漢字にしてくれる?」とリクエストがありました。筆ペンを持って行ったので、文字の強弱は出しにくかったですが、こぼしたり汚したりしにくいので使いやすかったです。
<昔話の紹介>
「花さか爺さん」の話をパネルシアターで紹介しました。日本語、英語で物語を読んだ後、7グループを作り紙芝居を作りました。どの場面を描くか決める時、女の子グループは、桜や小判が出てくる場面、男の子はガラクタが出て来たり、お殿様(侍の大将と説明)が出てくる場面を選んでいたのが面白かったです。
女の子はパネルシアターに興味を持ち、私が自分で作ったと言うと、とても感動していました。男の子は、パネルシアターのお爺さんの表情が面白かったようです。絵を描く時も、パネルのお爺さんとそっくりな絵を描いていました。最後に代表2人に読んでもらいました。意地悪なお爺さんの時に、ガラクタばかり出てくる場面は、最後までウケてました。
<研修の終了>
8週間の研修期間で、今の自分に出来ることを精一杯やりました。最後が近くなったある日、gr2の男の子が帰る間際に「かぶとを教えてくれてありがとう!」と笑顔と共に言ってくれました。その子は普段クールな表情だったので、私の授業には興味なさそうだな、と思っていました。なので初めて私の目を見て笑顔を見せてくれたことに一層感激しました。
フィンランドでの生活リズムも落ち着き、余裕を持って生活が出来るようになってきました。知り合いの輪もますます広がり、長いと思っていた夏休みの予定も、すっかり埋まってしみました。旅行をしたり、パーティーに招待してもらったり、ヘルシンキ大学で英語の勉強をしたり...。どれも楽しみです。
学校では子どもたちがすっかり私に慣れてきて、先日は子どもたちのお寿司パーティに招待されて、一緒にトトロの映画を見たり折り紙で遊んだりする時間も過ごしました。学校行事の遠足やパーティに声をかけていただくことも多く、先生方の親切なお心遣いに感謝する毎日です。
早いもので、最初のホームステイ2カ月の期限が迫っており、来週には引っ越しです。寂しい気持ちもありますが、「夏休みはコテージに一緒に行きましょう」「時々、夕飯を食べにいらっしゃい」「クリスマスパーティの時は、またメッセージ送るからね!!」と声をかけてもらっているので、これからもこの出会いを大切に関係を続けていけたらと思います。
日本にいる友人や家族、そして同僚や教え子、さらには保護者の方々も私のことを気にかけ、連絡をくださることは、とてもありがたいことだと思っています。待っていてくれる人がいる、帰る場所があるということも、幸せなことだと感じています。
出会いとチャンスに感謝し、これからも充実した日々を過ごしていきたいと思います。
ただ、小学校や高校などに行く場合は少し気をつけて準備をしっかりしてから行ったほうがよいと思います。
普段通っている学校ではないところに行って授業をするのですが、授業内容について先方からの要望が不明瞭だったり、現地でパソコンが使えるか(僕は普段USBやパソコンなど使ってスクリーンにうつす場合が多いのですが)、パソコンが教室になかったり、いってみたら100人規模の教室で授業を行うことになっていたり、マイクが使えなかったりと、USBを読み込んでくれなかったりと、行ってみないと状況がわからず、その場で対応を即考えなければならない場合がありました。
その時は急遽データは使わず自分の言葉のみで授業を進めることもありましたが、はじめて会う生徒たちとその状況で授業をうまく進めていくのはなかなか大変です。
海外なので、状況に絶対はありえませんが、まだ出発前の方は、どんな状況でもこの授業案ならデータが使えなくてもアレンジして使える、とか、授業時間を40分で調節したり、50分で調節したりできる、というものを2つくらい用意されてから出発されたらよろしいのではないかと思います。
僕は準備しきれていなかったので、前夜に徹夜するはめになったりしていますので。
ホストスクールでは、1学年を1週間ずつ順番に見学させてもらっています。自身の経験と比較をしながら、良いアイディアをたくさん吸収することができており、ここに来て良かったと感じる日々です。おりがみを教えたりもしましたが、本格的に授業をするのは来年度以降にしました。今は、感じたことを先生方に質問したり、互いの国の教育法や指導法について話し合う時間を大切にしています。夏休みにはヘルシンキ大学で開かれるフィンランド語講座に参加する予定なので、秋以降は今よりフィンランド語を上達させ、スムーズに授業ができればと思っているところです。
放課後や休日は、ホストファミリーとジムに行ったり、買い物に行ったり、忙しくも充実した日々を過ごしています。来週は先生方が開いてくださるパーティーに参加したり、ホストファミリーと一緒に行くストックホルムへの旅行も控えているので、わくわくしています。
日本で応援してくれている家族・友人・同僚ともSkypeやLINEでまめに連絡がとれているので安心です。チャンスと出会い、応援してくれている人たちへの感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張りたいと思います。
生徒も教員も、「自由」。でも大切なこと≪相手の気持ちを尊重し、自分の意思も持つこと≫は守られているのが、研修校の第一印象です。
してはいけないことをルールで縛るのではないので、中には隠れて授業中にお菓子を食べたり(ガムを噛んでいるのはok、さすがキシリトールの国です)、携帯をいじっていたりする生徒もいます。そんな時、教員は静かに諭すように声をかけ、それでも止めない生徒にはじっと見つめます。
「今これはいけないんだな。相手と向き合わなきゃいけないんだな。」というのが、自然に身に付いていくように思います。サポーター制度(教員を目指す若者が教員のサポートで授業に参加する)も充実しており、気になる生徒の横にはサポーターがさりげなくついています。
朝のホームルームは週1回。もし、クラスの数人で申し合わせたエスケープなどがあった場合は、他の授業中でも担任が入っていき、注意を促します。それも、静かに、諭すように。。
子供の家庭環境は様々ですが、温かく包み込む雰囲気の学校なので、思い切った非行に走る生徒はいません。また、そういうことに意味を見出す雰囲気がありません。
1時間30分で巻きずしを作るのは難しい部分もありましたが、初回うまくいかなかった部分を次の授業で修正して時間内に作ることができました。
日本料理を紹介するのは今回で2回目でしたが、なかなか初回は思ったとおりにいかないことが多く、生徒の様子を見て学ぶことがたくさんあります。
良くなかったところを修正すると、出来上がる料理も前より美味しくなるということも授業を行ったことで学べたことだと思います。
日本は人気があるようで、学校に日本人がやって来たというニュースが生徒の間に広まり、まだ紹介されていないうちから、生徒のほうから話しかけてきました。マンガ・アニメに興味があり、6月に市内で行われるお祭りでコスプレするそうです。
日曜日には、凍った湖の上で散歩、クロスカントリー・スキー、パラ・スノーボード・セーリング、氷に穴をあけて魚釣りなどを楽しんている人々を見かけました。
ついにこの日を迎えてしまいました。学校の最後の日もなかなか最後っていう実感はありませんでした。最後はよくお世話になった特別学級のクラスにお邪魔して、一緒に歌をうたったりしました。その後、その週に行われたスキーの試合の表彰式がありました。金・銀・銅とメダルをランチホールで渡すということで皆集まりました。私もメダルを子供たちにかけてあげました。そして、英語の先生が出てきて私が今日で最後であるということを言ってくれて、生徒からプレゼントとカードをもらいました。泣かないようにしようと思ってたんですが、やっぱり泣いてしまいました。一言御礼を言いました。その後も子供たちが個別に手紙などを渡しに来てくれたりと、1日中泣きっぱなしでした。最後も外に出て子供たちと休み時間を一緒に過ごしました。授業が終わってからも会いに来てくれて、一緒い写真を撮ったりなかなかわかれることができませんでした。また会いにくるよと約束しました。本当に子供たちと過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。
そしてスカウトのキャンプにも参加させていただきました。子供たちと一緒にいろいろ作ったり、サウナの後に湖に飛び込んでみたり良い体験ができました。そこでも皆でお箸を使ってご飯を食べたり、折り紙を教えました。スカウトには同じ学校の生徒も何人かいて、折り紙クラブの生徒もいました。その子の両親もスカウトなのでキャンプに来ていて、そのときにその子の両親だと知りました。お父さんが、折り紙クラブで折った折り紙をちゃんと保管してるよとか、その子が折り紙を折りたくて探したけどなかったと聞いたので、持ってきていた折り紙をあげました。これからも折り紙に興味を持ってくれてたらいいなと思いました。
ホストファミリーは日本の旗を描いたとても大きなケーキを作ってくれました。とても美味しかったです。私がムーミンが好きだとずっと言っていたので、最後にいろんな人がムーミンのググッズをくれました。
いろんな人と出会いいろんな体験ができ、本当に参加して良かったなと思っています。
折り紙クラブではハート型の箱を作って、出来上がってからそこに日本のチョコレートを入れてあげました。日本のバレンタインの習慣も説明しました。
それからフィンランドではスキー休みがあり、南・北・真ん中で1週間ずつ休みがずれています。私は南に住んでるので2月の最後の週がお休みでした。その前の週は前にお世話になった学校に再び1週間行って来ました。皆私の名前を覚えてくれてました。そしてスポーツウィークということで毎日違うウィンタースポーツを楽しむことができました。スキーやスケート、スノーシューズを履いて歩いたりとても楽しかったです。そして最後の日の全校集会で全員に鶴をあげました。千羽鶴用の和紙で折ったので、先生方も幼稚園の子もみんな小さくてかわいいととても喜んでくれました。休んでる子にもあげたいから余分にほしいと先生に言われ、また生徒からは休んでる妹にもあげたいから頂戴と言われました。そして6年生が最後にハグしていい?と英語で言ってくれました。短い期間でしたがとても素敵な子供たちと先生に出会えてよかったなと思いました。
中にはフィンランド語しかできない生徒もいるため、メッセージをフィンランド語で返すのが大変ですが、結果生徒との距離を縮めることもできるし、何より語学の勉強になります。若者言葉や、現地のおすすめの場所なども教えてくれますよ。
先生をされている方は、フェイスブックに限らず、言葉でわからないことがあれば、生徒に聞いちゃうのが一番有効な手段かもしれませんね。
もちろん、現地の先生方にはリクエストを受けて良いか確認の上で、進めています。
僕の場合6ヶ月という短期なので、認められているのかなというところです。日本で自分が先生をしていたら、同じことをやるのはまず無理でしょうが、、
自分から生徒には申請しない、など一部の制約は自分にも設けた上で活用していますが、1つの有効な手段だと思います。
なお、小・中学校だと難しいかもしれませんが、大学生レベルになると希に日本語が堪能な子がいたりします。
そういう子を見つけて、フィンランド語と日本語を教えあう形が取れたら、語学向上に力になると思いますよ。
初回はどのように生徒に伝えて良いのか分からず失敗してしまいましたが、
うまくいかなかったところを修正して2回目以降は生徒からおいしいという言葉をもらうことが出来ました。
当日渡されたレシピが英語で書いてあり、作る料理はなじみのない日本料理、私はフィンランド語を話すことができないので、生徒にとっては大変な調理実習だったと思います。
料理なんだから何語で話そうと伝わるはずだと思い、生徒には分からないことがあったら英語でもフィンランド語でも構わないので聞いて欲しいと伝えました。
この授業を通じて、相手の気持ちを考えてから教える・伝える大切さを学べたと思います。
藍は、つい顔をしかめてしまうほど匂いが強く、嗅覚を刺激します。また、染め上がりは緑色ですが、空気にさらすと美しい藍色に変化します。布を輪ゴムで縛ったり、小さな木の板で挟んだりと、どんな仕上がりになるのか、染めてみないと分からない。そんな楽しみももあります。
このような体験をしたことを、彼らが大人になってから、一度でも思い出してくれたら嬉しいと思っています。
染色液は、Amazon.comで見つけた下記の藍染めキットを使用しました。使い勝手がよく、1箱分が10人程度のクラスには適量です。
紺屋藍 http://www.seiwa-net.jp/product/konya_i/index.html
日本で録画したNHKの「トラッドジャパン」を見てもらってから「日本を教える」に載ってた力士を使って遊びました。低学年はこのようにしましたが、高学年だと簡単すぎると思い折り紙で力士を作りました。その後時間があったので1番強いのはだれか決めることに!この試合が思いのほか盛り上がり、最後に残った2人をクラス全員で応援してました。勝った子にはシールをあげました。
音楽の授業は日本の楽器や歌手、歌を紹介しました。楽器など持ってないし弾けないので、You tubeを使って見てもらいました。最後は一緒に「糸」をうたいました。歌詞をフィンランド語に訳したので意味をわかってもらいながら、日本語を一緒に読んで音楽に合わせてうたいました。短時間でしたが皆上手にうたってくれました。
それから1週間だけ違う学校へ行ってきました。今までとは違い各学年1クラスだけのカントリーサイドの小さな学校でした。他の学校とは少し雰囲気が違うなと感じました。最初の日に日本語を教えたクラスで、先生が今日から1週間は日本語を話すようにと言ったので、皆「こんにちは」と毎回挨拶してくれました。まだ教えてないクラスの1年生たちまで「こんにちは」と言いに来てくれたのでびっくりしました。5,6年生は英語でいろいろ質問してくれて、私が英語で言ったこともほぼ理解していました。普通の会話も英語だけで十分でした。3,4年生で日本に興味ある子は簡単な日本語を話してくれたし、英語で質問もしてくれました。6年生に折り紙でカエルを教えた時も、2回ほど教えただけでもう自分たちで作れるようになってて、1㎝ほどのカエルを作って小さい方がよく飛ぶよと教えてくれました。
1週間だけだったんですが、最後の日にホールに集まった際に前に呼ばれプレゼントをいただきました。そしてみんなで一斉に「さようなら」と言ってくれました。びっくりと感動でした。いつでも来ていいよと言われたので、また1週間お邪魔する予定です。
自分自身日本語クラスの初授業もデビュー。
最初なので、いろいろできなくて当然なのですが、やはり、現地の子供たちが話す言語はしゃべれた方がよいと感じました。フィンランドはフィンランド語。
もちろん、現地の言葉がしゃべれなくても、授業はできます。僕は英語を中心に進めているので。
ただ、しゃべれるかしゃべれないかで生徒や先生方との距離感の詰め方もだいぶ違うのです。
基本子供たちはフィンランド語で会話します。英語を日常で使ってる子はまずいない。
先生方は英語で話せる方も何人もいるのですが、全員ではない。何より、子供たちと授業や授業時間以外で絆を作っていく上でコミュニケーションをとるのに、国の言葉は非常に重要だと感じますし、先生方も、集まる休憩所では基本フィンランド語で話しています。
早すぎて自分はまだ話にもついていけないし、会話に入るのも難しいです。
皆さん優しいので、時々英語で今このことについて話してるよ、とか教えてくださるんですけどね。
もちろん、生徒たちや先生方との関係は徐々に向上しています。
よく生徒からフェイスブックの申請もきますしね(笑)
ただ、いつまでも甘えてはいられないので、現地で行われているフィンランド語講座に通うこと、日本にいたときお世話になっていたスオミ会のフィンランド語講座にスカイプで参加など、できることはしっかりやっていきたいと考えています。
最初に相撲について説明し、どのように試合が行われるのか観てもらうためにYoutubeの映像を使用しました。最後にアクティビティで折り紙の力士を折り紙相撲を行ったのですが、担任の先生から映像を先に見て紙相撲を行うのはとても理解しやすいと言って頂きました。
内容が盛りだくさんなので授業時間を過ぎてしまったクラスもありましたが、言葉で説明するだけでなく、映像や体験で理解してもらうことの大切さを改めて感じました。
クリスマスはホストファミリーと過ごしました。まずはポリッジを食べ共同墓地へ行きキャンドルを灯し、その後サウナに入りたくさんの料理を食べました。9歳の男の子はサンタクロースはまだかまだかとソワソワしてました。プレゼントは玄関に置かれていて、プレゼントを開けるときが1番楽しみだと言っていました。私にもプレゼントがありとても嬉しかったです。その後3日間はクリスマス料理を食べ続けました。
休みには前のホストファミリーの家へ行きクロスカントリースキーをしました。意外に難しかったんですが、いい運動にもなるし楽しかったです。これからもっと練習して上手く滑れるようになりたいなと思います。それから最近はホストマザーとずっと編み物をしています。次は何作ろうと言いながら、編み物初心者でしたが教えてもらいながら今ではいろいろ編めるようになりました。冬のフィンランドで過ごすのには編み物はとてもいいかと思います。
他の参加者の方も利用しているようですが、おりがみくらぶは様々な折り紙が様々な言語で紹介されており、ビデオもアップロードされているのでインターン活動を助けてくれるウェブサイトの1つだと思います。
先週で年内の活動は終了したので、来年はジャンプするカエルと紙相撲を紹介しようと考えています。
書道は1時間では1人1人に丁寧に教えてあげることはできなかったんですが、月~日までを前に書いて好きな曜日を書いてって言ったら、全部書きたいって言って結構興味を持ってくれました。その後自分の名前を書いてあげるとさらに喜んでくれました。
いつもいる学校では時間があったので、担任の先生に前もって生徒に書きたい言葉を聞いてもらって、それを日本語に訳して1人1人手本を書きました。当日名前を呼んで1人1人手本を渡していくと、皆それぞれ違うので驚いたような顔をしていました。授業が終わってからも妹やお母さんの名前を書いてと私のところにやってきました。日本語に少しでも興味を持ってくれるだけでもうれしく思いました。
1週間いた学校で授業見学してたクラスに、ちょうど誕生日の子がいてお祝いで誕生日の歌をうたいました。まずフィンランド語でその後英語で、そしてその後日本語で歌ってほしいと言われたので英語の歌詞を訳したのでうたいました。
ちょうどこの前にいつもいる学校の併設の幼稚園の先生からお誕生日の歌を日本語で教えてほしいと言われ、でも日本では英語で歌ってたので、調べてみるといくつかの歌詞がありました。これといったのはなく、なんで日本では英語でうたってるんやろうという疑問は残ったんですが、どこの国でも英語の歌詞と同じ歌詞なので簡単な方がいいと思いそのまま英語を訳したのを教えました。
この授業の後教室から出て行こうとすると、何で帰るんって生徒が言ってくれたり、会うたびに皆あいさつしてくれたり、1週間でしたがとてもハードで充実した時間でした。
生徒たちはシャイでおとなしい子が多いように感じましたが、きちんと話を聞いてくれてとても嬉しかったです。
生徒の一人がシャイでおとなしい点がフィンランドの文化の一つなんだと教えてくれました。
時間を頂くことで、日本文化を伝えるだけでなく、フィンランドの文化を学んでいけるようにしたいなと考えています。
私の学校では今年あいさつをすることを大切にしているので、日本語であいさつを教えてほしいと言われました。それから私が千羽鶴を折りたいと言ってたので、それもこの日にできることになりました。
まず最初に校長先生が何カ国かの言葉でおはようを教えて、その後に私が日本語で言いました。そして私が千羽鶴の話を日本語でして、その後英語の先生がフィンランド語でしました。最初は私がフィンランド語で話そうと思ってたんですが、日本語を聞くのは子供たちにとっていいことだからということで日本語で話すことになりました。
英語の授業でもいろんな国の言葉を子供たちに聞かせていて、先生は小さい頃の聞くのは大切なことだと言っていました。
そういうわけでこの日はインターナショナルな日で、私と先生は浴衣を着ました。他の先生や子供たちもそれぞれいろんな国の衣装を着ていまいした。
その後全校生徒が数か所に分かれて鶴を折りました。低学年の子たちにはちょっと難しいだろうということで簡単な羽ばたく鳥を教えました。この日までに先生と5年生の女の子たちには鶴の折り方を事前に教えて、当日教えるのを手伝ってもらいました。休み時間に集まって皆さん覚えてくれたので嬉しかったです。
何とか無事に終わり、休みの間も学校に出てきた先生が鶴に糸を通して木の枝に飾ってそれをランチホールに飾ってくれました。まるで本当に鶴が飛んでいるようで、千羽鶴ではなくなりましたが、とても素敵で良かったなと思いました。
ホームステイ先では、これまで、ちらし寿司、お好み焼き、オムライス、天ぷら、チャンチャン焼きを作りました。持参したカツオ節以外、すべて現地の食材、調味料で再現できました。海外でもお米はよく使われていますが、「炊く」というよりは「茹でる」調理法が主流なので、炊き方に興味を持っておられました。お好み焼きのソースにはHPソースを代用しました。ラーへでは、醤油、わさび、海苔、みりん、米酢などをスーパーで購入できます。ヘルシンキには日本食材店があるそうです。
研修先の学校について。パソコンによっては日本語を表示できないようです。パソコンなどの環境は、教室によって様々です。先生の希望に合わせてあるようで、OHPだけの教室、インターネットに接続できる教室、様々です。コピー枚数や画用紙など消耗品の使用に制限はありません。折り紙が一番人気ですが、日本から持参した折り紙と学校のコピー用紙を併用しています。金魚やピアノ、トントン相撲の力士など、裏が白い方が適しているものには折り紙を、犬や猫、カエル、チューリップなど、完成した作品に表の色しか出ないものはコピー用紙を正方形に切って使っています。コピー用紙は折り紙より厚いので、カエルや手裏剣には、それぞれ縦に2分の1、4分の1サイズにカットして使っています。コピー用紙は茶色や緑、赤など濃い色からピンク、黄色、紫、水色など淡い色までたくさん種類があります。また、コピー用紙そのままのサイズで紙飛行機を作ると、しっかりしてよく飛びました。新聞紙で紙てっぽうも大人気でした。カブトは折り方が簡単なので、低学年に最適です。被るサイズを作るには、かなり大きな紙が必要ですが、模
造紙のような大きい紙を正方形にカットして作ったところ、色を塗り、カタカナで名前を書き、大好評でした。
新学期が始まりましたが、しばらくは夏休み前と同じく授業見学をしていました。textileや技術のクラスで一緒に作らせてもらったり、ロシア語も一緒に勉強したり授業参加を楽しんでいます。あとは英語の授業のお手伝いや他の授業も見に行ったりしています。
あまり話をしたことがなかった先生に話しかけたら、先生の彼氏が日本のバイクの「隼」が好きとのことで、書道で「隼」を書いてくれないかとお願いされました。また授業もしてほしいと言われました。授業が終わった後、またお願いしたいと言われました。それから他の先生も授業してほしいと言ってたよと教えてくれました。それからよく行ってるクラスの先生に、スカウティイングの子供たちに折り紙を教えてほしいと言われたので行ってきました。毎週いろんな活動をしているそうで、折り紙はとても興味を持ってくれました。日本に興味があるという子もいたので、これからもお邪魔しようかと思っています。
過去のインターンの方で折り紙クラブを始めたという方が結構いらっしゃったので、私も提案してみたらいいよという風に言ってもらえました。先生がフィンランド語でちらしを作ってくれたので、それを学校の掲示板に貼りました。来たい子は名前を書けるようにしてもらいました。何人来るかすごく不安でしたが、ちらしを見てすぐに名前を書いてくれました。今のところ週1回はこの折り紙クラブで教えています。夏休み前から何人かは折り紙に興味を持ってくれていて、どうしたら子供たちに教えれるかと考えていたので、折り紙クラブができてよかったです。最初は私が作った折り紙を見せたり何を作りたいか聞いてみました。2回目にジャンプするカエルと風船を作りました。遊べる折り紙だったので楽しんでくれたし、風船は日本語で数え方を教えたらとても興味を持ってくれました。
今回改めて何事も自分から行動しないといけないなと思いました。最初はなかなか授業をお願いされないし、先生が話してる会話の輪になかなか入れないので学校かわりたいなと思った時もありましたが、先生と話すためにきたのではなく子供たちに日本文化を紹介しに来たのだと改めて本来の目的を考えたらまた頑張ろうと思えました。先生とも個々には話をするし、ただ皆さん英語で話すのが億劫な感じなので自分からもっと話しかけたいと思います。それに焦らず自分のペースで先生や子供たちとコミュニケーションをとっていれば、自然に先生からお願いされるし子供たちとも仲良くなれると思います。今は休み時間におんぶしてーっと子供たちが私のところに駆け寄ってきてくれます。疲れたって思うこともありますが、子供たちが駆け寄ってきてくれるのはとてもうれしいので全力で遊ぼうと思っています。
現地ツアーに参加すればガイドは英語で話すので、せっかくの説明が聞き取れないこともありますが、これもまた英語力のアップにつながるかなと思います。それに比べて他の外国の方はほとんどみなさん聞き取れているようで、やはり外国では英語が話せるのが当たり前なのかなと、改めて自分の英語力のなさが悔やまれます。それでもフィンランドでの生活は何とかやっていけるので、ある程度の英語ができれば大丈夫だと思います。それにフィンランドの方の英語は同じくらいのスピードなので聞き取りやすくて、私は英語があまり得意じゃなかったので逆に英語圏じゃなくてよかったかなと思いました。英語はもちろん話せるようになりたいという気持ちは変わりませんが、それ以上にフィンランド語も話せるようになりたいと今は思っています。
語学の勉強は独学でしています。学校の先生に「easy finnish」というサイトを教えてもらいました。このサイトでlisteningやreadingなどフィンランド語を勉強することができます。それから、フィンランドに来てから英語で毎日日記をつけています。それを英語の先生に添削してもらっていました。今はできませんが日記だけは毎日書いています。こちらに来て1ヶ月くらいしてからは、英語の日記を書いてその下に3行ほどフィンランド語でも文章を書いています。
それから夏休みは先生たちとブルーベリーを採りに行って、伝統的なブルーベリーパイの作り方を教えてもらいました。ホストファミリーにもフィンランドの伝統的な料理やパンの作り方を教えてもらったり、私の住んでる地域のお祭りに行ったりしました。
渡航してみると、授業、給食、放課後、先生と生徒とのかかわり方、何をとっても日本とは異なるので最初は戸惑いました。休みに入るまでの約2ヶ月の研修で、ようやくこちらの授業・時間の感覚を掴みました。
まず時間感覚について。たとえば、毎日9時~3時までが学校の時間だと定められていても、自分の授業がない時間は「教師」として拘束されることは一切ありません。みなさん個人の時間として過ごすのです。途中一時間空いた場合、家に帰るも、学校で仕事をするも自由です。当初日本の学校の感覚しかもっていなかった私はこのことが分からず、夕方まで何もすることがないながら残ったりして困ることもありました。放課後も同様で、学年の授業終了時間にかかわらず、教師はだいたい同じ時間まで学校に残っているものと思い込んでいましたが、こちらではばらばらです。日によって、人によって、下校時刻は違います。それに気づいたとき、みんなあまりにもすっぱり帰るので驚いたものです。日本のように委員会活動や放課後クラブ活動がないことが理由のひとつだと思いますが、特徴的だと思いました。
次に授業のやり方については、パワーポイントの活用が功を奏していると思います。同じ写真を見せるのでも、見出しや動きなど少し工夫があると(特に低学年の生徒になるほど)テンポよく授業を進められます。時間も計りやすく、自分でシミュレーションもしやすいのでお勧めです。話に聞いていたとおり英語は高学年以上だとほぼ完璧に通じ、それ以下の学年では他の先生が丁寧に訳してくださいます。ですが、やはり現地語の方がこちらも生徒側も相手に親近感・興味を持てることを実感しています。生徒に教え、(言語を)教えられ、という状況は、授業以前にお互いの関係作りにとても有効だと思います。聞いたこともなかった言語の習得なんて、難しく思えて最初はめまいがしそうですが、自分がその言葉の中に生活しているということが最強の近道であり、分かり始めた時の嬉しさは格別です!
現在は日本より一足先に6月のはじめから夏休みに入り、休暇の真っ最中です。今年のフィンランドは例年より涼しいようで、先週は一週間大雨時々雷という天気が続きました。
夏休み中もたまに学校の先生たちと誰かの家を訪れてサウナを楽しんだり、買い物に出かけたりしています。また、たくさんある時間を利用して集中的にフィンランド語を勉強中です。そろそろ、新学期からのトピックや授業の組み立てを先生たちとお話しながら行っていく予定です。
これまで本当に現地の多くの人の親切に支えられていることに心から感謝して、引き続き頑張って生きたいと思います。
フィンランドはもう6月から夏休みなので、最後の1週間はテストも終わり授業がありません。時間があるということで授業をさせてもらいました。特に好評だったのが広告で作ったpaper gunでした。作ってからは残りの時間ずっと遊んでいました。Paper gunは1度鳴らすと元に戻さないといけないので、鳴らしては元に戻して~と子供たちが来て、忙しかったですが楽しんでもらえてよかったです。Dog & Catもすごく興味をもってもらえたので、最初に楽しめる折り紙をすると日本文化に興味を持ってもらえるし、子供たちとの距離も近づける気がしました。それから、もう卒業してしまうクラスで折り紙を教えてほしいと言われ、最後の日に折り紙をしました。何を作りたいか聞いたところ圧倒的にポケモンでした。こっちの子供たちは不器用だと聞いていたけど、この学校の生徒たちは結構上手く折っています。ポケモンも時間内に折れたし、他の学年では、あまりトトロは知らないようでしたが、トトロ折ってみたら皆作れました。そして、ポケモンを作っていたら他の先生も教室にやってきて、興味を持ってくれて一緒に折っていました・u・。そして、夏休みに私の子供たちにも教えてほしいと言われました。
その最後の日には伝統的な行事として、卒業生VS 先生でfloor ballというアイスホッケーの土の上でやるバージョンで対決するそうで、私も初めてのスポーツですが先生チームに参加させてもらいました。子供たちは私が出ると私の名前を呼んで応援してくれたので嬉しかったです。途中先生チームが勝っていたんですが結局負けてしまいました。毎年卒業生が勝つそうです。その後先生方がランチルームに集まってケーキを食べながら、休暇に入る先生にお花を渡したりしました。そのときに校長先生と教頭先生にお花を渡すので、サムライヘルメットをかぶせてあげてはどうかと言われ作って用意しました。そしてかぶせてあげると笑いがおきました。他の先生にもサムライヘルメットを披露することができた良い機会でした。
こちらでは終業式と卒業式が土曜日に一緒に行われます。私も見に行きました。そこでは各クラスそれぞれ練習していた歌やダンス、劇などが行われ、最後に卒業生に先生から1人ずつ花を渡すというものでした。日本とは全然違っていて、こういう式は見ていて楽しくていいなぁと思いました。そして私は仲良くなった子供たちから「Have a nice summer」と書かれた手紙をもらいました。2か月ちょっと子供たちに会えないのは寂しいけど、長い夏休みを楽しもうと思います。日本とは全く違う学校の習慣を体験できて、とてもよい経験でした。