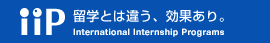4月着任当初は現地小学校に関わっていたが、縁あって8月より研修先を現地中学校に変更して研修を継続している。生徒が約600人のフィンランドでも有数の大規模校であり、アシスタントなども含めると70人以上の教職員が関わっている。生徒は近隣国からの移民も多く、言語の面で苦労している生徒も多い。そうした事情への対応など、これまでとは違ったフィンランドの教育システムの一面を見ることができ、学びが多い環境である。また、教職員は日本の文化や教育、社会について興味をもっており、日々さまざまな教育事情や課題について情報交換や対話を行うことができている。
国際交流授業も多く実施している。まずは日本の学校教育や教育制度について、7年生と9年生の「進路指導」にあたる教科において講話を行った。写真や映像などの資料を示すことで、生徒たちは日本の学校生活に大いに興味を抱いていた。グローバルな社会を生きていく子どもたちにとって、教育制度が国によって違うことや様々な背景があることを知るのはとても有意義だと感じた。また、日本のさまざまな教育制度、例えば校則やクラス替え、行事や清掃活動などは、フィンランドの先生方にとって考えさせられるものだったという。教育無償化が実現されている一方、すべてが"当たり前"となり学校の備品などを大切に使わないことや、スマホを学校に持ち込めることで授業中も指導しにくいことなどを先生方は嘆いており、これはフィンランドの多くの学校で起きているそうだ。また、フィンランドは現在多くの移民を受け入れ、当校でも移民学級の対応がとられている。しかし、実際には言語の壁は高く、生徒や先生方への補償も十分とは言えないそうで、インクルーシブ教育の実際も含め、現場の先生にとっては課題が多い。
生徒を見ていても、移民の生徒が抱える葛藤は大きく、しかし制度としては限界があることも理解できる。そもそもフィンランド人の生徒についても、ここ10年くらいで性質が変わってきており生徒指導に苦慮していると先生方は話していた。そのような負担感からか、鬱などの理由で病休に入る先生も少なくなく、代替教員(フィンランドでは大学院生が行っている)が見つからず人手不足であるなど、国は違えど現場の苦悩については近しいものがある。いずれにせよ、同じ学校に継続して関わることができているため、生徒の様子や先生方の考えなど、忖度なくリアルな学校現場を視察することができている。
また、水墨画や折り紙、祭事についてなど、日本の文化について紹介する授業を実施した。授業準備にあたり、私自身も改めて日本について調べることで、国際交流とはまず自国のことを知ってから始まるということを実感した。帰国後、日本において国際理解教育を進めていく際に、この経験を指導に生かしていく。
その他、学校行事なども参加・見学することでフィンランドの教育現場について理解を深めつつ、教育にはその国の国民性や価値観などが反映されていることを実感する日々である。