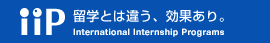早いもので、1か所目の活動が終わりました。
ハイライトとして印象深いのは、現地の学校教育関係者による、日本の学校ドキュメンタリー映画の観賞会です。
鑑賞したのは「小学校~それは小さな社会~」という、世田谷の公立小学校の一年に密着した映画で、掃除当番や給食配膳、委員会活動など、児童らに与えられた様々な役割や彼らの一日の風景から得るものは無いか、とフィンランドの学校関係者が考えて企画されたのだそうです。フィンランド全土の主要な映画館で公開されていました。
また、鑑賞後に行われたパネルディスカッションに呼ばれ、壇上で話す機会を頂きました。
教育関係者ではないので、自分に務まるかとても不安でしたが、その場にいらっしゃった現役学校関係者のIIP派遣生の方2名に助けて頂き、なんとかやり切りました。
現在のフィンランドの学校教育は選択科目が多いらしく、選択の自由を与えると「選択しない」子が多い(=やらなくてよいことはやらない)そうで、身に着けるべき知識も勉強する機会がない、と嘆いている教職員も多かったです。
連帯性を重んじる日本の教育は、フィンランド人にはやや軍隊的に映ったようですが、ある程度強制的に学ばせた方が良いこともある、と感じているそうで、フィンランドの学校教育関係者が日本の教育スタイルから学びを得ようとしている姿が印象的でした。
パネルディスカッション参加にあたり、日本で教職員をしている友人数人にインタビューしてみましたが、少なからず不満を抱えているのに大勢は変えられないと皆半ばあきらめているようで、アクティブに変化しようとするフィンランド人の姿勢は見習わないといけないなと思いました。
教育に従事していない自分はなかなか受け入れ先が決まらず苦戦しました。また、現地で医療機関にかかることがあり、診察の電話予約では英語が喋れないオペレーターが多く、一人ではどうにもできないこともたくさんありました。そんな自分を受け入れ、貴重な経験を与えてくれて、生活を助けてくれたホストファミリーに本当に感謝です。
ホストファーザーである校長は、最終日別の場所へ電車移動する際は駅まで送ってくれて、車内に荷物を運ぶのも手伝ってくれました。出発前、派遣先が決まって嬉しかったこと等を思い出して、挨拶しながら泣いてしまいました。フィンランドの実家のような存在になりました。