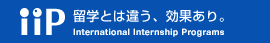フィンランド中央部にあるPihtipudasの小規模高校で研修をしています。今回は実践した授業について報告します。フィンランド語が全く話せないので、拙い英語で授業を進めています。高校と中学の授業では概ね理解してもらえます。小学校の低学年の生徒に対しては、途中途中でフィンランド語で説明してもらうことも多いです。
授業① 寿司パーティー
高校3年生の英語の授業で国際理解と称して、寿司パーティーを開きました。巻き寿司と握り寿司、インスタントの味噌汁、緑茶という簡単メニューでした。授業時間54分におさめるために、英語の先生と相談して、酢飯と錦糸卵は事前に用意して、後は具材を海苔で巻くだけ、握って鮭やいくらを載せるだけ、という段取りにしました。生魚を食べれないという生徒や卵アレルギーの生徒もいましたが、巻いたり握ったりする作業は楽しそうに取り組んでいました。片付けの時間まで入れると若干時間切れの面もありましたが、ワサビや折り紙で作った箸袋などは生徒にも先生にも好評でした。ただ、残った食材や巻きずしの切れ端などを容赦なく捨ててしまうのを見て、米の一粒まで大切にする意識やもったいない精神などについても事前に触れておけばよかったと反省しました。
授業② 日本の高校との交流授業
日本の高校と異文化交流授業を行いました。時差の関係で、フィンランドの午前中の英語の授業と日本の授業の時間帯が合わず、日本の高校には放課後に有志を募ってもらい交流が実現しました。接続の準備や打ち合わせの時間を考慮して、交流時間は正味40分としました。双方の出席者が10名程度だったこともあり、自己紹介とそれぞれの学校紹介の後、質疑応答という構成で時間内に収まりました。お互いに、緊張していたのとシャイなのとで、最初はぎこちない場面もありましたが、後半は日本側の生徒が活発に質問をしていたのが印象的でした。英語力の差はあったと思いますが、コミュニケーションをしようとする姿勢が大事だということが生徒自身にも理解できたのではないかと思います。終了後は、双方のホームページやSNSに授業の様子を掲載したり、リンクを貼ったりして、発信することもできました。
授業③ 折り紙教室
小中学校へ折り紙の出前授業に行きました。折り紙の経験がある生徒もいましたが、手先を細かく使うことや、折り紙特有の紙の折り方は、慣れない分難易度が高いようで、年齢を問わず苦戦しつつも楽しそうに取り組んでいました。完成したものを眺めて楽しむだけでなく、使ってほしいと思い、折り紙でブックマーカーを作成しました。アニメのキャラクターや動物をモチーフにしたもので、顔や名前を書き込むとオリジナルのブックマーカーが出来上がります。そのまま、宿題の個所に挟んでもらい、「これで全員宿題を忘れないね」などと声をかけると、生徒もまんざらでもない表情を浮かべていました。ポケモンのブックマークが大人気で、黄色の折り紙を大量に使いました。12月には、クリスマスシーズンのためサンタクロースやクリスマスツリーの折り紙を取り上げました。こちらも、メッセージカードや飾りつけに使える実用的なものを意識しました。この時は、赤の折り紙を多く使いましたが、途中でなくなってしまい、赤い包装紙を正方形に切って代替しました。サンタのメッセージカードに「love」を日本語で書きたい、と尋ね
た生徒がいて、「愛」と黒板に書いたところ、クラスの生徒全員が黒板に「愛」と上手に書いたのを見た時は、不思議な気持ちと感動とで胸が熱くなりました。
授業④
中学2年生、3年生に日本語の授業をしました。日本のゲームやアニメは中学生に浸透しており、アニメの声優の声を生成する無料ソフトを使って、ひらがなやカタカナについて説明しました。象形文字、指示文字、会意文字の漢字の意味をクイズ形式で出したところ、イメージを膨らませて漢字の成り立ちや意味を理解してくれました。基本的に、マンガの吹き出しにはすべて振り仮名が振ってあるので、ひらがな対照表でセリフの読み方を拾って、google翻訳の日本語の枠にローマ字入力すると、英訳やフィンランド語訳が出てきます。生徒の前でアプリやソフトを使ってみせると、ハードルが下がり興味をもってくれたように思います。
自分の名前をひらがなやカタカナで書く、というシートを作りましたが、フィンランドの名前は日本語で表記しにくい発音や、ja(ヤ)、vo(ヴォ)など対照表に書かれていないものも多く、理屈を説明するのが非常に難しかったです。
授業① 寿司パーティー
高校3年生の英語の授業で国際理解と称して、寿司パーティーを開きました。巻き寿司と握り寿司、インスタントの味噌汁、緑茶という簡単メニューでした。授業時間54分におさめるために、英語の先生と相談して、酢飯と錦糸卵は事前に用意して、後は具材を海苔で巻くだけ、握って鮭やいくらを載せるだけ、という段取りにしました。生魚を食べれないという生徒や卵アレルギーの生徒もいましたが、巻いたり握ったりする作業は楽しそうに取り組んでいました。片付けの時間まで入れると若干時間切れの面もありましたが、ワサビや折り紙で作った箸袋などは生徒にも先生にも好評でした。ただ、残った食材や巻きずしの切れ端などを容赦なく捨ててしまうのを見て、米の一粒まで大切にする意識やもったいない精神などについても事前に触れておけばよかったと反省しました。
授業② 日本の高校との交流授業
日本の高校と異文化交流授業を行いました。時差の関係で、フィンランドの午前中の英語の授業と日本の授業の時間帯が合わず、日本の高校には放課後に有志を募ってもらい交流が実現しました。接続の準備や打ち合わせの時間を考慮して、交流時間は正味40分としました。双方の出席者が10名程度だったこともあり、自己紹介とそれぞれの学校紹介の後、質疑応答という構成で時間内に収まりました。お互いに、緊張していたのとシャイなのとで、最初はぎこちない場面もありましたが、後半は日本側の生徒が活発に質問をしていたのが印象的でした。英語力の差はあったと思いますが、コミュニケーションをしようとする姿勢が大事だということが生徒自身にも理解できたのではないかと思います。終了後は、双方のホームページやSNSに授業の様子を掲載したり、リンクを貼ったりして、発信することもできました。
授業③ 折り紙教室
小中学校へ折り紙の出前授業に行きました。折り紙の経験がある生徒もいましたが、手先を細かく使うことや、折り紙特有の紙の折り方は、慣れない分難易度が高いようで、年齢を問わず苦戦しつつも楽しそうに取り組んでいました。完成したものを眺めて楽しむだけでなく、使ってほしいと思い、折り紙でブックマーカーを作成しました。アニメのキャラクターや動物をモチーフにしたもので、顔や名前を書き込むとオリジナルのブックマーカーが出来上がります。そのまま、宿題の個所に挟んでもらい、「これで全員宿題を忘れないね」などと声をかけると、生徒もまんざらでもない表情を浮かべていました。ポケモンのブックマークが大人気で、黄色の折り紙を大量に使いました。12月には、クリスマスシーズンのためサンタクロースやクリスマスツリーの折り紙を取り上げました。こちらも、メッセージカードや飾りつけに使える実用的なものを意識しました。この時は、赤の折り紙を多く使いましたが、途中でなくなってしまい、赤い包装紙を正方形に切って代替しました。サンタのメッセージカードに「love」を日本語で書きたい、と尋ね
た生徒がいて、「愛」と黒板に書いたところ、クラスの生徒全員が黒板に「愛」と上手に書いたのを見た時は、不思議な気持ちと感動とで胸が熱くなりました。
授業④
中学2年生、3年生に日本語の授業をしました。日本のゲームやアニメは中学生に浸透しており、アニメの声優の声を生成する無料ソフトを使って、ひらがなやカタカナについて説明しました。象形文字、指示文字、会意文字の漢字の意味をクイズ形式で出したところ、イメージを膨らませて漢字の成り立ちや意味を理解してくれました。基本的に、マンガの吹き出しにはすべて振り仮名が振ってあるので、ひらがな対照表でセリフの読み方を拾って、google翻訳の日本語の枠にローマ字入力すると、英訳やフィンランド語訳が出てきます。生徒の前でアプリやソフトを使ってみせると、ハードルが下がり興味をもってくれたように思います。
自分の名前をひらがなやカタカナで書く、というシートを作りましたが、フィンランドの名前は日本語で表記しにくい発音や、ja(ヤ)、vo(ヴォ)など対照表に書かれていないものも多く、理屈を説明するのが非常に難しかったです。