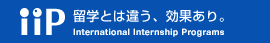「子どもの幸せとは」「教育とは」など、いろいろと考えることができました。日本、デンマーク、どちらの国も、「子どもたちが豊かに生きることができるように」という教育の目的は変わりません。
しかし、日本の学校は、「いかに勉強するか」「学習で成果を上げるか」という側面が強いのに対して、デンマークは、「民主主義社会の一員として、助け合いながら、いかに豊かに楽しく生きるか」ということに重点を置いた教育をしていると感じました。それについて、よくホストの校長先生とも語り合うことができました。
また、これまで、不登校の増加や子どもや教師のメンタルの問題などは、日本の教育システムに何か問題点があるのではと感じていましたが、デンマークにも同じような状況は見られ、子ども大人含めて、人間そのものは、どの国も同じだと感じました。特に、授業をしていて、子どもたちは、国が違っても共通だとすごく感じました。
ニュージーランドのMastertonに来て、約一ヵ月が経ちました。首都Wellingtonから車で一時間半ほどの場所に位置する小さな町に滞在しています。本稿では、ここまでの実習について書きます。
私は、Makoura collegeという学校で、日本語クラスの教員として実習に参加しています。Collegeというと、大学をイメージしますが、ここではHighschoolを意味するようです。ニュージーランドでは、5歳からprep-yearに入りYear 6までの7年間をprimary school。Year 7からY 8をIntermediate school。Year 9からYear 13までをsecondary school/collgeに通います。(通う学校による)私の実習先は、Year 9からYear 13の生徒が通うCollegeです。
実習校は、必修科目であるNumeracy/Literacyと、4つの枠から1つずつ科目を選択した合計5科目で授業を構成しています。そのうちの1つが日本語クラスです。他の授業と同じ配分で、70分授業が週4回あります。週4回なのは、生徒のためでもありますが、教員が週に一度は自分の生徒と顔を合わせない日を作るためでもあるそうです。
日本語クラスは、担当の先生が2人います。35人と多いので2つのクラスに分かれて作業をしています。一人の先生は、基本的な日本語の読み書き・会話ができ、その方がメインで教えています。もう一人の先生は、担当者ではなかったけど、思いのほか選択した生徒が多く、配属されたそうです。
授業は、メインの先生を中心に、一緒に考えます。LanguageとCultureの項目に分けて、なるべくどちらも学ぶことができるように授業を組んでいます。といっても、指導案を作ったり、具体的に計画はしていません。当日の朝、その場で考えて、一時間目の授業を行うこともあります。(それでも意外となんとかなってしまうものです。)急に、今日は日本語のゲームかなんか紹介してくれない?とか、プリント用意できなかったんだけど、今日何したらいいと思う?と聞かれたりします。言語に関しては、ひらがな、ローマ字からスタートしました。
先生は、私のやってみたいことはないかと質問してくださり、すぐに私の提案に応じようとしてくれます。だから、私もなるべく応えようと思い、日本で作っていた授業案のリストから提案したり、先生がこういうのやってみたいと伝えてくれたことを軸に提案して、週に1回、2回と少しずつ自分の担当する回を増やしています。自分が授業内容を計画していないときは、発音のサポートや、文を書くときのサポート、会話練習のサポートをしています。
☆やってよかったこと
・ひらがなかるた:【あ】と発音して、【あa】を見つけてもらう。少し慣れてきたら、学習した単語を読んで、散らばったひらがなカードから単語をつくってもらいます。【こあら】→【こ】と【あ】と【ら】
・日本について知ってることを書いてもらう。
・立って歩き回り、合図を出したときに出会った人と【挨拶・簡単な自己紹介】を行う。
・意外と知らない日本料理を知ろう→クイズ
・日本についてクイズ
27年前、イギリスの中等教育学校でのスクールインターンの経験は、当時教育学部の学生だった私に大きな影響を与えました。その後、小学校の教員となった私は、オーストラリアの学校での教育交換プログラムを経て、今のイギリスの小学校教育を見たいという思いがさらに強くなり、今回のイギリス滞在を決めるに至りました。自分の仕事の都合上、1月の1週間という短い間でしたが、この27年間、英語の学習を続けてきてよかったと今ほど思ったことはありません。以前の記憶も頼りとなり、27年前の9ヶ月間に匹敵するほど、イギリスの教育について数多くのことがわかりました。また、これまでの教員生活で感じてきた疑問点について、日本とイギリスとを比較することで、自分の視野や考え方が広がったことを感じました。温かく受け入れてくださり、すべてをオープンに見せてくださったウェスト・ミッドランズ州の研修校の先生方や児童に感謝がつきません。
学力向上、不登校対策、特別支援教育と、教育を巡る課題は様々な国で共通していますが、中でも私が一番知りたかったことは、不登校対策です。イングランドでは、出席率に対して高い目標値があり、子どもが学校に行かない場合は保護者が罰金を払うこともあるという、厳しい政策を耳にしたことがあります。コロナ禍を経て、子どもの学びや学校に対する意識が変わりつつある中で、おそらく保護者だけに責任を負わせることはないだろう、学校としても子どもたちが学校に来たくなるような工夫をしているはず、問題だとは言いつつも高い出席率を保っているイングランドの学校には、どのような秘密があるのだろうか、という思いを胸に、渡英しました。1週間という短い期間なので、私が知り得たことはほんの一部だと思います。そのような中で一番印象に残ったことは、温かい教育環境です。教室にはカラフルで楽しい掲示物、たくさんの植物。常にグループで座るので友達との距離も近く、休み時間にはおやつを食べるので、自然と楽しい雰囲気になります。登下校は保護者同伴なので、登校時には出迎える校長先生と親子で挨拶をし、下校時には担任の先生と保護者が一言挨拶を交わします。「苦情も多いのよ。」と話す先生もいましたが、担任の先生から「今日はこんなことを頑張りましたよ。」と言われ、保護者に褒められながら帰って行く子どもたちを見て、保護者と教員が数多く顔を合わせることも、子どもが学校に通いやすい環境に役立っているのではないかと思いました。
生徒指導に関しては、学校教育目標の活用も大いに参考になりました。「イギリスの学校の先生は、生徒指導や学級経営には重きを置かず、主に学習指導に焦点を当てて取り組んでいる」という話を聞いたことがあり、実際に27年前もそのような印象を受けましたが、今回滞在した学校では、校長先生を筆頭に、先生方お一人お一人が生徒指導にもとても積極的に取り組んでいました。学校教育目標のような扱いであるSchool Rule はShow respect、Be ready、Make safe choicesの3点で、とても簡潔です。しかしこの3つが生徒指導の核となり、あらゆる場面で児童に意識付けられます。授業中に話を聞いていないと、Show respectとBe readyを振り返らせ、休み時間にトラブルがあるとShow respectとMake safe choicesを振り返らせ...。自分の行動を何がいけなかったか、これからどうしたいかをきちんと学校教育目標と結びつけさせ、指導していました。振り返って自分の日常を考えると、学校教育目標はもちろん大切ですが、そこから下りてきた生活目標、学習目標、保健目標、給食目標とたくさんの目標があり、どれも大切でたくさんのきまりを覚えなくてはならない、という感じも受けます。今後の学校教育では、自己指導能力の育成が重要になってきます。すべての元となっている学校教育目標を児童自身も自覚し、それに向けて自己調整できる働きかけをしていく、大変参考になりました。
私は現在、勤務校の学力向上を担当しており、児童の基礎学力の定着や活用力の育成に取り組んでいます。社会によって求められる学力や学力の定義は異なり、各種国際調査の結果が発表されても、国際間で学力の単純な比較はできないと常々感じています。特に、7年前にオーストラリアのシュタイナースクールで教育交換プログラムをさせていただいたときに、強く感じました。27年前にイギリスの中等教育学校に滞在した際には、ドリル的な知識の定着よりも、子どもの思考の過程を大切にし、一人一人の興味関心に応じた学習や調べ学習を重視している印象を受けました。今回は校種が違うこともあり、また違った学習指導の様子を知ることができました。特に驚いたことは、授業時間に対する国語と算数の学習時間の長さです。1週間の滞在中、1年生から6年生まですべての学年を見せていただきましたが、どの学年も午前中は国語と算数の授業しか行っていませんでした。しかも一単位時間が1時間から1時間半と、日本ではあり得ない長さです。現在の勤務校では、一日6コマの授業がある高学年の児童でも、国語も算数も毎日1コマ、45分間ずつしか学習していません。そしてその1時間から1時間半の授業中、1年生の児童もおしゃべりをすることなく、学習に集中しているのです。算数のテキストは、シンガポールの学習メソッドをイングランドのカリキュラムに当てはめて作られたもの、ノートの使い方もシンガポールを参考にしたものと、国際学力調査で好成績を収めているシンガポールの学習の仕方を取り入れているとのことでした。一単位時間の中の学習の進め方がきちんと設定されているところにも、指導者が変わっても児童は同じような指導を受けることができる工夫を感じました。また、朝の学習や読書、単語練習など帯活動を設定し、さまざまな方法で児童の基礎学力の定着を図っている様子がわかりました。探究学習や家庭学習、実技教科の指導など、知りたいことはまだまだたくさんありましたが、国語・算数を中心に学力向上に本腰を入れている様子に、私たちも頑張らなくてはと身が引き締まる思いがしました。
特別支援教育においても、多くの学びを得られました。イングランドではインクルーシブ教育を行っており、個に応じた支援が充実しているという話を聞いたことがあります。滞在中も、学習支援の道具を使っている児童がいたり、先生が個に応じた課題を出したり、ホールで取り出し指導を受けている児童がいたりと、様々な対応が見られました。また、授業に入り支援・指導を行う支援員さんの人数も充実していて、それぞれの児童が達成感を感じられるような工夫をしていると感じました。ワークシートを用いたノート支援は、四分の一の児童が受けているクラスもありましたが、児童はそれを当たり前のように受け入れていることから、このような個別の配慮が日常的に行われていることがわかりました。ただ、先生方のお話を伺うとインクルーシブ教育にも限界があり、様々な苦労をしているようです。児童のやりがい、自己肯定感、保護者の願いなど、様々なことを勘案した上で、児童にとってふさわしい教育を行えるよう、国を超えてみんなで考えていければと思いました。
研修校には2か国語以上を話す児童も多く在籍しており、学校の中で40もの言語が話されているそうです。そのためか、外国語習得に対する意識も高く、児童は数多くの日本語を知っていました。5年生のクラスで日本語や日本文化を紹介する授業をさせていただきましたが、挨拶や簡単な自己紹介など、児童は次々と知っている日本語を話してくれました。また、紙飛行機や折り鶴など、折り紙もとても親しまれていました。そこで授業では日本語の文字に慣れ親しむことをメインとし、片仮名で自分の名前を書くことに挑戦しました。和紙の折り紙で作ったカードに片仮名で名前を書いてあげ、児童はそれをなぞって練習していたのですが、数分後には何も見ないで書くことに挑戦する児童が増えてきました。名前の中に「ツ」や「シ」があると「スマイリーフェイスがある!」と喜ぶ子がいるのは、27年前の研修校(2校)と同じで、懐かしく思い出しました。
研修校の先生方とのおしゃべりはとても楽しく、教員という職業に共通する思いを感じる瞬間がいくつもありました。働く環境、児童の実態、求められている仕事は違っても、子どもたちを思い、豊かな人生を切り拓くことができるよう精一杯応援する姿勢は皆同じです。国を超えて同じ目標をもつ仲間ができたことは、私にとって大きな励ましとなりました。27年前の1回目、7年前の2回目に引き続き、今回もすてきな体験をさせていただき、大変ありがとうございました。それぞれの研修校で先生や子どもたちから学ばせていただいた多くのことは、今後も私の教員生活に大きく影響すると思います。これからも、学び考え続けられる教員でありたいと思います。ありがとうございました。
4月着任当初は現地小学校に関わっていたが、縁あって8月より研修先を現地中学校に変更して研修を継続している。生徒が約600人のフィンランドでも有数の大規模校であり、アシスタントなども含めると70人以上の教職員が関わっている。生徒は近隣国からの移民も多く、言語の面で苦労している生徒も多い。そうした事情への対応など、これまでとは違ったフィンランドの教育システムの一面を見ることができ、学びが多い環境である。また、教職員は日本の文化や教育、社会について興味をもっており、日々さまざまな教育事情や課題について情報交換や対話を行うことができている。
国際交流授業も多く実施している。まずは日本の学校教育や教育制度について、7年生と9年生の「進路指導」にあたる教科において講話を行った。写真や映像などの資料を示すことで、生徒たちは日本の学校生活に大いに興味を抱いていた。グローバルな社会を生きていく子どもたちにとって、教育制度が国によって違うことや様々な背景があることを知るのはとても有意義だと感じた。また、日本のさまざまな教育制度、例えば校則やクラス替え、行事や清掃活動などは、フィンランドの先生方にとって考えさせられるものだったという。教育無償化が実現されている一方、すべてが"当たり前"となり学校の備品などを大切に使わないことや、スマホを学校に持ち込めることで授業中も指導しにくいことなどを先生方は嘆いており、これはフィンランドの多くの学校で起きているそうだ。また、フィンランドは現在多くの移民を受け入れ、当校でも移民学級の対応がとられている。しかし、実際には言語の壁は高く、生徒や先生方への補償も十分とは言えないそうで、インクルーシブ教育の実際も含め、現場の先生にとっては課題が多い。
生徒を見ていても、移民の生徒が抱える葛藤は大きく、しかし制度としては限界があることも理解できる。そもそもフィンランド人の生徒についても、ここ10年くらいで性質が変わってきており生徒指導に苦慮していると先生方は話していた。そのような負担感からか、鬱などの理由で病休に入る先生も少なくなく、代替教員(フィンランドでは大学院生が行っている)が見つからず人手不足であるなど、国は違えど現場の苦悩については近しいものがある。いずれにせよ、同じ学校に継続して関わることができているため、生徒の様子や先生方の考えなど、忖度なくリアルな学校現場を視察することができている。
また、水墨画や折り紙、祭事についてなど、日本の文化について紹介する授業を実施した。授業準備にあたり、私自身も改めて日本について調べることで、国際交流とはまず自国のことを知ってから始まるということを実感した。帰国後、日本において国際理解教育を進めていく際に、この経験を指導に生かしていく。
その他、学校行事なども参加・見学することでフィンランドの教育現場について理解を深めつつ、教育にはその国の国民性や価値観などが反映されていることを実感する日々である。
ナダでは、州の中でも近い地域ごとにSchool Districtとして教育委員会が分かれており、教育のシステムもだいぶ違う。以前滞在したクランブルックでは、日本でいう中学校の年齢の子どもたちが通うMiddle schoolがあり、高校の学齢のHigh schoolがあった。ノースバンクーバーでは、Kindergarten(年長)からGrade7までがElementary schoolで、Grade8~12までがSecondary Schoolという分け方になっている。学習のカリキュラムもこのSchool Districtごとに決まっているため、日本のように学習指導要領によって全国の学習内容が統一されているわけではない。
また、こちらに来て新鮮に感じたのが学年を超えたクラスが大多数を占めているということだ。幼稚園以外は、1,2年生合同のクラス、2,3年生合同のクラスというように2学年合同のクラスが多数存在する。なぜかというと、こちらではインテグレーション教育をしているため、特別支援学校や学級は存在せず、特別支援の必要な子も常に通常級にいるため、その子につくEA(Educational Assistant)の配置によって、教育委員会が学年編成を決めるからだという。これについては、合同のクラスが好きという先生もいれば、1学年だけが好きという先生もいて興味深かった。
ちなみに、フルタイムではない先生やスタッフも多くいて、パートタイムの先生でも担任を持っている。そのような場合は、月~木曜日は〇〇先生で金曜日は△△先生というように決めている。育児をしながらでも働きやすい環境になっていると感じた。
学習や教室などに関しては、担任の個性が大いに反映されていて、教室の配置やあるものも全く異なっている。教科書があるわけでもないので、学習内容も何もかもその先生の力量にかかっているといってもいいかもしれない。日本は統一したり合わせることを大事にしすぎて、その先生の個性が出にくいところもあるという欠点もあるが、裏を返せば、標準化されているし、学年で揃えることによってある程度の質が保てるのかもしれないとも感じた。
現在は、まず、全てのクラスを見学させてもらう予定を立てている。先生方や子供たち、そして学習内容や発達段階を実際に見て理解した上で、日本文化の紹介につなげたいと考えている。