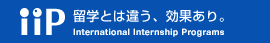2024年5月
オーストラリアでの研修が始まり、約1ヵ月が経過しました。研修校であるROSSMOYNE SENIOR HIGH
SCHOOLには日本語クラスがあり、日本語の先生が5名、日本人のアシスタントの方が7名程いらっしゃいます。私はアシスタントの一人として、毎日平均4時間、授業に参加しています。クラス内で学習進度に個人差はありますが、7年生から日本語を学んでいるため、12年生になると簡単な会話ならできる生徒も多くレベルの高さに驚きました。
現在参加しているクラスは、7年生から12年生と幅広く、各クラスとも個性的で、クラスごとの自分の役割、できることを探しながら研修をさせてもらっています。クラスによって、授業に集中することが難しい生徒、日本語が好きで自分でどんどん進めていく生徒など理解度の差が大きく、それぞれの生徒に合った対応ができるように取り組んでいます。生徒の英語が聞き取れず、質問の意図が上手くくみ取れないこともありますが、何か一つでも伝えられるようにという心構えで授業に参加しています。11年生、12年生はスピーキングのテストがあり、約1分間のスピーチとその内容に対する質疑応答、家族、学校、趣味、アルバイトなど与えられたトピックに関する質疑応答の2つのパートがあります。質問に答える際は、習得すべきグラマーポイントを使わなければならないため、生徒たちは一生懸命に文章を考えていました。スピーキングの練習に毎週入っていますが、グラマーポイントをおさえながら、より自然な日本語の文章に仕上げていくことが難しいと感じました。
自分にとって母国語である日本語を、苦手な英語で教える。英語での表現を学びながら、改めて漢字や言葉の意味、助詞の使い方などを振り返る日々です。また、生徒はみんな様々な国の文化、バックグラウンドを持っており、オーストラリアは「多文化主義国家」であるということを肌で感じます。あっという間に、研修期間も残すところあと1カ月となってしまいました。言いたいことを上手く伝えられず、もどかしいことも多々ありますが、今日の自分にできることを一つずつ、と自分自身に言い聞かせながら取り組んでいきたいと思います。
現在参加しているクラスは、7年生から12年生と幅広く、各クラスとも個性的で、クラスごとの自分の役割、できることを探しながら研修をさせてもらっています。クラスによって、授業に集中することが難しい生徒、日本語が好きで自分でどんどん進めていく生徒など理解度の差が大きく、それぞれの生徒に合った対応ができるように取り組んでいます。生徒の英語が聞き取れず、質問の意図が上手くくみ取れないこともありますが、何か一つでも伝えられるようにという心構えで授業に参加しています。11年生、12年生はスピーキングのテストがあり、約1分間のスピーチとその内容に対する質疑応答、家族、学校、趣味、アルバイトなど与えられたトピックに関する質疑応答の2つのパートがあります。質問に答える際は、習得すべきグラマーポイントを使わなければならないため、生徒たちは一生懸命に文章を考えていました。スピーキングの練習に毎週入っていますが、グラマーポイントをおさえながら、より自然な日本語の文章に仕上げていくことが難しいと感じました。
自分にとって母国語である日本語を、苦手な英語で教える。英語での表現を学びながら、改めて漢字や言葉の意味、助詞の使い方などを振り返る日々です。また、生徒はみんな様々な国の文化、バックグラウンドを持っており、オーストラリアは「多文化主義国家」であるということを肌で感じます。あっという間に、研修期間も残すところあと1カ月となってしまいました。言いたいことを上手く伝えられず、もどかしいことも多々ありますが、今日の自分にできることを一つずつ、と自分自身に言い聞かせながら取り組んでいきたいと思います。
クランブルックに到着し、翌日から学校に出勤、校長先生に学校を案内してもらい、先生方の授業を見せてもらうなどして過ごした。外国の中学校に教員という立場で行くのは初めてだったので、全てが興味深かった。日本文化を伝える授業も15回以上やらせてもらい、とても充実した毎日を過ごしている。今回は、この地区の時間割と教科について詳しく報告する。
【時間割】時間割のシステムが特徴的で、どの授業も平等な回数を行う上で合理的だと感じた。授業は1~8までのブロックに分かれていて、1ブロック(66分間)に1教科行う。毎日、生徒は5ブロック分の授業(午前中に3ブロック、午後に2ブロック)を受けることになる。Week1の月曜日の1時間目からブロック1が始まり、1,2,3,4,5と授業を受ける。次の日の火曜日は、ブロック6から始まり、6,7,8,1,2,と5ブロック分の授業を受けることになる。この流れを木曜日まで繰り返すと、木曜日の5時間目はブロック4で終わる。
そして、翌週の月曜日、つまりWeek2の月曜日はブロック5から始まり、その週の木曜日の5時間目はブロック8で終わることになる。つまり、2週間でどの授業も5回受けられる計算だ。このWeek1とWeek2を繰り返していくという。金曜日はというと、祝日などでなくなってしまった分をうまく計算し、この日はWeek1の月曜日の時間割、この日はWeek2の火曜日の時間割、と決められている。
また、年間の教員の就労時間が決まっているようで、その調整のため金曜日は休みになることも多い。先生たちは、それぞれのブロックに1~8に授業の準備時間も含めて受け持つクラスと教科が決められている。日本では、月曜日が祝日で休みになることが多く、授業時数の不平等がよく生じているため、このやり方は一つの解決策であると感じた。
【アウトドア教育】選択科目の1つにアウトドア教育がある。今まで、学校近くのコミュニティフォレストで焚火をしたり、焚火でホットドックを食べたり、野外遊びをしたり、また、バスに乗ってハイキングに行ったり、釣りに行ったり、ある時は、自転車を持ってきてサイクリングをしたりと様々な活動に同行した。日本でも校外学習や宿泊学習で似たようなことを行うこともあるが、年に数回程度である。時に2ブロック分を使って外に出ることもあるのだが、定期的にこのような活動があることは、大自然がすぐ近くにあるカナダならではの教育である。