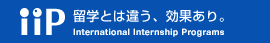2024年6月
現地の中学校では、授業観察をさせてもらうとともに、日本について教える機会をたくさん得ることができた。
実践した授業は、日本語(ひらがな・片仮名・漢字・簡単な挨拶)、相撲(トントン相撲を含む)、日本の伝統衣装(着物・法被・浴衣)、のり巻きの調理実習、昔話や随筆、折り紙(かぶと・手裏剣)、書道、昔遊び、日本の硬貨、仏教と神道、日本の封建制度、歌舞伎、運動会の競技(二人三脚、ムカデ競争、背中渡り、借り物競争)などである。
授業依頼については、まず「こんなことができます!」というリストを自分で作り、メールで先生方に送ってもらった。すると「日本のことを何でもいいから教えて!」といったものから、「社会で中世の日本について学んでいるからそれについて話して!」というような具体的なものまでいろいろと声を掛けてもらった。授業観察をする中で私ができそうなことを見付けては「侍や忍者のことを学習しているんだったら、かぶとや手裏剣を作るのはどう?」というように提案することもあった。当たり前だが、現地の先生方にとっては、私がいなくても授業は成り立つ。だからこそ、どのようにしたら日本人の私を有効に使ってもらえるかをいつも考えていた。授業機会を獲得するために、実践事例を乗せたチラシを作成してメールで送ってもらったり、自分から「こんなことをやりたいんだけど、どうかな?」と売り込みに行ったりもした。待っているだけでは何も起こらない。動き出すには勇気が必要だし、自分を奮い立たせる必要もあった。やはり何かを得るためには自分から行動することが大切である。
日本で児童に教えていたことも大変役に立った。小学校1年生で使った平仮名、片仮名の表を使って日本語を教えたり、漢字の成り立ちをクイズにしてみたり、生活科で昔遊びをやっている児童のビデオを見せてから生徒たちにやらせてみたり、6年生で「枕草子」を指導した際に児童が書いた「わたしの枕草子」を例に挙げてからカナダの生徒たちにも随筆を書かせたり。小学校で教えていることは日本人としてのアイデンティティーを構成する上での大事なことがたくさん含まれているなとも感じた。
私自身、日本についての授業をすることで、改めて豊かな日本の文化や歴史などを見つめ直すことができたし、その素晴らしさに誇りをもつことができた。ここで感じたことを日本の子どもたちにも伝えていきたい。