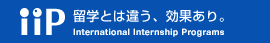2012年6月
3月に満開だったプラムの木々に赤い実がついています。木々の葉が鬱蒼と茂り、雲の流れに時の早さを感じます。相変わらず、6月に入っても雨が多く気温は13度くらいの日々が続いています。6月5日はエリザベス女王の即位60周年祭(Diamond Jubilee)の式典が挙行されました。ロンドンはコンサートやパレードでずいぶん人出があったようです。今は、オリンピックに向けてトーチリレーが各地を走っています。6月18日にハルの町を通過しました。
私は休みを利用して、ヨークにいきました。古く美しい町並みが古代ローマ時代を偲ばせます。町の中心をウーズ川が流れボート観光ツアーが行われています。カンタベリーに次ぐヨーク大聖堂があり、中世の城壁が残存しています。城壁の一角の美しいデザインはabbeyの跡と、知らない人が話してくれました。町の通りにはみやげ物屋が並びます。
さて、先月に続き、リスニングについて少し触れたいと思います。昨年10月、リスニングの小テストの時です。最初の文章が聞き取れなくて、その後、狼狽してしまい、結局、集中できなくなり、小テストはできませんでした。その最初の文章とは、"Let us not to the marriage of true minds admit impediments"テスト後に渡されたスクリプトです。シェイクスピアのテムペストからの引用でした。先生はここは、誰にでもわからないところ、テストでは、軽く流して、その後の文章の意味を掴むことが大切、と言われました。リーディングであれば、前文に戻り何度でも読むことができます。リスニングでは一瞬にして流れる音の連続につけず、あわてふためくと、知っていることも聞き逃して得点になりません。リスニングで大切なことは、語彙の充実を図り、音声に慣れ親しむ方法しか、外に道はありません。外国に暮らしてみて初めてわかることです。日本にいても、英語の音声を親しむ環境をつくれば、当然、リスニングの力を養成することは可能です。
英国ハルでの9ヶ月、沢山の人に出会い、差し入れやプレゼントをもらいました。人との別れはさびしいものがあります。人生には別離はつきもの、といってもやはりさびしいものです。少しの期間でしたが、私の教え子たちが日本語を駆使して国際舞台で活躍されることを祈念して、6月の報告書を終えたいと思います。ありがとうございました。
フィンランドはもう6月から夏休みなので、最後の1週間はテストも終わり授業がありません。時間があるということで授業をさせてもらいました。特に好評だったのが広告で作ったpaper gunでした。作ってからは残りの時間ずっと遊んでいました。Paper gunは1度鳴らすと元に戻さないといけないので、鳴らしては元に戻して~と子供たちが来て、忙しかったですが楽しんでもらえてよかったです。Dog & Catもすごく興味をもってもらえたので、最初に楽しめる折り紙をすると日本文化に興味を持ってもらえるし、子供たちとの距離も近づける気がしました。それから、もう卒業してしまうクラスで折り紙を教えてほしいと言われ、最後の日に折り紙をしました。何を作りたいか聞いたところ圧倒的にポケモンでした。こっちの子供たちは不器用だと聞いていたけど、この学校の生徒たちは結構上手く折っています。ポケモンも時間内に折れたし、他の学年では、あまりトトロは知らないようでしたが、トトロ折ってみたら皆作れました。そして、ポケモンを作っていたら他の先生も教室にやってきて、興味を持ってくれて一緒に折っていました・u・。そして、夏休みに私の子供たちにも教えてほしいと言われました。
その最後の日には伝統的な行事として、卒業生VS 先生でfloor ballというアイスホッケーの土の上でやるバージョンで対決するそうで、私も初めてのスポーツですが先生チームに参加させてもらいました。子供たちは私が出ると私の名前を呼んで応援してくれたので嬉しかったです。途中先生チームが勝っていたんですが結局負けてしまいました。毎年卒業生が勝つそうです。その後先生方がランチルームに集まってケーキを食べながら、休暇に入る先生にお花を渡したりしました。そのときに校長先生と教頭先生にお花を渡すので、サムライヘルメットをかぶせてあげてはどうかと言われ作って用意しました。そしてかぶせてあげると笑いがおきました。他の先生にもサムライヘルメットを披露することができた良い機会でした。
こちらでは終業式と卒業式が土曜日に一緒に行われます。私も見に行きました。そこでは各クラスそれぞれ練習していた歌やダンス、劇などが行われ、最後に卒業生に先生から1人ずつ花を渡すというものでした。日本とは全然違っていて、こういう式は見ていて楽しくていいなぁと思いました。そして私は仲良くなった子供たちから「Have a nice summer」と書かれた手紙をもらいました。2か月ちょっと子供たちに会えないのは寂しいけど、長い夏休みを楽しもうと思います。日本とは全く違う学校の習慣を体験できて、とてもよい経験でした。
今月は6年生と3年生のクラスに入りました。毎日授業を参観しているのですが、丸付けをしたり、わからない生徒にやり方を教えたりと少しずつできることが増えてきました。しかし、教えても『いや!そのやり方は違うよ!』と信じてもらえないこともありますが・・・。それもまた新鮮な体験です。
6年生には習字の授業をしました。日本語には3種類の文字があることを伝えた後、『友』という字を書きました。初めての墨に緊張していたようで、みんな集中して取り組んでいました。はらいもなかなか上手でした。
3年生には新聞紙で作る三角でっぽうを教えました。一か所難しい折り方がありますが、できた後は教室中『パンパン』とよく鳴らしていました。次の日、さらに黙々と作っている子がいて嬉しかったです。
英語で授業をするのはまだまだ難しいですが、担任の先生や子供達に助けられながら進めています。
"What do you want?"と突然聞かれることが多々あります。
「どっちでも。あなたに合わせるわ」と何度か言ったことがありますが、即却下されました。「みんな」という意識が強く、「和」を何よりも大切にする日本人には「私は○○したい/したくない。」というのは、強すぎる表現に感じられます。
でも、はっきりと自分がどうしたいのか、どうしたくないのか、常に意識してすぐに相手に伝えられるとコミュニケーションがスムーズにとれると思います。
6月の中旬で年度が終了し、年度末は様々な行事(修了式・卒業式・卒業パーティー等)がたくさんあり、日本との違いを知るとても良い機会になりました。
もっとも驚いたのは、修了式自体が生徒を表彰する場であるということです。色々な教科や活動の中で活躍した生徒や成績優秀者など、本当に多岐にわたって様々な表彰がされていました。時間も長かったです。しかし、こうして表彰されること自体は生徒たちにとっては誇らしいことであり、日常の活動を頑張っていくモチベーションの1つになっているのだろうな、ということを感じました。
また、高校の卒業パーティーでは卒業生はみな驚くぐらいの豪華なドレスを着て、パーティーに参加します。お祝いの雰囲気としては日本の成人式を祝う感じに似ていたと思います。『高校を卒業すると、大人の仲間入り』そんな雰囲気の伝わってくるパーティーでした。
最近はやっと語学学校に行き始め次の日に早速子ども達に習ったことを使っています。すると、発音に厳しい子どもたちが必死にデンマーク語を教えてくれるので上達するのも早い気がします。自分のために単語カードまで作ってくれました。なかなか懐いてこなかった生徒も私がデンマーク語を話し出したら、教えてあげなきゃ!と話してくれるようになりました。スポーツデイではなかなか絡むことの少ない上級生ともスポーツを通じてやっと仲良くなることができ、下級生は英語が通じないので上級生が助けてくれるようになりました。
ホストファミリーはとても親切で何でも教えてれますし、日本にすごく興味を持っていて政治や歴史など色んなことを食事中等に話しています。ホストファザーがオーストラリア人なので英語もデンマーク語も教えてれますし、デンマーク語の難しさを知っているので色々アドバイスもしてもらえます。
デンマークの学校はもうすぐ夏休みです。この間に自分の言語スキルの向上や教案を見直そうと思っています。夏休み明けの学校が今からとても楽しみです。
日本語能力試験に向けての文法・漢字など通常の内容のほか、受講生が飽きないように工夫をします。たとえば、会話の練習の中で、一人ひとりに1分間スピーチをしてもらったり、日本のケータイ電話について説明した後、電話でのやりとりを演じてもらったり。習った文法を使って伝言ゲームなどもしました。「もしもし」という言葉はかなり面白がられます。ときどき習字や折り紙もやりますが、相手は大人なのであまり子どもっぽくならないように気をつけます。
また、日本語能力試験N2・N1は、こちらも予習が必要なレベルです。類語辞典や国語辞書つきの電子辞書があると便利です。