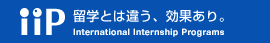研修校の冬の行事として、中学校ではウィンタースポーツを楽しむ一日があった。スキー、スケート、アイスホッケー、ダンスなど12種類のアクティビティから1つを選んで参加する。私はTurkuからバスで3時間ほどのところにあるHimosというスキー場まで出かける日帰り旅行に参加させてもらった。3台の貸切バスに150人ほどの生徒が乗り、私を含めて5人の教員が引率した。ほとんどの生徒が自分のスキー道具を持参し、11:00から16:00まで滑り放題だった。日ごろからスキーによく出かけている生徒が集まっていたとは言え、斜度35度はある最上級コースを何のためらいもなく滑っていく生徒が多く、スキーのうまさに驚嘆した。日本の勤務校では冬休みに4泊5日でスキー学校を実施しているが、その最上級かそれ以上のレベルの生徒ばかりだった。
気になったのは、引率教員の少なさである。150人の生徒に対して5人では、広いゲレンデに散った生徒の様子に目を配るのは到底無理である。そのあたりの事情を探ってみると、朝7時に出発して夜8時に帰着する長時間の旅行の引率を希望する先生が少ないかららしい。学校や市内の運動施設に行き昼過ぎまでには解放されるコースの方が楽というわけだ。スキーを引率している先生はもともとそれが大好きで、引率のついでにスキーが楽しめるならいいと思って来ているらしい。スキー好きの生徒なら、放っておいても勝手に滑っているから、自分は自分で楽しめるとまで言われた。生徒の安全を第一に考えて、事故のないように手を尽くしたシステムで運営している勤務校のスキー学校と比較すると、大ざっぱで緊張感に欠けると感じてしまった。合宿形式の旅行という発想があまりないフィンランドならではということか。
用意したのは、お好み焼き、人形焼、おせんべい、砂糖菓子、抹茶クッキー、緑茶、お酒(もちろん、勤務時間内には飲めませんが)の7品。
パッケージは日本語表記ばかりなので、事前に、食べ物の名前と原材料を英語で表記したカードを作り、付けておきました。
反応は・・・・・
●噂には聞いていましたが、お好み焼きが、好評。特に、お好み焼きソースの味が好評でした。青のり、かつお節は、お寿司の時の「のり」と同様の反応で、匂いが苦手・・・・という方もちらほら。
●抹茶クッキー、人形焼きは、食べたことのない味だったようですが、意外と好評。抹茶は、クッキーでも、苦味や香りを感じるようでした。
あんこも、「初めて食べたけど、甘くておいしい!」という反応がありました。
●おせんべい、これは、4月当初にお土産で持ってきたので、前にも食べたことがあるということで、好評・・・・のはずが、外側に「のり」が付いているだけで、みなさん、あまり、手を出さず。
●砂糖菓子は、とても細かく、綺麗に作られているものだったので、見た目の美しさに、魅了されていました。味も、なかなか、好評。
●緑茶は、用意しただけで、出す機会がなく。お酒も、勤務時間には飲めないので、反応は後日聞いてみる、ということになりました。
様々な反応でしたが、この経験から、感じたこと。
①日本人は、魚や魚介類・海藻をよく食べる人々。そのためか、その匂いには鈍感。
サーモンやニシンを食べることが好きなフィンランド人でも、その匂いには日本人より敏感で、好まない人もけっこういる。
②食は、素材にしても、味付けにしても、今まで食べたことがあるか否かで、印象が大きく変わる。「食べたことのないものを食べる」ということは、勇気のいること。だから、文化紹介の中で、「食」というのは、身近に実践できるひとつの事柄だけれど、「よい反応のものもあれば、あまりよい反応ではないものもある」ということを心得て、実践すべき。
2月には、中学校で調理実習の機会もいただいたので、これらを心得た上で、臨みたいと思います。
あくまで私自身の感想ですが、もし参考になる面があれば幸いです。
調理実習が4クラス。2時間の間に巻きずし、お好み焼き、お味噌汁、抹茶マフィンを作って食べて片付けるというハードスケジュールでした。中学2年生と3年生のクラスでやったのですが、おもしろいもので中学3年生は割と日本食が口に合う子が多かったのですが、中学2年生はあまり好きじゃなかったみたいです。調理実習のたびに思いますが、こちらの子供たちは毎週調理実習をしていて、男の子も女の子も調理器具の使い方や管理の仕方、料理の作り方をしっかり学べて羨ましいなぁ、と思います。
他には「第二次世界大戦以降の日本の発展」について、1時間授業をしました。久々の英語での授業だったので気分が楽でした。中学2年生の社会の授業だったのですが、先生も英語での授業をとても喜んでくださいました。日々フィンランド語で話すように心がけていますが、英語を忘れかけているので、私にとってもいいリハビリになりました。中学生の中にも英語の得意な子、まったく喋れない子、など色々いるのでつたないながらもフィンランド語を使ってしまうのですが、子供たちのためにも、中学生への授業は英語でやるのがいいのかもしれません。
それにしても社会や宗教、国語の授業をするとき、いかに自分が日本について知らないか、覚えていないのかを痛感させられます。授業の資料を作る中でいろいろ勉強させてもらってます。
12月から始まった3学期は、高校3年生にとって最後の学期となる。春に控える卒業試験に向けて、2月から学校の授業はなくなるためだ。理数系の教科では試験に向けた総まとめとなる問題演習の授業があり、高校の全範囲を知ることができるので参加している。化学の演習授業では、日本のセンター試験や勤務校の理工学部・医学部の試験問題を英訳して解いてもらうことになった。フィンランドでは試験の際にデータや公式の集まった指定参考書を持ち込めることや、各問題の配点が10点と決まっているので、日本の難関大学で出題されるような総合問題は少ない。ある実験について反応物と生成物から化学反応式を完成させ、物質量の絡んだ計算をしてから、最後にそれらを説明する記述問題が含まれるのが特徴である。化学の先生と相談して難易度を調整しているが、いくつかの知識を総合して考えるタイプの問題をどう解くのか、その様子を観察したい。
高校での授業が少なくなった分、中学の理科の授業にも多く参加できるようになった。中学3年生の地学の授業では、フィンランドの気候について学んだばかりということで、日本の気候について2時間の授業をした。季節風と山脈の影響で冬には特に太平洋側と日本海側ではっきりした違いが出ることは、スカンジナビア半島のノルウェー側とスウェーデン・フィンランド側の気候の違いと似ており、理解しやすいようだった。
冬休みは北極圏のラップランドで過ごした。一日中太陽が昇らないとは言え、地平線に近づいた太陽の光が漏れ出てくるので、12時前後の3時間くらいは意外と明るくなる。本物のサンタに会い、トナカイソリやクロスカントリースキーを体験し、死ぬまでに一度は見たいと思っていたオーロラも見えた。写真やテレビで見るようなダイナミックなものではなかったが、地球と宇宙の神秘が感じられて、寒さも忘れてしまうほどだった。
クリスマスモードが漂い、子どもはサンタの帽子をかぶり大人も赤い服や小物をさり気なく身にまとっていました。フィンランド人はみんなクリスマスが好きなんだなあとハッピーは雰囲気を私も一緒に楽しむことができました。
「ピックヨウル=小さなクリスマスパーティー」を生徒たち、そして先生方と共に参加させていただきました。
赤ワインを飲みながら、普段あまり会話をしない先生とも心を通じ合うことができて、今まで自分がここで過ごしてきた時間が前向きなものであったと思えました。
そして生徒にクリスマスプレゼントにお花をもらいました。手作りの紙のお家の作品も一緒に。言葉が不自由な今の私にとって、子どものピュアな気持ちがとても嬉しく、心に響きました。
人に物を贈ることの本当の意味は、気持ちを伝えることなんだなあと4歳の小さな女の子が教えてくれました。
クリスマスイヴに姉が日本から遊びにきて、年越しまで共に過ごしました。校長先生が気遣ってくれ、クリスマスに親戚が集う中私たちをお家に招いてくださいました。
ホストファミリーとも、姉が持ってきた日本食を一緒に食べ、楽しい時間を過ごしました。
姉にとって、今までの海外旅行とは違う貴重な体験ができたと喜んでいました。
授業では、いろんなクラスで折り紙でモミの木を作りました。仕上がりが立体的にできあがるので、みんな気に入っていて、食堂のおばちゃんやお掃除のおばちゃんたちにも教えて一緒に楽しみました。また中学3年生の女の子たちに剣道の授業もしました。先生がいないなか一人ぼっちで2時間の授業。みんな恥ずかしがって最初はなかなかうまくいきませんでしたが、今まで彼女たちの授業に一緒に生徒として参加したりしていたおかげでもともと仲はよかったので、途中からはみんな楽しんでくれていたようでした。こちらの人にとって、棒で人をたたくということに抵抗があるようでしたが、最後には私が防具をつけて、彼女たちに竹刀を渡して「面・小手・胴、どこでも好きなとこ打っていいよ」って言ったら、恥ずかしがりながらも「じゃあ面で」といったようにちゃんと自分の意見を言って稽古していました。翌週には雑誌で見つけた剣道のページを一人の生徒が私にプレゼントしてくれてうれしかったです。
また近所の知的障害者の作業所にもお邪魔して、日本のことについて話したり、写真を見せたり、みんなで新聞紙でかぶとを作ったりしました。30人ほどの大きなグループでしたが、いつもと変わらず楽しく授業できました。
フィンランドではピックヨウルと言ってクリスマスの前、11月後半からパーティーをしてお祝いをする習慣があります。私も3回ほど行かせていただきましたが、ダンスあり、クリスマス料理ありの素敵な時間でした。日本とは違って1か月くらい前からみんな今か今かとクリスマスを待ちわびている様子は新鮮です。
独立記念日には学校で中学生のダンスパーティーがあり、事前の体育の授業ではワルツなどダンスの練習をしました。日本ではめったに踊ることがないので、私も一緒に習いました。本番のダンスパーティーでは立派に男の子が女の子をリードして踊っていました。私も生徒の一人と踊ったのですが、曲が終わった後もエスコートしてくれてすっかり感心してしまいました。
学校外の活動では、すでに定年退職されている元進路指導の先生にプーッコと呼ばれるナイフづくりを体験させてもらいました。7回ほど先生宅に通い、計10時間ほどで見事なナイフが完成しました。学校でカンテレを作ったりしていたので機械にはだいぶ慣れてはいたものの、さすがに指の3ミリ先を電動のこぎりが通過するときは緊張しました。自分へのクリスマスプレゼント、色んな方のご厚意によって無事完成しました。感謝感謝です。
明日はいよいよクリスマス。フィンランドでは24日にお祝いをするそうです。サンタさんも夕方やってくるそうです。楽しみ!
いろいろやりたいと思ったことを、訪ねたりしていかなければ何も出来ずに終わってしまうかもしれません。いかに時間を有効に使っていくかを考える必要があると思います。教育方法を学ぶにしても、教育制度を学ぶにしても早くやるべきことを見つけて行くことが大切だと感じました。
一人ひとりが道具を持てるよう、日本の勤務校で引き取り手のいなくなった書道道具を集めてもらい、研修校に送っておいた。授業では、筆を使った基本点画の書き方を順番に説明し、それらの組み合わせで書ける「土」「人」「光」を練習して清書した。字のバランス分析通りに筆を運ぶのは初めてでは難しく、お手本通りの字形にならないことが多いが、総じて楽しんでいるようだった。しかしながら、精神を集中して字を美しく書くために、同じ字を繰り返し練習することはあまり魅力的ではないらしい。2, 3度練習してすぐ書き終えてしまい、早く次の字を書きたそうにしている。文化紹介の一つだからと割り切ってはいるが、筆を持って字を書けばそれが書道だと思われるのは何とも残念である。美しく書くために練習する、という視点を理解してもらえるような授業の工夫を考えようと思う。
取材では、フィンランドへ研修に来た経緯、主な活動内容、日本とフィンランドの教育の共通点や相違点について話題を提供した。私は日本の勤務校で理科教諭として5年間教壇に立ったあと、フィンランドの理科教育を学び実践することを主な目的として、1年間の研究休暇を得ている。取材を受けた編集者は、このことを正しく理解してくれたし、中高の校長からも、専門の理科を教えつつ日本研究の授業も行っている様子についてコメントをしてもらえた。研修の目的を理解し、専門性を活かした活動をできるよう配慮してもらえる学校に来ることができて、本当によかったと思っている。
11月半ばに、カナリア諸島で行われる天体観測へ生徒を引率する物理の先生に変わって、1週間授業を担当した。振り子の周期を精密に測定し、重力加速度を求める実験を行い、データのグラフ化と分析方法を教えた。実験後には、レポートを作成する。日本では毎週のように実験とレポート作成をセットで行っていたので、最も得意とする内容であった。しかし、毎週レポートを書くことが習慣になっている生徒と比べると、提出された報告書の内容は十分と言えず、日々の積み重ねが科学的な表現力養成にも重要だと改めて思った。
お寿司は必ずといってよいほど求められるのですが、残念ながら好き嫌いがはっきり分かれる料理です。(特に海苔への抵抗が強い)フィンランドの子供たちは海苔をおいしいといって食べてくれましたが...そこで、こちらでも手軽に作れてハズレなくおいしいと言ってもらえるお好み焼きも一緒に作りました。作る工程も楽しいし、小麦粉、キャベツ、たまご、ベーコン、コーン、えびなど、材料も簡単に手に入るものばかり。ソースはブラウンソース(HPというブランドのは手に入りやすいはず)、ケチャップ、マヨネーズを混ぜればできます。老若男女、おいしい!!と大絶賛でした。お寿司より鉄板料理だと思います。
1年生~6年生がいるので、言葉は私が英語で話し、6年生がフィンランド語に訳しながら進めています。(徐々に私の話すフィンランド語も増えてきてはいますが・・・。)6年生は、他にもたくさんお手伝いをしてくれて、とても助かっています。
先日は、前半に象形文字の漢字(今回は木、川、目、日、火、手の6つを取り上げました)の成り立ちを紹介、後半はそれらの漢字を筆(習字)で書くことに挑戦。とっても楽しんで、何枚も書いている子もいました。
以前、5年生の授業で習字に挑戦した時、筆順や筆の運び方等、うまく伝えられず、文字もかすれたり墨汁がつきすぎたり・・・・・なんだか思ったようにいかなくて、難しいなぁと思いました。でもよく考えたら、そんなにすぐに、筆の運び方が分かってできたり、お手本のような字を書けたりするはずがないのです。「習字の基本の書き方を伝えること、お手本のような字を書くこと」よりも、「漢字の成り立ちの面白さに気づいたり、筆で書く体験を楽しんだりしてもらおう」という目的に代えた途端、なんだか気持ちも軽くなりました。
「日本文化を伝える」というと、それについての情報をくまなく伝えなくては、大それたことをしなくては・・・・・と、肩に力が入ることもありますが、興味をもってもらったり、楽しんでもらったりすることに重点を置いて、自分自身楽しむことも重要だと思うことができました。
父の日明けの今日、1年生の女の子が廊下で会ったとき「お父さん、すごく喜んでくれた!ありがとう!」って言ってぎゅっとハグしてくれました。すっごくうれしかった!!!
このTシャツは大人気で、いろんなクラスで父の日のカードを作りました。小学6年生ともなると他の紙を切ってネクタイを作ったり、ボタンを付けたり。お父さんはいつもオレンジ色の作業服を着てるから、って言ってオレンジの紙で作る女の子や、ポケットに携帯電話や懐中時計を描く男の子。みんなお父さんのこと、よく見てるなぁ、って感心させられました。
近所の学校でも作ったのですが、その時は1年生と5年生がペアになって、5年生が1年生を助けながら授業を進められたので、人数は多くてちょっと大変でしたがとても有意義な授業になりました。
理数系の授業については特に、15人程度の少人数にすることで、生徒と問答をするように授業を進めることができる。個々の理解度の差を把握し、問題演習では別々の内容を同時進行することが可能になる。実験についても、同時にたくさんのグループに対して器材や試薬を準備する必要がない。
国家による検定なしに作られた教科書が、もう一つの重要な制度的違いである。日本の場合、近年は「発展」と呼ばれる指導要領を超えた内容が一部で認められてはいるものの、依然として定量的な理解を深めるような内容は不十分である。その結果、特に中学段階では単なる暗記に走らざるを得ないような学習内容となってしまう。一方フィンランドでは、必要な専門用語を包み隠さず使って丁寧に解説した教科書を使っている。加えて、豊富な問題演習が含まれているので、教科書を読んで関連する問題も解くことで自学自習が可能である。
学校の役割についても、ずいぶんと違う。フィンランドでは、学校は勉強する場所である、という認識が生徒・教員・保護者に共有されているように思う。放課後の部活もなく、学年全体での宿泊行事もなく、入学式や始業式などの式典もない。派手さはないが、むしろ生徒は知的好奇心を満たすことで、学ぶことそのものを楽しんでいるように見える。教員もプロ意識の高い人が多く、生徒のために何が大切かを常に考えている。保護者も学校の方針に文句を言う人はほとんどいないし、学校に勉強以上の何かを求めないようだ。日本では、勉強するとともに、部活などで上下左右の人間関係を学び、宿泊行事や式典で連帯意識を醸成することも学校の役割である。
このほか、私立学校と公立学校の違い、習い事や塾の存在、教員の社会的立場など豊富な話題を提供し、活発に議論ができた。講演後は、家庭科室で日本の家庭料理を全員で作り、こちらも好評だった。
授業は、アート(日本で言う図工)の時間にクラスに入り、日本文化紹介を兼ねた内容をすることが多いです。折り紙の他にも、習字で日本の「日」とフィンランドの「芬」を書いたり、日本のアニメやキャラクターの紹介(フィンランドのムーミンが日本で有名なことも話しました)、日本の服(日常服と着物や浴衣など)、日本の音楽(楽器や童謡)等々実践しました。
授業内容を考え準備することは、簡単なことではありませんが、自分の中で日本のことを再認識する、よい機会になっていると感じています。何より、子供たちや先生が喜んでくれることが嬉しく、励みになっています。
日本の勤務校が9月から新学期になったので、5月に引き続きSkypeを利用した遠隔授業も行った。前回は十分に準備する時間がとれなかったので、今回は授業3回分をあてて、グループごとにフィンランドを別々の視点から発表する準備をした。各自の自己紹介は学んだばかりの日本語を使い、名前もカタカナで紙に書いて、カメラに写した。サンタクロース、冬のスポーツ、食べ物と飲み物、音楽、サウナ、ムーミンのテーマで資料を作り、カメラに写しながら発表した。日本側からは様々な質問が出て、前回よりも和やかな雰囲気で進めることができた。
物理の授業では、グループごとに簡易モーターを作って回転の原理を考えたり、発電機の仕組みについて説明し、原発事故についても取り上げた。化学の授業では、有機化合物の構造異性体を分子模型と構造式から考える演習を行った。物理の内容は日本と大差ないが、化学については日本よりも詳しく細かい概念まで扱っていた。特に、原子の電子配置をs,p,d,f軌道に分けて説明し、混成軌道による結合角の違いまで扱っているのは、日本の理工系大学1年レベルに相当する。物質がなぜその性質を持つのか、なぜ反応が起こるのか、という化学の根本を電子の動きできちんと説明しようとする姿勢がうかがえる。一方で、授業の進め方を見ていると、実験に使う器具をその場で準備したり、授業が始まってからICT機器の設営をするなど、無駄が多いと感じられる場面がある。その間、生徒も友達としゃべっていたり携帯をいじっているなど、せっかくの貴重な授業時間が失われているのは、個人的に残念である。フィンランド特有の余裕ということなのだろう。
クラブではまず、浴衣を着た姿を見せた後、希望する子に浴衣を着せてみました。みんな、くすくす笑いながら試着。気恥ずかしい時に出るような、照れ隠しの笑い?のようでした。着終わった子にカメラを向けると、素敵な笑顔になり、喜んでくれているようでした。
その他に、映画「TOTORO」を何週かに分けて鑑賞しました。ところどころで笑いが起こり、楽しそうに観ていました。映画「TOTORO」は、かわいくてストーリーが子供も面白く感じるのはもちろんのこと、日本家屋やランドセルをしょった小学生、お弁当に日本のおばあちゃん・・・等々、日本の暮らしを伝えるにも適したアニメです。私は個人的にもトトロが大好きなので、フィンランドの子供たちにも好んでもらえて嬉しかったです!
内容としては、玉ねぎの皮とみょうばんを使った絞り染めを木綿タオルやトートバッグを使ってしたり、盆踊りの紹介の後に「炭坑節」をみんなで踊ったり、はっぴを着てもらい雰囲気を体験してもらったり、一緒にカレー作りをしたりしました。
自由遊びの間は、「ぐりとぐらのかいすいよく」を子どもたちに読み聞かせ、その流れで近くの海辺まで水遊びに行ったり、折り紙遊びをしたりしました。
・8月は中旬から新学期が始まるので、前半は子どもたちも半分程度の登園でした。
他の先生が子どもたちを見てくれている間は、昼寝用のベッドのシーツを換えたり、廊下の壁飾りを新しいものへと取り換えたりして、気づいたところの手伝いをしていきました。
フィンランドの先生がゆかりおにぎりを美味しい!お茶のような味がする。と言って食べてくれたのは本当に嬉しかったです。
音楽の週には子どもが幼稚園の絵本の棚から見つけてきた英語の歌(絵本になっていて最後のページに楽譜がついている)one light one sun という歌をうたいました。日本語の歌も考えていたのですが子どもが「これどんなの?」と聞いてきたのと、新学期がはじまり入園間もない子もいたので私がいなくなってからも継続出来るものがよいと思いこの歌を歌おうと思いました。私も今回初めて知った曲ですがとってもステキな歌です。
お別れパーティーの前日には子ども達と先生で、私のリクエストしたチョコレートケーキを作ってくれました。ケーキ作りの最中に2、3歳の子がケーキの材料のバナナを食べてしまうという笑ってしまうような事もあり小さい子は本当に世界共通だと感じる事が随所にあります。
最終日には卒園した子も会いに来てくれたり、入園間もない子からもプレゼントを頂いたり本当にあたたかいみなさんに恵まれて1年を過ごす事ができたなと、感謝の気持ちでいっぱいでした。
幼稚園の年齢の子達でもちょっとでも日本に関係のありそうなことだと「見て!日本!」と言って張り切って見せてくれていたので(例えば、動物図鑑に載っている柴犬とか、日本語だと思っていたエジプトの文字とか)小さい遠い国の日本に関心を持ってくれて本当に有難いなあ。と思うばかりです。
そして、折り紙と寿司が本当に喜ばれる物であったことを改めて知る事ができました。
皆さんに出会えた事に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
まず、日本の夏休みについて、「35度以上になる日もあって、湿度の高い、暑い毎日。」「約40日。」「宿題があって、勉強もする。」と話すと、予想以上の反応。口々に話していたことの詳細まではわかりませんでしたが、「夏休みなのにー!?」と言っていたのはわかりました。「フィンランドの夏はいいね。」と付け足すと、静かになって、みんな納得したのかな、という感じでした。
次に、花火と盆踊りの写真を見せながら、夏祭りを紹介。(ここフィンランドでも、夏になると、中高年の方々を中心に、民族衣装を着て湖の近くに集まり、タンゴ等のダンスを踊る習慣があります。)
そして、メインは、七夕について。笹の葉は手に入らないので、笹の見本を見せた後、代わりに木を使用して、飾り付け。折り紙に切き込みを入れて作る「あみ飾り」と願いをかいた短冊を飾って楽しみました。5年生の子供たち、けっこう本気で願い事を考え、短冊を書いていました。季節外れですが、思いの外、反応がよかったので、安心しました。
今学期から、月に1回ほど全校集会で話す機会をいただいきました。ちょうど、来週に担当する日があるので、授業をしていないクラスにも七夕を紹介して呼びかけ、もっと短冊が集まればいいかなぁと思います。
まず、6月末から7月にかけて、フランスの友人とイギリスの恩師を訪ねて2週間の旅をした。フランスでは、高校時代の短期留学で知り合った友人と9年ぶりに再会し、彼の住むフランスの田舎町でのんびりとした生活を満喫した。特に、近くの農場まで森の中を歩き、風に揺れる小麦畑を眺めながらのピクニックランチは最高だった。また、以前にホームステイで受け入れたフランス人の家も訪れ、大都会の住宅地での生活も味わった。ユーロスターでイギリスへわたり、短期留学でお世話になった先生との再会も果たした。自身の目を海外へ向け続けるのに大きな影響を与えたイギリスでの日々を思い出し、当時思い描いた将来像と今の自分がどう近づいたのか、何がまだ足りないのか、など、これまでを振り返ることのできる充実した旅となった。
フィンランドへ戻り、日本からの友人の訪問を受けたり、家族を案内したりして、主にHelsinkiとTurkuを観光した。その後7月末から8月にかけて、鉄道を使ってドイツとチェコを旅行した。伝統料理を味わったり、ノイシュバンシュタイン城やプラハの街並みの美しさに感動したりして、ヨーロッパの長い歴史を感じることのできる旅となった。
8月16日から、新学期が始まる。週に計5コマ、中学と高校で授業を担当することになっているので、現在はその準備をしながら過ごしている。また、実験を主体とした理科の授業も、進度に合わせて行ってゆくことになっている。
保育園の子供たちは、英語が全く通じないので、フィンランド語で...と言いたいところですが、私の語学力不足のため、ほとんど身振り手振りでコミュニケーションをとりました。折り紙で折ったものをあげたり、一緒に折って遊んだりしました。中には4歳になったばかり、という子も折り紙に挑戦してくれました。特に、コップを作って本当に水を入れて飲んだ時の子供たちの笑顔がとても素晴らしかったです。
今回、劇や卒園式、歌と全ての伴奏をまかされました。良い経験でした。
また、劇でつかう大道具、小道具なども先生たちと作りました。そういう準備などは日本と似ていて、今までの経験が役に立ったと思います。
言葉の壁はありますが制作や音楽など言葉を使わない所では日本での経験が役に立ちます。
また、真夏の卒園式も初めての経験でしたが季節も国もちがいますが子どもを送り出す気持ちはどこでも同じだということがしみじみと伝わりました。
卒園証書に私の名前も漢字でサインしました。保護者の方々も温かい言葉をかけて下さり、本当に良い経験をさせて頂いていると思っています。すべてよい思い出です。
学年末の前日には、ほとんどの生徒が教会に集まり、夏を迎える前の礼拝が行われた。
終業式は、日本の学校のような儀式的な雰囲気は一切なく、ボランティアの生徒が司会をし、音楽やコントなどのパフォーマンスをしたり、この一年に活躍した生徒へメダルを送ったり、代表生徒が宣誓したりするなど、夏休みを待ちきれない生徒のエネルギーが伝わってきた。
卒業式は、一転して厳かな式典だった。卒業生一人ひとりが壇上に上がり、校長から卒業証書を受け取った後、担任から白い帽子を被せてもらう。この帽子はFinland人にとって大切なもので、高校卒業の証であるとともに、毎年5月1日のVappuの時のみ、昔の帽子を出して被ることができる。町中が白い帽子を被った人で埋め尽くされる様子は、圧巻である。
学年末が慌ただしく過ぎた後、中高の先生たちと一緒に小型船を貸し切って、Turku沖のArchipelagoのクルージングに参加した。毎年恒例となっているイベントのようで、20人以上の先生が参加し、これまで接点の少なかった先生とも仲良くなることができた。クルージングのあとは、ある先生のサマーコテージに上陸し、サウナに入ったり海で泳いだりして楽しんだ。サウナから出て冷たい海に飛び込むと聞いて心配していたが、実際にやってみると意外と気持ちのいいものだと感じた。先生同士がまるで家族のように仲が良く、その証拠にサウナにも男女一緒に入る。最初は驚いたが、サウナを通したコミュニケーションがFinland人にとってどれほど大切か聞いているうちに納得した。
夏休みに入ったので、まず2週間ほど日本に一時帰国をし、家族や友達と会ったり勤務校を訪れたりした。8月から中学と高校で日本に関する授業を週5コマ受け持つことになったので、その教材集めもした。夏休みの間は、地の利を生かしてヨーロッパ各国を旅行して回ることにしている。
フィンランドには独自の文字、Finアルファベット(アルファベットの上に点々がついたりする)があり、発音の仕方も英語とは異なる(ABCはアーベーセー)。また、フィンランド語にはシャシュショやザジズゼゾなどの発音がないため、練習しなくてはならない。しかし、英語に共通する点が多いため、平仮名、片仮名、漢字という全く異なる文字を使っている日本の子ども達よりも、英語にはなじみやすいだろう。
授業内容としては、例えば、4年生の授業(週4時間)では、最初に How are you? What's up? What day is it? What's the weather outside? What time did the school start? What time will the school end? など毎回同じ質問を1人ずつ答えている。教科書は、リーディング用、問題集用と2つの教科書があり、教師用指導書にはワークシートや掲示用のイラストやカード、単元末のテストなど、あらゆるものがつまっている。
また、教科書に合わせたCDもあり授業で使うことも多い。基本的に教科書に準じて授業を行い、宿題も何ページまでと告げられる。参観した授業では、教科書に出てきたbig・pigの発音の違いを口の前に紙をもたせて練習していた。また、単語テストが日本の漢字テストのようにあり、単元ごとのテストもある。テストでは、リスニングや英作文の問題もある。
5月9日に、日本での勤務先の私立中学校とFinlandの研修校との間をSkypeでつないで、遠隔授業を行った。日本からは中学2年生が23名、Finlandからは物理の授業グループを中心に高校生が26名参加した。時差が日本から見て-6時間なので、Finlandは始業後しばらく経った9時過ぎ、日本は放課後の15時過ぎに授業を始めた。
初めに時計を見せ合って、画面に映った相手の時間帯が異なることを確認した。東西に8000km以上離れたところに相手がいるという実感を持ってもらおうと考えたからである。次に参加者全員が一人ずつ画面の前で自己紹介した。Finlandの生徒は学習歴も長いために上手に英語を話す生徒が多いが、日本の生徒は英語を習い立てで、名前と年齢を典型文で説明する以上に話すのは難しいようだった。一部の生徒が相手の国の言葉で自己紹介すると、拍手も大きく親近感を感じているようだった。
日本の生徒は、昨年まで私が教えていたのでリラックスしていたが、Finlandの生徒はまだ馴染みが薄く、日本の生徒たちの一体感を見て、やや引いてしまっているように見えた。日本の学校には制服や校歌があるがFinlandではどうか、最近の気温や日照時間の違いについてなど、日本からは盛んに質問が出た。一方で、よく言われるようにFinlandの生徒はとてもシャイで、事前に質問を考えておくよう指示していたにも関わらず、一部の生徒が回答するばかりで逆に質問するような展開にならなかったのが残念であった。通常授業の制約があったので難しかったが、事前に参加予定の生徒を集めて準備できれば、もう少し盛り上がったのかもしれない。
普段の授業では、物理の時間に実験を交えた授業を数回担当した。試験管を使った気柱共鳴の実験と理論の解説、凸レンズ・凹レンズによる像のでき方とレンズの公式による計算、充電したコンデンサーの電位差を利用して教室の生徒全員を感電させる「百人おどし」などを行った。日本の勤務校のように生徒一人一人に実験させるだけの器材が揃わないので演示実験が主体であるが、実験結果を生徒たちとディスカッションして確認しながら次のステップに進めるので、理解度を把握しやすいと思う。実験の準備をしながら担当の先生と話すことで、互いの実験技術やノウハウを共有することができ、秋学期以降も引き続きいくつかの実験を解説することに決まった。
こちらにきて2か月がたち、シャイな子供たちもだいぶ私に慣れてきたようです。いろいろちょっかいをかけてきたり、遠くからでも「おはよう!」や「またね!」と言ってくれたり、授業をしてても「ゆきこ!」「助けて!」と積極的に声をかけてくれたりと日々の変化がとても楽しくまたとても嬉しいです。日本クラブが発足して、水曜日の放課後には数名の子供たちと一緒に折り紙をしたり、書道をしたりしています。彼らは特に日本に興味を持っていて、すごく積極的にいろんなことを聞いてきます。編みぐるみって共通語なんですね。生徒の一人が編みぐるみを作るのが大好きで、いろいろ作ったものを見せてくれるのですが手先の器用さに毎回びっくりさせられます。
私はこちらに来てから授業に参加して編み物や服作りを生徒たちと一緒に習っています。技術の授業ではフィンランドの神話「カレワラ」に出てくる楽器「カンテレ」を男の子たちに交じって作っています。ギターのように弦を張ってひく楽器のようですがどんなものができあがるのかとても楽しみです。
・4月から段々と行事が増えていき夏に向かっていきます。
フィンランドのイースター(Pa:a:sia:inen)は暦によって毎年日にちがかわり、今年は遅いイースターと言われていて4月の22~25日の間に祝われました。
その期間幼稚園は休日となり、その前にイースターの卵の形の紙にじゃがいもの色スタンプをしたり、イースターの時期に飾られるネコヤナギの枝をモチーフにした制作(麻ひもを枝、指スタンプをネコヤナギの白い部分に見立てる)や、牛乳パックに土とライ麦の種を植え草を育てるという活動をしたりしました。
その一週間前にもPalmusunnuntaiという行事があり、教会へキリスト復活の物語を聞きに行きました。
・5月1日のメーデー(Vappu)に向けて幼稚園でも子どもたちのVappuのイベントが開かれ、子どもたちも仮装をしたり風船や紙テープを飾り付けたりして祝いました。おやつには、Vappuの時期のセットのドーナツとsimaという炭酸ジュースが出ました。
Area Name : Kotka,Finland
Usefull News : ・4月は雪が雨に変わったり、道路も雪解けでドロドロだったりするので耐水性のある上着や、長靴などが活躍します。
傘はフィンランドではあまり使われていませんが(フィンランドの人いわく「面倒くさい」(!)とのことです)、折りたたみの傘があると天候が不安定なこの時期に役に立ちます。
・イースターの一週間前に祝われる"聖日曜日"(Palmusunnuntai)というキリスト教の話に基づいた行事があり、各地で子どもたちが魔女などに仮装して近所の家を周り、飾りつけしたネコヤナギの枝を配る代わりにお菓子をもらうというイベントが行われます。
HelsinkiのエリアにあるSuomenlinnaという世界遺産の島の中でも地元の子どもたちによってそのイベントが行われるので、おすすめです。
・イースターの休日中やフィンランドのメーデー(Vappu)の休日中、いろいろなお店や場所も休みになり、バスなどの交通機関も休日ダイヤになります。HelsinkiのKamppiという場所のスーパーは休日中でも開いていました。
・フィンランドでも学校などで子どもたちが折り紙に親しんでいますが、日本で売られているような折り紙はこちらで売られていないので、自分たちでちょうどいい大きさに切ってから使ったりしています。
なので、折り紙セットや簡単に折れる折り紙の本を何種類か持参すると、いろいろな場所へすぐ日本紹介の材料として持って行けるし、コミュニケーションもとれるのですごく役に立つと思います。
・フィンランドでは病院などでしか、基本マスクが使われていません。街中でマスクをすると、よっぽどの感染症か重病の人と扱われあまりよく思われないそうです。薬局では一応買えるとのことです。
色画用紙で木をつくっておいて、子どもたちと折り紙で桜の花をつくりその枯れ木に自分たちではなを咲かせる(飾る)という活動です。折り紙は好きですし、はさみを使ってカットすると形が変化するというのももの珍しかったのか、楽しんでもらえました。桜の木はそのまま飾ってあるので、毎日少しずつ子どもが作った花が増えていくのも見ていて嬉しいものです。
折り紙の本を見て自分たちで作る子も増えてきました。日本の文字にも、プレスクールの子が興味を持ちだし、自分の名前を書ける子もいます。アルファベットもかきはじめたばかりの子の年齢で日本の文字に興味を持ってもらえるとは有難いかぎりです。
ロヴァニエミ郊外の、大学進学のための高校です。敷地内に中学が隣接しています。
到着した4/1~8の1週間はテスト期間だったため、身体を慣らすことができました。住まいから学校へは徒歩10分、市街中心部へは河を渡って30分弱です。
14日木曜15:05から初回の日本文化コースが始まりました。1回75分で週3回あり、同じ生徒たちと会うので、教材研究に時間がかかりますが、私が生徒に質問して、脱線する事も多いです。大体授業は、用意した全てを消化する事無く次回へ続いてます。
授業案、4月はイースターのウサギにかけて、卯月と干支を紹介し、折り紙もウサギを選びました。女子高生、意外に喜んでます。
「フィンランドの英語教育をスパイしに来た」と冗談で言ったつもりだったのに、真面目な英語の先生たちが、総力を挙げて全授業に参加させてくれています。なので、生徒たちと一緒に英語の授業を受けています。科目毎に内容が異なり、且つ日本の英語の教科書とはやや異なるので、受講していて勉強になります。
私の名字の読み方が、フィンランド語の「大きい」に相当する事から、一気に打ち解けることが出来ました。ビックリ。
Turkuへ到着して2週間が経った。毎日5分くらいずつ日が伸びており、日本との緯度の違いが感じられる。最初の1週間は研修先の高校が試験期間だったため、翌日の試験に備えたPreparation Lessonを見学しつつ、中学校の授業に参加した。主に英語の授業のゲストとして呼ばれ、出発前に考えたFinland語による自己紹介のあと、日本や自分自身に関する質問に答えた。中学3年生にもなるとかなり流暢に英語を話し、こちらの言うことも正確に理解しており、日本の一般的な中学生との差を感じた。校長によると、9歳から英語を学び始めることに加えて、TVで放映される映画にはFinland語の吹き替えがほとんどないため、日常的に英語に触れる機会が多いという。実際にTVを見てみると、確かにFinland語の字幕があり、音声は英語だった。
多かった質問は、やはり日本で起きたばかりの地震・津波・原発事故についてだった。日本で起きた自然災害で最悪のものであること、地震の後も計画停電や物資の不足で今まで通りの生活が送れないことなどを説明した。また、世界中からの心配や応援のメッセージが日本の力になっていると話し、感謝を伝えた。
高校の授業内容は、物理・化学・数学については日本と大きな違いはなかった。ただ、教科書の記述が丁寧で、問題演習も豊富にあり、解説もきちんとついている。自学自習が可能な教科書の作りになっている点で、日本の教科書より優れていると思う。試験前の復習の授業が前日にあるというのも、日本ではあまり聞かない。教師の説明に対して生徒はかなり積極的に質問をしており、教師は考え方のプロセスを複数の視点から説明していた。
次の教員会議で、正式なあいさつをし、合わせて日本との遠隔授業について提案することになった。日本とフィンランドをつないで、互いの紹介だけでなく理科的な視点での交流を目指している。
三月はひなまつり、ということで紙皿と千代紙をつかっておひなさまをつくり飾りました。
ひな壇のようなベンチがあったので、そこにちりめんの和柄の風呂敷を敷きお雛様を飾ると、とてもかわいらしくなりました。ひなあられなどおひなさまのお菓子も少しかざり、ひなまつりパーティーで食べよう、と話すと楽しみになったようです。
実際、パーティーの時はウエハースとゼリービーンズのようなお菓子はすぐ売り切れましたがひなあられはあまり人気がありませんでした。あと、星たべよう、という星型のおせんべいも。ちょっと残念でした。ちらし寿司はソーセージとキュウリと薄焼き卵でトッピング。
巻きずしより子どもたちにはこちらのほうが良かったようです。
またガールスカウトのキャンプでは紙芝居や新聞かぶと、おにぎりづくりなど色々な事を紹介させていただく機会に恵まれました。研修校以外の場でも活動ができる事に感謝です。
現地の方と知り合いになると、このような機会にめぐまれるかと思います。
このごろは折り紙が子どもたちに大人気で自分たちで本をみながら折っている子もでてきて
嬉しく思っています。
剣道の防具を持参してきたので、道着や防具を身につけて授業をしたらみんな興味深々、先生もとても喜んでくれました。武道という枠を超えて、道着の素材について家庭科の先生に質問されたり、意外なところから質問がきてこっちがびっくりさせられました。フィンランドではまだまだ知名度が低いようで、少しでも多くの人に剣道を知ってもらえたらいいなと思っています。
・3月は太陽の日差しも大分まぶしくなりました。日焼けし始めた先生もいます。中旬くらいまでは海の上でもスキーや散歩ができましたが気温が日中1~2度など暖かくなってきたのでニュース経由で海の上を歩く際は気をつけるよう、という注意情報が出ました。
幼稚園の子どもたちもそれ以降は海の上へ出かけないとのことです。
・幼稚園での保護者会や子どもたちの朝の会などで、茶道のお点前の紹介と抹茶、和菓子(いちご大福)をふるまう機会がありました。
抹茶をごく薄めに作ると、子どもたちも飲んでくれ「いいね~」と言ってくれる子もいました。フィンランドでは緑茶などに砂糖を足して飲む人もいて、「強い味だけど、日本の人は抹茶に砂糖入れないの?」という質問もありました。
茶道の道具は日本から持ってきました。抹茶の粉もこちらで売られているのをまだ見かけていないので、日本から送ってもらったものを使いました。米粉、あんこはフィンランドでも買えました。
・3月から4月の始めにかけて幼稚園では"芸術"をテーマにした制作や活動をしていて、私も就学全教育のグループで習字を紹介し子どもたちと一緒に名前を書いたり、2~4歳のグループでは紙の半分に色を塗ったものをもう片側にくっつけて写す、鏡絵(?)のような制作をしました。