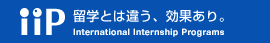日系人が多いハワイでは日本式のスタイルでお正月を迎える方がたくさんいらっしゃることをはじめて知りました。スーパーに行くと門松、お供え餅等のお飾りが並んでおり、食べ物に関してもお雑煮、なますをはじめとするおせち料理があり、日系人のお宅ではハワイスタイルのおせち料理を食べてお正月を迎えるようです。材料が若干ハワイのものに代わっていたりとするようですが、基本は日本のおせち料理と一緒です。
通常の生活から日本食はたくさん食べられてますが、お正月におせち料理を食べる習慣があることにもとても驚きました。
クリスマスに比べると元日はとても静かで穏やかな過ごし方でしたが、お正月にもハワイ独自の文化があることはとても興味深いことでした。
しかったわ。私、家でまた作ってみるわ。」とも言ってくれました。
ただ、ただ、鶴を折るだけの授業なのに、そんな言葉を言ってくれるほど感動してくれていた子どもがいた!!ということは大変な驚きであり、指導者冥利に尽きると思いました。この上ない幸せだと思いました。
私がすなわち、イコール日本人では決してないのだけれど、やはり出逢った目の前のこの日本人の私を通して、子どもたちは、日本とは、日本人とは、日本の文化とは・・・などなどを大げさかもしれないけど一生?イメージ、理解するのだと思います。実際、私がそうでありがちなように・・・。よく考えれば、責任重大です。研修生活もあと残す所2ヶ月となりました。日本の美しいもの、日本の生活、習慣、文化、本当のこと、本当のもの・・・を私の出来る限りの努力と誠心誠意の気持ちで、子どもたちに見せたり、聞かせたり、伝えたりできたらと思います。
一方で冬休み期間中は、クリスマスや正月をHome Stay先の家族と楽しく過ごすことができ、非常に良い経験にもなった。特にクリスマスは、日本での過ごし方と違い、と言うか昔の日本の正月の過ごし方に似ていると感じた。先ずツリーを切りに行くところから始まり、飾り付けをした。その間にどんどん家族・親戚一同が集まって来て、ツリーの下にプレゼント、何十年も前の子供の頃に作ってもらったと言うソックスをいまだに使っていて、その中にもプレゼント。25日の朝は早くから全員が集まって、2時間くらいかけてプレゼントを開けた。夕食にはでっかい七面鳥をみんなで食べて、年末年始はカレンダー通りなので、翌日にみんなそれぞれ帰っていった。私はHome Stay家族の分しかプレゼントを用意しておらず、でも他の人たちは私にもいろいろとプレゼントをくれては、その選んだ理由まで説明してくれて、ありがたいやら、申し訳ないやら、でもうれいいやら... で、本当に楽しい数日間だった。元旦はこちらで日本の事情に詳しい人がいて、一緒に日本的?な正月を過ごした。あとは千羽鶴を何とか完成させて、こちらの人の健康と幸せを祈る旨の短冊を、書初めを兼ねて久し振りに筆で書いて、1月9日に学校に寄贈した。なかなか好評で苦労した甲斐があった。
天気予報ではさすがにそろそろ冬本番となるようで来週にはマイナス30℃の予報となっている。先ずは風邪や事故にあわないように気をつけながら、でもいろんなことに挑戦し続ける姿勢をもっていたい。残り3ヶ月となったが、今一度初心に戻り、有意義な生活を送って行きたいと思う。
校長先生や先生方のご要望により、いくつか行う授業の1つに手巻き寿司の授業を入れることになりました。
生徒の皆さんは、「お寿司を食べたことはあるけど、自分で作って食べたことはない。」と、この授業を楽しんでくれたようです。
材料(1人あたり約5つ食べてもらうことにしました。)
①カルフォルニア米(日本のお米に似ています。1カップで2~3人分)
②ミツカンの寿司酢(アジアンショップで買いました。)
③しょうゆ
④わさび
⑤焼きのり
⑥ごま(好みでかけてもらいました。)
ネタ(野菜)
①レタス
②きゅうり
③アボカド
ネタ
①スモークサーモン
②ゆでた大きなエビ
③チェダーチーズ
④カニかまぼこ
⑤シーチキンのマヨネーズ和え
学校にキッチンがなかったので、ほぼ全てをホストの家で用意して学校に運びました。
寿司飯の作り方と手巻き寿司の巻き方を演示しました。
手巻き寿司の成功の秘訣は、たくさんのごはんやネタを海苔にのせないことだと強調しました。
手巻き寿司の巻き方を演示する前に、You Tubeで英語の良いビデオ教材を見つけたので、それを見せてから、実際にもう一度生徒の皆さんの前で演示しました。
You Tube "How To Make Temaki"
http://www.youtube.com/watch?v=Ii2ja4Nh0Fo&feature=related
授業の最後に、巻き寿司の演示をしてあげられたらもっと良かったと思います。
にぎり寿司や巻き寿司は、作るのにテクニックや道具が必要ですが、手巻き寿司は、誰でも気軽にお寿司作りを楽しめます。
使った食材は、どのお店で入手したのか場所と電話番号なども含めてレシピを作成し、配布しました。もちろん授業で見てもらった手巻き寿司の巻き方のYou Tubeのアドレスも入れました。
特に、料理の授業などは、習ったことが生徒達の普段の生活の中で生きるような配慮を心がけて、これからも授業を考えてみたい思います。
早かった。9月に始まった新学期ですが、もうクリスマス休暇になってしまいました。ハロウィーンなんてつい昨日のような気がします。あの頃は書道でてんてこ舞いでしたが。書道は墨汁不足のため7,8年生が終わった時点でいったん終了。来年、墨汁の残量をにらみながら慎重に再開の予定。12月は、クリスマスの話に絡めて日本の宗教について触れたり、(ちょっと早いですが、終わってからよりいいかなと)正月の話をしたりとテーマには事欠かない月でした。日本のクリスチャンが人口のわずか2%/260万人(Wikipedia)というのは、彼らにとってショッキングな数字だったようです。盛り上がるのは、料理の話ですね。クリスマス・ディナーには各民族の伝統があり、先生の中には、オランダとかポーランドという人もいて、私も勉強になりました。学校では、クリスマス・コンサートに加えて、各クラスでいろんな取り組みをしていて、その手伝いでも忙しい1ヶ月でした。家では、MelとRhondaが連日のラッピング作業。ツリーの下にあふれるギフト、いったい誰に贈るのでしょうか?職場や地域の集まりもあり、大体ポットラッ
クなのでフランス系、ドイツ系、ロシア系+メキシカン、と特色ある料理が楽しめました。ここはドイツ系とロシア系の多いところで、特に40代以上の人には(カナダ生まれでも)第1言語が英語ではない人が多く、言語に関しては寛容な土地柄です。一方、日本との接点は少ないですね。日本料理の食材などもあまりありません。みそもほんだしもそばもなし。巻きずしはできますが、日本風に作ろうとするとかっぱ巻きくらいしかできないと思います。(Melはカルフォルニア・ロールやチキン・ロールを作りますが)学校にはメキシコからの留学生が10名以上いますが、日本の高校生だとホームシックになるんじゃないかと思ったりもします。あらためてカナダとモーデンと日本との違いを思った12月でした。
さて私の現在の活動ですが、学校訪問に加えてハワイ日米協会のメンバー向けのプログラムにもいろいろ参加させてもらっております。一年に数回大きなイベントがあり、年末も近いということで10月から12月の頭に掛けて、かなり大きなイベントが続いてありました。少人数のスタッフで大きなイベントを運営・企画することはなかなか大変で、私もその過程を見つつできる限りのお手伝いをしました。
12月の上旬にはサイレントオークションというイベントがあり、準備期間が大変でしたが今まで経験したことのない楽しい経験をすることができました。出品されるものもかなりバラエティーにとんでいて、日本の骨董品みたいなものから、有名ホテルの宿泊券・ゴルフコースでのプレイ券等々。出品された品物をみているだけでも楽しかったです。
年内の大きな行事も終了し、いよいよクリスマスウィークに突入しました。温かい場所で過ごすクリスマスは初めてなのでとても楽しみにしております。街のイルミネーションやオーナメントもハワイらしい、サーフボードに乗ったサンタ・水着のサンタ等々とても新鮮です。
またお正月も日系人が多いということで、ハワイスタイルのお正月のお祝いがあるようです。そちらも楽しみにしております。また次回報告できればと思います。
会話に自信のない私は、これまで、特にプライベートの時間は、英語のワークを広げて一人で過ごすことが多くありました。「ここカナダに来た意味は何?文法や単語の正確さにとらわれず、もっともっと話さないとね。とにかくただ話すのよ。それから、もっともっと英語を聞くといいわね。私たちと一緒にテレビや映画を見ましょう。」とあたたかいホストはいつも私にアドバイスをくれていました。そんな私の目標は、せめて、「お誘いを断らない。」でした。最近、その目標が実を結びつつあるのを感じています。研修中の学校で「私、青森で英語の先生をしていたの。」という保護者の方に出逢いました。その方のお招きを受けて、先日、ファミリーハロウィーンパーティを一緒に楽しませていただきました。また、学校で知り合ったフランスから来たフランス語の先生と一緒に映画を見に行ったら、そのお友達の大学で移民の方に英語を教える先生(ESL)の先生に出逢いました。今日は、研修中の学校がたまたまお休みだったので、その先生の授業を受けに大学を訪問させていただきました。そこでは、様々な理由でカナダにやってきた、インドや中国、ベトナム、チリ、グアテマラの方々に出逢い、一緒に楽しく英語を勉強させていただきました。その先生に教わった英会話力アップのために薦めたいこととは、①「たくさんのメロドラマか映画を見ること。できたら毎日一本。(※メロドラマの方が、生活に密着しているからできたらメロドラマがいいそうです。)」②「英語の歌を聴くこと。」③「できるだけたくさんの人とお話しすること。」です。ホストのアドバイスと全く同じでした。①については、幸いホストがたくさんのDVDを持っているので今はそれを毎晩借りて見ています。ドラマは、テレビでホストと一緒に見ています。②については、大好きなジブリソングを英語で聞いています。先生は、また、私の英語のレベルに合った本も紹介してくれました。「The No1 Ladies Detective Agency」です。早速、図書館に行ってこの本を探してみたいと思っています。改めて"人との出逢いが英会話力アップの鍵であり、人生の宝物"だなあ~と思う今日この頃です。次なる私の目標は、「自分からお誘いしてみる。」です。私にできる皆さんに喜んでいただけそうなこと、例えば、手巻き寿司の作り方を教える(私がカナダで出逢ったほとんどの人がお寿司が好きと言ってくれます。)などで、もっともっと出逢いを広げて行こうと思います。
とうとう雪が積もりました。2日ぐらい前からグっと冷え込んだので案の定です。でも、例年と比べると遅い雪だそうです。気温の方は、先週ぐらいから最高気温が0度を下回っています。雪が積もる前から真冬日というのは、北海道出身の私にとっても予想外でした。予報では、今週末は-20度くらいまで下がり、風も強そうです。でも、子供は元気ですね。こちらの学校は、午前と午後に15分のrecess、ランチの後に25分の休みがあり、雨の日以外は、子供たちは外で遊ぶことになっています。寒くなったので、オーバー、帽子、マフラーをしっかり着用していますが、寒くなればなるほど子供たちの元気度はアップしています。でも、これは小学生の話。ミドル・スクールでは、Grade7-8の生徒が廊下にあふれています。授業の準備があるとかなんとか言って外に行こうとはしません。9月までは、人影はあまりなかったのですが。
今日は18日金曜日ですが学校は休みです。このところ、先生方の研修やらミーティング(?)やら祝日(Remembrance Day) やらで5週続けて金曜日が休みでした。(先生方は祝日以外は休みではないのですが。)今週末は今年最後の3連休、エンジョイしようと思います。ホスト・ファミリーは、私の誕生パーティーをしてくれるようですし。
11日はRemembrance Day で、学校では、前日の10日に、退役軍人の方も列席してセレモニーがありました。この日は第1次世界大戦の停戦日です。イギリス系や欧米の多くの国がこの日を戦死者を悼み平和を祈念する日としていることを、今回初めて知りました。日本では8月15日は夏休み中です。日本でも取り入れたらどうだろうかなどと考えながら、生徒たちの式典を見ていました。ある先生に尋ねると、カナダは第2次大戦で日本とも交戦しているということなので、図書館で本を1冊借りて読みました。イギリス連邦の一員として、香港守備に当たっていたカナダ兵は戦死もしくは捕虜になり、3年半に渡る過酷な捕虜生活送ったことが生存者の証言をもとに綴られていました。栄養不良と疾病に苦しみ、生きて帰国できた兵士は少数派です。登場する兵士の中には、近隣の町の出身者もいて、ちょっとドキッとしました。私にとっては、日本人であることを考えさせられる日となりました。
今月に入って急に寒くなってきた。今日も雪が降っていて朝学校に行く時でも気温は-5~-10℃と日本の冬と比べるととても寒い。Host familyのアドバイスもあって、車のエンジンオイルやウインドウォッシャー液の交換、タイヤのチェックも済ませた。コートも買ったし帽子や手袋、冬用の靴も買ったり借りたりして準備万端。でもココは本当に乾燥しているので注意している。今、生活のパターンが出来てきて毎日をしっかりと過ごしていこうと心がけている。月・水・金の朝はプールで水泳(Hot tubとサウナがあるがとても気に入っている)、火曜の夜はChoir、木曜の夜は日本語の授業、金曜の夜はCurling、もちろん昼間は学校で日本語の授業(毎週月・水の2回)とその準備。空いた時間は他の授業や英語の勉強に当てている。毎週金曜の午後にCarolと翌週の予定を確認している。最近特に感じるのは、ここPeace Riverの人たちは、実はものすごく保守的なのではないかということ。一見みんな明るいし、とても親切だが、何か新しいことをする時には、ものすごく慎重になるし、中には一切試しぁw)トみようとさえしない人もいる。これは年齢や性別、住んでいる地域などにはあまり関係ないようだ。日本人は、第一印象が静かだし、比較的控え目に映るようなのだが、初めてのことに取り組むのに興味が沸くし、もし可能ならちょっと改良して試し続けたりする。最初は人によるのかとも思ったがどうもこの傾向は変わらない。一方、反対に日本に来ている海外の人が日本でいろんなことに興味を抱く姿勢と似ているのかも知れない。滞在してみて日本で考えていたことと違うことがたくさんあって非常に面白い。あと、最近、特定の話題についてはものすごく英語が聞きやすく感じるようになってきた。でも現地の人の日常会話のあのものすごいスピードでの会話は未だにものすごく苦労している。まだまだです。
プレゼンの方での最近のヒットは、YouTubeで偶然見つけた日本の住宅紹介のビデオです。これまでいくら説明しても私の英語力では理解してもらえなかったBathroomの構造や「縁側」もバッチリ、「百聞は一見に如かず」です。また、日本在住の方が英語で紹介しているので、余計な説明をせずにビデオを見せて、"What did you find about this house?"と質問すると生徒参加型の授業になるという効果もあります。YouTubeサマサマ、SmartBoardサマサマ、です。
Origami "A Dog (face) and A Cat( face)" and " Overturns Frog"
1 はじめのあいさつ(あいさつの指導)
Good afternoon, everyone! We say "Konnichiwa" for "Good afternoon". Please repeat after me. " Konnichiwa" Today I am here to teach you how to fold origami.
2 折り紙の紹介
Origami is one of traditional Japanese paper craft arts. You can make many shapes simply by folding a small square paper. Japanese children are taught how to make origami by their parents or grandparents. Sometimes they learn in kindergarten or preschool.
3 DVDを見せる(持参したNHKのトラッドジャパンのDVD)
Here is a DVD about origami. First please enjoy watching it.
4 折り紙を配る
Now let's fold "A Dog face and A Cat face". This is an example of how we are going to fold. I will give you a piece of origami paper. Please take your favorite color from the papers I am handing out.
5 折り方をワンステップずつ教える(折り紙指導の便利なサイト http://en.origami-club.com/)
I will show you how to fold origami first. Please follow my directions for folding.
※折った後に、日本語指導
We say "inu" for a dog. Please repeat after me. " Inu"
We say " neko" for a cat. Please repeat after me. "Neko"
6 時間があればもう一つ別の折り紙を教える(時間調整)
We have ○ more minutes. Let's fold another origami. I will teach you how to fold"Overturns Frog". Please take your favorite color from these papers again.
※折った後に、日本語指導
We say "kaeru" for a frog. Please repeat after me. " Kaeru"
7 おわりのあいさつ(あいさつの指導)
That's all for my lesson. I hope you enjoyed this origami lesson.
Thank you for inviting me to your class today.
We say "Arigato" for "Thank you". Please repeat after me. "Arigato"
We say "Sayonara" for "Good bye. Please repeat after me. " Sayonara"
授業リスト例
①折り紙(おりがみクラブのサイトhttp://www.en.origami-club.com/を使用して子どもたちの年齢に応じた教材を考えます。折り紙の経験が少ない子どもにとって、いきなり鶴の指導は少々無理があります。時間数はあくまで目安。目安でも先生方にとっては、授業時間をどれだけ日本文化の授業に当てるか計画する上で必要です。)
・犬と猫の顔 (10分)折ったあと、言葉の指導をも入れてあげます。(inu,neko)
・カエル(12分)折ったあと、言葉の指導をも入れてあげます。(kaeru)
・新聞紙を使ったかぶと(かぶれるので大人気!)(15分)
・紙風船(20分)もし、1~10の数え方を先に指導できていたら、日本語で数えてもらいながら遊んでもらいます。
・おすもうさん(25分)
・鶴(30分)
・はばたく鳥(30分)
・ピカチューの顔(30分)
これは本当に大人気です。以下に参考のサイトです。http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/4737/pica/picae.htm
②紙芝居(デジタル絵本サイトhttp://www.e-hon.jp/から紹介しています。それぞれ10~15分)
・桃太郎(この後に、歌指導を入れたりしています。)
・鶴の恩返し(この後に、折り鶴指導を入れたりしています。)
・おむすびころりん(おむすびを作って行って見せてあげる、または自分たちでも作ってみるなども楽しいですね。)
・かさじぞう(年末近くに読みたいですね。)
・はなさかじいさん
・さるかに合戦
・金太郎
③盆踊り(CDと浴衣持参)30分
東京音頭、河内音頭など
④1~10までの数え方(10分)
⑤日本の子どもの日の紹介(30~40分)
5分程度日本の子どもの日を口頭と写真で紹介。(こいのぼり、食べ物、五月人形など。)
かぶとを新聞で折る。(どの学年でも大丈夫)
鯉のぼりを折り紙で折る。(高学年)
⑥日本の歌(20分)
・こぶたぬきつねこ(この後に、折り紙のネコやブタを入れたりしています。)
・きらきら星
・桃太郎さん
これは、紙芝居の後紹介しています。英語の歌詞を入れています。
MOMOTARO-SAN MOMOTARO-SAN
GIVE ME YOUR KIBIDANGO
WHICH IS HANGING ON YOUR WAIST
YARIMASHO YARIMASHO(持参したCDがこのように歌ってます。)
IF YOU FOLLOW ME TO BEAT ONIS
SHALL WE GO TO ONIGASHIMA
・チューリップ
⑦書道(45分)墨汁5本と筆(大30本 小20本)持参。硯は、紙コップ。下敷きは、新聞紙で代用。文鎮はなし。
・カタカナで自分の名前(名簿を事前に先生からいただき、筆順と共にお手本を書いてあげます。時間がかかりますが、大変喜ばれます。
・日本の「日」これは書きやすいです。
・友達の「友」この漢字は、先生方が生徒に指導して欲しいと思う漢字で、生徒がまあまあ書きやすいものです。
⑧お箸の使い方(30分)
プレゼンテーションでお箸の使い方を説明したら、ポップコーンつかみレースをします。
30秒でいくつつかめる?2~3ゲームしてあげます。これはもう大好評です。
ただし、食べ物はアレルギーなどあるので、担任の先生と綿密な打ち合わせが必要です。
以上が授業リストです。
以下参考までに・・・
●授業の導入に使うため、NHKのトラッドジャパンの日本の文化が紹介されているDVD全6巻を持参しました。1つのテーマで3分で英語で端的に紹介されています。カナダでは、再生できないDVDプレイヤーもあります。自分のパソコンからだとOKです。その場合、プロジェクターを使います。また、教室でスマートボードが使えたら見せてあげられます。
●世界中でピカチュウは大人気
私はおしゃべりピカチューのぬいぐるみを持参しました。(大きい目)
授業に行くときや、朝や帰りのあいさつの時は必ずピカチュウを抱いています。
ピカチューの顔の折り紙指導にも便利です。(顔を描く時。)
でした。日本では、こんなに多くの時間を割くことは出来そうにありませんが、年度の初めに、保護者に学校に来てもらって話し合いを持つことには、メリットが大きいだろうと感じました。
私のスケジュールも今週(12日~)になってから決まってきました。また準備に追われることになりそうです。昨年は小・中3校に日替わりで行っていましたが、今年は、当面、小・中1校ずつということになりました。少し落ち着いて仕事ができそうです。
マニトバは、9月に入っても25度を超える日が続き、みんな、今年は異常だと言っていました。暑いといっても空気が乾燥しているので、日本人の私にはさわやかに感じられます。私はずっとこのままであってほしいと思っていますが、今週は一気に涼しくなりそうです。そして11月には冬が・・・。
Maple Leaf 小学校に来た体育の先生は、以前に日本人インターンと仕事をしたことがあると言って、彼女が、スポーツ・チームが近隣の学校まで遠征するのにバスで1時間かかると知って、驚いていたという話をしてくれました。北海道出身の私にとっては、驚くほどではありませんが。その他には、Tim Hortons(カナダではスタバよりメジャーです)で偶然出会った人が、奥さんが日系でランチに招待されたりとか、いろいろと変化のありそうな9月です。
すでに数回学校訪問を行い、所属しているJapan-America Society of Hawaii独自の日本を紹介するプログラムを見学する機会がありました。覚えること、学ぶことがたくさんありますが、楽しみながらプレゼンができるようになれるといいなと思っております。
教育プログラム以外でも、これから年末に向けての行事がいろいろ予定されています。そちらにも可能な限り参加し準備等のお手伝いができればと思っております。
一般生活もサイクルが出来上がった上に少しだけ周囲を見る余裕ができてきました。仕事関係以外の人々ともできるだけ触れ合う機会が作れればいいなと思っております。
私が研修させていただいているカナダの小学校は、6月25日~9月5日までが夏休みです。この2ヶ月以上の長い夏休みの予定は、前もって5月の初め頃からホストファミリーと何回か相談させていただき決めました。
私の中でまず思い浮かんだ夏休みの計画は、カナダと言えば、ナイアガラフォールズや赤毛のアンのプリンスエドワード島を見ておくべき?はたまた、友人の住むモントリオール訪問?・・・でした。が、ホストファミリーのお誘いを受けて、ホストファミリーと一緒でしかできないバケーションにしようと決めました。
まず、7月中旬頃、ホストの運転する車で、車窓から見える雄大な自然を満喫しながら(夏でも少し雪をかぶった美しい山々、たくさんの湖や滝、野生のクマやシカも時折発見!)、バンクーバーに約18時間かけて向かいました。途中、ホストの娘さんが住むプリンスジョージで一泊しました。バンクーバーでは、UBC( University of British Columbia)の宿泊施設に一週間滞在し、ホストの校長先生が夏期レクチャーを受けている間、私はバンクーバーのダウンタウンに毎日出かけて観光、買い物を楽しみました。二週目は、ホストの実家のあるペンティクトンに滞在しました。バンクーバーからは車で約4時間のオカナガン湖とスカハ湖の挟まれたリゾート地です。湖に泳ぎに又は散歩に出かけたり、いくつかの果樹園やワイナリーを訪ねたりしました。その週末には、今度は、ホストの親戚の集まりの会に出席するため、世界中から旅行者が集うトフィーノと言う海辺のリゾート地に行きました。集まった親戚の方々みんなでカニを食べたり、地域の夏のイベントに出かけたり、海辺の散歩や森のハイキングを楽しみました。そしてまたペンティ
クトンに戻り、近隣の街、ケロウナやオソイウスに案内していただきました。このようにして、約3週間、ホストファミリーやそのご親戚の方々と楽しく過ごさせていただきました。
8月1日から4週間は、今のホストと離れて単独行動に移りました。
まず、最初の1週間は、日本から迎えた友人たちとバンクーバーやビクトリア、ウイスラーを旅しました。
そして、次の3週間は、昨年IIPを通して知り合ったアメリカの元ホストファミリーを訪問しました。アイダホにある山の別荘にご招待していただいたのです。約1年ぶりの再会は感動でした。アイダホでは、山や森、湖へのハイキング、サイクリング、Yellowstone National Park およびGrand Teton National Parkへの観光、地元の街歩き、ビール工場、ファーマーズマーケット、野外音楽フェスティバル、ロデオショー、プライベート用の飛行場見学、カヤック、魚釣り、乗馬をしながら山の散策約2時間、ミュージカル鑑賞・・・など一緒に楽しませていただきました。アイダホでもまた、大自然を満喫できました。色とりどりの野の花の向こうにそびえる雄大な山々の眺め、美しく青く澄んだ湖、オレンジ色のサンセット、山の上にぽっかりと浮かぶ月に、毎日心が本当に癒されました。エルクやバイソン、ムース、シカ、リスなどの野生の動物との出逢いもあちらこちらでありました。
以上、個人の旅行では絶対できないと思われる、今の、また、元のホストファミリーの方と一緒にいたからこそ出来た数々の大自然や人々との出逢い・・・この夏休みの全ての経験もまた、私の一生の宝物で
Calgaryからは、GreyHound(バス)でJasperへ。1日観光した後、VIA鉄道でPrince George(British Columbia州)へ。Canadian Rockyの山々はそんなに高くはありませんが、厳粛な雰囲気をたたえ、水はエメラルドに輝きます。鉄道のチケットはラッキーなことに半額($140)でした。
Prince Georgeから車で1時間ほど北西に行った、Vanderhoofという町に、私のホストの兄、Gordonが住んでいます。彼とは5月にOntarioで一緒に釣りをしている既知の仲です。trout釣りのほか、製材所見学や彼の仕事に同行したりと、他ではできない経験でした。彼は林業で働いています。収入はいいけれど、きつい仕事です。家は、森の中の5エーカーもの広さの土地にあります。表通りは森の中の一本道みたいですが、木々の背後に、そんな広い家が何十軒も続いています。約30年前に$30,000で土地を買い、トレーラー・ハウスで暮らし始めたそうです。当時は本当に森でした。木を切って土地を広げ、$53,000で家を建てたのが20年前。きれいな庭つきのこの家の現在価格は$350,000になります。彼はリタイアしたら、家を売って、夫婦2人で小さな家に移るつもりです。日本では不可能ですね。土地価格が高いのは仕方ないとしても、中古住宅は高値では売れません。不動産の仕組みが違うのだと思います。羨ましくなる話です。
中学校ではDiversity Day(多文化の日)というのがあり、私は巻きずし作りを手伝いました。500名以上の生徒全員に体験させる必要から、フードプロセッサーでみじん切りにしたキュウリとニンジンを太巻にするという、日本では考えられない巻きずしで、とてもうまいとは言えない代物でした。「日本の巻きずしはこんなものではないよ」と言いたいところですが、問題はそれ以前のところにあります。「海苔」です。「この寿司は海苔がダメだね」なんて言う日本人はいないと思います。日本人がほとんど問題にしない海苔が彼らの最大のハードルです。海藻が全く食べられない人はかなりの数になります。彼らには海藻を消化する酵素がないという研究報告もあるそうなので、嫌いなのは自然なことなのかもしれません。食文化を伝えることの難しさを感じた1日でした。
フィンランドには独自の文字、Finアルファベット(アルファベットの上に点々がついたりする)があり、発音の仕方も英語とは異なる(ABCはアーベーセー)。また、フィンランド語にはシャシュショやザジズゼゾなどの発音がないため、練習しなくてはならない。しかし、英語に共通する点が多いため、平仮名、片仮名、漢字という全く異なる文字を使っている日本の子ども達よりも、英語にはなじみやすいだろう。
授業内容としては、例えば、4年生の授業(週4時間)では、最初に How are you? What's up? What day is it? What's the weather outside? What time did the school start? What time will the school end? など毎回同じ質問を1人ずつ答えている。教科書は、リーディング用、問題集用と2つの教科書があり、教師用指導書にはワークシートや掲示用のイラストやカード、単元末のテストなど、あらゆるものがつまっている。
また、教科書に合わせたCDもあり授業で使うことも多い。基本的に教科書に準じて授業を行い、宿題も何ページまでと告げられる。参観した授業では、教科書に出てきたbig・pigの発音の違いを口の前に紙をもたせて練習していた。また、単語テストが日本の漢字テストのようにあり、単元ごとのテストもある。テストでは、リスニングや英作文の問題もある。
ブリティッシュコロンビア、プリンスルパートから車で20分ほどのところにある、ポートエドワード小学校で研修をさせていただくことになりました。幼稚園からグレード7年(日本で言う中学1年生)までが学んでいる、複式学級3クラスの児童数約70名の小さな小学校です。各クラス20~24名です。
最初の1週間は、学校の全体の様子、また学校生活をつかませていただくため、各クラスの参観をお願いしました。行った初日は、各クラスに自己紹介をしに行きました。挨拶のカードをあらかじめ作成して行きました。(常に使うと思われる物、おはようございます。こんにちは。こんばんは。さようなら。ありがとう。またあした。の6つを用意しました。)
挨拶文は、あらかじめ先生用、生徒用に分けて作成しておき、ホストに事前に間違いをチェックしてもらったものを握りしめていきました。当然何度も繰り返し言う練習をしているので、ほぼ暗記していたのですが、念のためです。私のように英語に自信のない方には、あらかじめセリフを用意して何度も声に出して読んでおくことはお薦めの方法です。
私は、まずは「おはよう。」を覚えてもらうことにしました。そのため、毎朝、持参したピカチュウのぬいぐるみと共に、「おはよう。」のカードを持ち、登校時間に合わせて学校の入り口に立ち、子どもたち一人ひとりに挨拶をすることにしました。「Good morning」「おはよう」を何度も繰り返し言います。毎朝、子どもたちを挨拶しながら迎えることで、自然に覚えてもらえることをねらっています。ピカチュウ抱いていると自然と子どもの注意を惹きます。どの子もがんばって日本語で挨拶してくれるようになりました。「さようなら」「またあした」も同様です。帰る時間に合わせて子どもに繰り返し挨拶します。授業の初めには「おはよう」か「こんにちは。」授業の最後には、今日は私を教室に招いてくれて「ありがとう」「さようなら」を使います。「こんばんは。」は、なかなか使う機会がないのですが、必ず数人は「Good evening」は日本語でどういうの?と聞いて来ます。それに備えてぜひ準備しておきたいものです。
挨拶もそうですが、私は「繰り返し」を大切にして授業をさせていただこうと考えています。「1~10」の数え方を教えたクラスで、次にもし歌の授業をお願いされたら、「今日の歌の授業の前に、前の授業の数え方の復習をしましょう。覚えているかな?」と、「1~10」の数え方のレッスンの教材を提示します。次に、もし盆踊りのレッスンをする機会が与えられたら、数え方と歌の復習をしてから盆踊りを教えるのです。復習なのでそんなに時間は取られません。繰り返しの中で定着をねらえたらいいなと思います。
ホスト・ファミリーはMelとRhondaの夫婦2人です。Melは熱狂的ホッケー・ファン(ここでは、アイス・ホッケーとは言いません)なので、試合がある日は必ず、一緒に観戦しています。子供のころ、テレビでよくホッケーを見ていたのが、今、役に立っています。Rhondaは、あまり料理が得意ではありません。平日はRhondaが夕食を作りますが、インスタントなものが多いです。そんなRhondaですが、気遣いのある人で、私が困っていると、察して助けてくれます。私にはいいホストです。
食事にはすぐに慣れました。私の場合は、毎日ヨーグルトを食べていれば、胃腸の調子も上々です。食事も予想に反して、(失礼ながら、写真を見てそう思っていたのですが)脂っこくないですし、甘すぎるデザートもありません。その上、Melはすし好きで、時々巻きずしを作ります(一緒に作ることもあります)ので、短粒米が食べられます。
問題は会話です。最近では、以前より会話も弾むようになったかなと思うこともありますが、予想外の展開では全く言葉が出てきませんし、聞き取りは依然ダメです。ネイティブ同士の会話には、速すぎて聞き取れないので入っていけません。ホッケーの実況は聞き取れるようになってきたのですが(笑)。学校では、準備をしていくので、発音が悪くても話すことはできます。が、生徒の質問が聞き取れないことが度々あります。彼らの英語が教科書通りではないのも一因のようです。
学校のシステムの違いはかなりカルチャー・ショックでした。中学校はgrade5-8で、各クラス30名以下ということは事前に聞いていました。講義よりもプロジェクトが授業の中心というのも予想していました。驚いたのは、教科担任制ではなく小学校のようなクラス担任制であること。体育と音楽には教科担任がいますが、それ以外の教科は基本的に担任が教えます。小学校も同じです。事前のメールのやり取りではそこまでわかりませんでした。職員室もありません。教室には教員用に引き出しのある大きな机があり、彼らはそこで授業準備などの作業もしています。また、教室中に棚があり、各授業に必要なもの、はさみ、のり、絵具から辞書・事典までいろいろそろえています。教室内は乱雑ですが機能的です。
私の場合、教員経験が先入観になっていて、事前に積極的に動くことができませんでした。日本に関する科目はないと言われたのです。短期間であれば、それに合わせて時間を当てることができますが、1年間通して非正規の授業に時間を当てるのは無理だろう、先生方とコンタクトを取りながらゲリラ的に授業をしたり、地理でアジアを扱う際に話をさせてもらったり、といった形になるのかと思っていましたが、杞憂でした。常識的に考えれば、いろいろやってほしいことがあるからインターンを受け入れるのですよね。こちらでは、先方の事情などはあまり気にせずに、自分のしたいことを最初から言ったほうがいいようです。
先日、震災に関する署名コラムが掲載されました。オピニオンページは地味なので、どの程度読まれているのか分からなかったのですが、掲載された個人アドレスあてに30通以上のメールをいただき、励みになりました。本当に1文だけの感想から、支援策の提案、果ては日本旅行の相談まで。今は、彼らと連絡を取っている最中です。