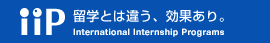インターンシップなら iiP !! 語学留学やワーキングホリデーより効果あり。
iiP-インターンシップ Top > インターンシップと語学留学やワーキングホリデーとはどこが違うか> インターンレポート抜粋
> 報告書
> 報告書
| インターンシップ参加者のインターンレポート |
| ◆こうしたことは本当に日常茶飯事 |
日常茶飯事と聞くと、やはり国民性の違いと言わざるを得ませんね。でもあせっても何もならない、郷に入っては郷に従うだけですね。こんな苦労もいい経験です。 |
| Thailand/EU/カレッジ/Mr. H.N. ( 06/04〜07/05 ) |
タイは4月が真夏。夏の真ん中にタイ正月(今年は4月13日から)があります。 タイ正月ソンクラーンの水掛祭りではチェンマイが最も有名ですが、それには昨年参戦したので、今年は休暇中にマレーシアを訪れることをしました。 6年前にマレーシアの高校生を1年間ホストファミリーとして預かったので彼女とご家族を再訪しようという企画です。 今朝宿舎の受付から「タクシー来ている」と突然呼ばれましたが、これは明日の空港への送りを予約したのを間違えて来たもの。 こうしたことは本当に日常茶飯事で、例えば先月、大学生の娘がこちらのNPOで2週間のフィールドワークをした時に、最終日に迎えに行って、私の宿舎で荷物を整理したあと空港に送るという段取りを決めました。 予約しておいたタクシー(知り合って間もなかったのですが比較的信頼できると思われた運転手に個人的に頼んでありました)が来ないので電話すると「今日は行けない」と。。 しかたなく他のソンタウ(乗り合いタクシー)を呼んで娘を迎えに行って、2時に宿舎にもどったときに、5時の空港への送りもお願いしました。5時になっても来ないので(もう、やはりという感じ)電話をすると「あっ、忘れてた」といって急いで(すごい笑顔で)やってきます。 人は悪いとも思えないのですが、こんな感じ。これに比べるとツアーのガイドなどは約束を破ることはまずないようですし、個人的な友人も、日本語学科の個人的なレベルの問題以上に、会社の運営システムとか規範に問題があるのかも知れないし、結局それで許されてしまうという環境があるのだと思います。 こんな時、日本人は「国民性」「文化」と言いたくなるのですが、明治の最初に日本を訪れた英国人はこのように書いています。「当時は一般の人々は時計を持たなかったし、また時間の厳守ということもなかったのである。2時に招かれたとしても、1時に行くこともあり、3時になることもあり、もっとおそく出かける場合もよくある。」(アーネスト・サトウ『一外交官の見た明治維新』)。 いろいろな人と出会って思うのですが、「○○人は」と決めつけるのは最悪だし、文化を固定的なものととらえてもいけないと思いますが、逆に、全ては「人による」ということでもなく、人のおかれている状況を見ていく態度が必要かと考えさせられます。 |